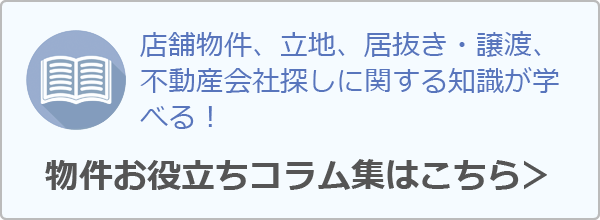その場所、飲食店は開業OK?店舗兼住居は大丈夫?知っておきたい「用途地域」の知識
2025年3月31日
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
契約前に「用途地域」の確認を!
日本では、暮らしやすさ、働きやすさ、利便性、景観などを守るため、地域ごとに建築できる建物の種類、用途の制限が定められています。この制限は「用途地域」と呼ばれ、全部で13種類に分類されています。用途地域によって飲食店開業が許可される地域、許可されない地域に分かれているのです。
開業したい建物が見つかったら、はじめに用途地域を確認することが非常に大切です。「以前に飲食店が入っていた建物だから開業できる」と断定することはできません。以前入っていた店が、無許可営業をしていた可能性はゼロではないためです。
反対に、「過去に開業できないエリアだったけれど、現在はできる」というケースもあります。これは、人口減少や建物の老朽化、街の機能と産業の維持と発展などを鑑み、用途地域はおおむね5年ごとに見直しがされているためです。
また、用途地域ごとに建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と、容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)も定められています。改築や増築時により用途地域の制限を受けることもあり得るので注意してください。
用途地域を知りたいときに調べる方法は?
用途地域を指定するのは、国や都道府県ではなく市区町村長。そのため、市区町村の都市計画の担当部署に問い合わせればすぐに確認することができます。最近では、ほとんどの自治体がホームページ上に用途地域がわかる地図などを公表しています。自治体のホームページを見たり、「○○(調べたい都道府県名や市区町村名)+用途地域」と検索したりすれば調べることができます。例えば東京都なら、都市整備局のHPで確認が可能です。
こうしたサイトを使うことには、用途地域以外に、公共施設やハザードエリアといった知っておくと役立つ情報が同時に得られるというメリットもあります。
出店エリアを決めかねていて、資料を集めている段階ならば、国土交通省が運営している「国土数値情報ダウンロードサイト」がおすすめです。【参考 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A29-v2_1.html】都道府県別に用途地域データをダウンロードできます。
注意すべきは、「建物のすべて」が営業可能な用途地域に入っていないと開業ができないことです。建物によっては「用途地域の境にある」「2種の地域をまたぐ」ケースもあるため、地図を見て判断に迷うときは必ず自治体に確認してください。
「サイトにより用途地域情報の作成時期が異なり、判断に迷う」「地図を読むのが得意でない」ときにも窓口問合せを活用しましょう。
用途地域にはどんなものがある?13種類の用途地域一覧
用途地域の種類は、大まかに住居系と商業系、工業系に分かれています。さらに都市計画の面から住居系は8地域、商業系2地域、工業系3地域に分かれます。まずは全地域をご紹介します。【住居系】
〇第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で、建てられる高さは10mもしくは12m。一戸建て、低層マンション、幼稚園や小中学校が建築可。閑静な住宅街を保護するため、店舗や大規模な施設の建設は厳しく制限されています。
〇第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域。第一種低層住居専用地域の建築可能建物に加え、150㎡以下の店舗や事務所(コンビニや飲食店)が建築可。日常生活に必要な小規模な利便施設が認められています。
〇第一種住居地域
住宅の環境を守る地域。大規模な工場や倉庫、店舗や事務所、ホテルやパチンコ店も建築可能。住環境を保護しつつ、ある程度の利便性も確保する地域です。
〇第二種住居地域
主に住宅の環境を守る地域。第一種住居地域の建築可能範囲に加え、カラオケ店やボーリング場、危険性のある工場も可。より幅広い用途の建物が認められ、多様なニーズに応える地域です。
〇準住居地域
国道や県道などの幹線道路沿いが設定されることが多く、自動車関連施設と住環境を調和させた地域。自動車修理工場、劇場や映画館などのエンターテイメント施設も建築可。幹線道路の利便性を活かしつつ、住環境への配慮もなされた地域です。
〇田園住居地域
農業と調和した低層住宅の環境を守る地域。住宅や教育施設、病院、さらに農産物直売所や農家レストランも可。都市部でありながら、農業と共存する地域として、独特の景観が保たれています。
〇第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域。建物の高さ制限はない。教育施設、病院などが建築可。中高層のマンションなどが立ち並ぶ、都市型の住居地域です。
〇第二種中高層住居専用地域
第一種中高層の建築可能建物に加え、1,500㎡以下の店舗や事務所も建築できる。利便性と住環境のバランスが考慮された地域です。
【商業系】
〇近隣商業地域
周辺に住む住民が生活に必要な買い物などをするための地域。小さな商店が集まった駅前商店街から中規模以上の商業施設まで建設可能。地域住民の日常生活を支える商業施設が集まる地域です。
〇商業地域
商業をメインとする地域。ターミナル駅があるようなエリアで、繁華街やオフィスビルなどが並ぶ。都市の中心部として、多様な商業活動が展開される地域です。
【工業系】
〇準工業地域
軽工業の工場と住宅、店舗が混在する地域。危険性や環境悪化のおそれがある工場や施設をのぞき、ほとんどの建物が建築可能。工業と住宅が混在し、多様な都市機能が共存する地域です。
〇工業地域
工業を中心とした地域。危険性や環境悪化のおそれがある工場や施設が建築可能だが、病院や教育施設などは不可。大規模な工場などが集積し、都市の産業を支える地域です。
〇工業専用地域
工場のための地域。どんな工場も建てられるが、13種類の用途地域の中で唯一住宅が建てられない。店舗や飲食店も不可。工場の操業に特化し、住環境への影響を排除した地域です。
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
飲食店が出店できる用途地域と出店できる面積制限のまとめ
開業の制限から見ると、飲食店は3つの形態に分けられます。飲食店や喫茶店、深夜に酒を提供する飲食店(バーや居酒屋)、接待等が伴う飲食店(スナックなど)です。■飲食店や喫茶店が営業できる地域
工業専用地域を除き、どの地域でも開業できます。ただし、住宅専用地域では制限があります。・第一種低層住居専用地域
店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもののみ可。地域住民の日常生活に必要な、小規模な飲食店のみ認められています。
・第二種低層住居専用地域
店舗兼住宅で店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは可。喫茶店なら店舗床面積が、15㎡以下で2階以下なら可。第一種低層住居専用地域よりも、やや規模の大きな飲食店が認められています。
・第一種中高層住居専用地域
500㎡以下で2階以下なら可。中高層の住宅地における、地域住民のための飲食店を想定した制限です。
・第二種中高層住居専用地域
1500㎡以下で2階以下なら可。第一種中高層住居専用地域よりも、規模の大きな飲食店が認められています。
・田園住居地域
その地域で生産された農産物を使用する場合は、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計500㎡まで可。農産物を使用しない場合は、店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡まで可。地域で生産された農産物を活用した飲食店を優遇する制限です。
制限のない地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域これらの地域では、基本的に自由な規模・形態で飲食店を開業できます。
■深夜酒類提供飲食店営業届の必要な店が営業できる地域
・近隣商業地域・商業地域
・準工業地域
・工業地域
これらの地域は、深夜の営業が認められる商業・工業地域であり、深夜酒類提供飲食店も営業可能です。
■スナック等、風俗営業1号許可が必要な店が営業できる地域
・近隣商業地域・商業地域
・準工業地域
・工業地域
これらの地域は、風俗営業が認められた地域であり、スナックなどの接待を伴う飲食店も営業可能です。
なお、上記の用途地域ルールとは別に、「保全対象施設(学校や病院など)」の近くでは営業ができないという制限があります。ただし、保全対象施設の対象や規制距離は都道府県により異なりますし、特例があることも。必要に応じて自治体へ問合せましょう。
前述の用途地域一覧からは、エリアごとに環境が異なることが想像できると思います。開業場所を選ぶときには出店の可否だけでなく、周辺環境に目を向けることも必要です。

住宅地に「店舗兼住宅」を建てる時のメリット・デメリット
近年、一軒家の1階を店舗、2階を住宅にして開業するケースが増えてきました。よく聞く店舗兼住宅とは、店舗と住宅の行き来が可能な住宅のことで、建築医基準法では兼用住宅といわれます。一方、中で行き来が出来ないものは併用住宅と言います。用途地域の制限が少ないのは兼用住宅です。「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗を建てることはできませんが、店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは建築可能です。ただし、50㎡とは約15坪なので、小さめの店舗になります。売上を上げていくには店舗のレイアウトに工夫を凝らしたり、テイクアウトに対応したりする戦略が求められるでしょう。また、店舗兼住宅は店舗と住宅の行き来が可能な住宅であるため、店舗部分を賃貸することはできません。
【メリット】
・通勤時間が必要なくなる
・家賃を抑えられる
・家族経営と相性がいい
・経営と、育児や介護を両立しやすい
・将来店を閉めても、賃貸物件にすることができる
店舗兼住宅は、住居費と店舗運営費を一本化できるため、コスト削減につながります。
【デメリット】
・場所選びが難しい(例えば、住宅を重視するエリアを選ぶと視認性が下がる)
・オンとオフがつけづらい
・匂い、害虫の発生が問題になりやすい
・行列や駐車、騒音などが近隣からの苦情につながりかねない
店舗と住居が一体化することで、生活と仕事の切り分けが難しくなる点がデメリットです。
上記のようなメリット・デメリットを踏まえた上で、「第一種低層住居専用地域」以外の地域で店舗兼住宅を建てることを検討してみるのもよい方法です。
用途地域は開業を“制限”する面がある一方で、開業に適した場所を教えてくれるものと考えることもできます。物件・土地探しの際には用途地域の情報を必ず確認しましょう。また、地区計画や建築協定等でその地域で街づくりのルールを定めていることもあります。これらも忘れずにチェックしてください。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
新着記事一覧へ
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
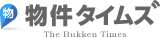



 トップへ
トップへ