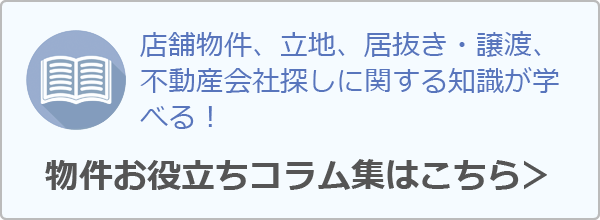飲食店開業「出資金は返さなくていい」は本当? 融資との違いや注意点を解説
2025年10月30日

飲食店開業の夢を実現するため、知人や投資家からの「出資」は大きな助けとなります。しかし、「出資は借金と違うから返さなくていい?」「利益が出たら、どれくらい還元すればいい?」といった疑問は尽きません。出資者とのルールを曖昧にしたまま開業すると、将来深刻なトラブルに発展しかねません。この記事では、飲食店の出資における返済義務の有無から、適切な利益還元の方法、契約の重要性までを分かりやすく解説します。
この記事は、こんな人におすすめです。
・ 飲食店開業のために知人や親族から出資を受けようとしている人
・ 「出資」と「融資(借金)」の違いを正確に知りたい人
・ 出資者への利益還元の相場や方法が分からず不安な人
・ 出資者と良好な関係を築き、トラブルを避けたい人
・ 出資契約書の必要性や盛り込むべき内容を知りたい人
飲食店の出資金「返さなくていい」は半分本当で半分間違い
飲食店開業にあたり、親族や知人から「出資するよ」という申し出があった際、まず頭に浮かぶのは「これは借金とどう違うのか?」「返すべきお金なのだろうか?」という疑問ではないでしょうか。
結論から言うと、飲食店の出資に関して「返さなくていい」と言われていても、それは半分本当で半分間違いです。
本当である理由としては、出資が「融資(借金)」とは根本的に異なるためです。融資、つまり金融機関などからの借金は、契約で定められた期日までに元本と利息を返済する義務があります。しかし、出資は事業の成功を期待して資金を提供してもらう行為であり、元本そのものの返済義務は原則としてありません。
一方で、間違いである理由としては、出資金を受け取った側には、事業が成功した暁には「利益を分配(配当)する」という形で還元することが強く期待されているからです。出資者はリスクを取ってあなたのお店(事業)に投資しているのですから、利益が出ればその見返りを求めるのは当然のことです。
この「出資」による資金調達の方法は、専門的には「エクイティファイナンス(株式などによる資金調達)」と呼ばれます。対して、融資(借金)は「デッドファイナンス(負債による資金調達)」と呼ばれます。この「出資」と「融資」の違いを正確に理解することが、出資者との良好な関係を築く第一歩です。

まずは明確に理解したい「出資」と「融資」の決定的違い
出資と融資は、どちらも開業資金を調達する手段ですが、その性質は全く異なります。この違いを理解しないまま資金を受け入れると、後々「こんなはずではなかった」という事態を招きかねません。
「出資」と「融資」の違いを一覧にまとめました。次項より、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。
| 比較項目 | 出資 (株式や利益配当による資金調達=エクイティ) |
融資 (負債による資金調達=デット) |
|---|---|---|
| お金の性質 | 自己資本(事業への参加) | 負債(借金) |
| 返済義務 | 元本の返済義務なし | 元本・利息の返済義務あり |
| 利益還元 | 利益が出たら「配当」として分配 | 利益に関わらず「利息」を支払う |
| 経営への関与 | あり(議決権を持つ株主・パートナー) | 原則なし(債権者) |
| 資金提供者 | 投資家、親族、知人など | 金融機関、公庫、個人など |
お金の性質:「出資」は事業への参加、「融資」は返済前提の貸付
出資と融資の最も根本的な違いは、お金の「性質」です。
「融資」は、いわゆる「借金」で、金融機関や個人から、返済することを前提にお金を借りる行為です。このお金は会計上「負債」として扱われ、自己資金ではありません。融資のメリットは、決められた利息さえ払えば、どれだけ利益が出てもそれ以上のリターンを求められないことです。デメリットは、赤字でも返済義務があり、負債が増えることで財務状況が悪化することです。
対して「出資」は、あなた(創業者)の事業に「参加」してもらう行為です。出資者はあなたのお店のオーナー(株式会社の場合は株主)の一員となり、事業の成功を一緒に目指すパートナーとなります。このお金は会計上「自己資本」として扱われ、負債にはなりません。これがエクイティ(自己資本)と呼ばれる所以です。
出資のメリットは、自己資本が増強され財務基盤が安定すること、そして元本返済の義務がないことです。対してデメリットは、後述するように経営に関与される可能性や、利益を分配する必要があることです。
返済の義務:利益が出たら「配当」する出資、利益に関わらず「返済」する融資
出資者への返済(正しくは利益還元)と、融資の返済は、義務の発生源が異なります。
融資(借金)の場合、お店が黒字であろうと赤字であろうと、契約で決まった返済日には元本と利息を支払う義務があります。これは絶対的なルールであり、返済が滞れば信用情報に傷がつき、最悪の場合は差し押さえなど法的措置を取られることもあります。
一方、出資の場合は、利益が出なければ「配当(利益の分配)」はゼロ、ということも理論上はあり得ます。出資者は事業のリスクも共有しているため、赤字の年に配当を要求することは通常ありません。ただし、利益が出ているにもかかわらず配当をしない、あるいは赤字が続くようであれば、出資者との関係は当然悪化します。出資者からすれば「返済は求めていないが、利益が出たら配当を出すのは当然だ」と考えているからです。
経営への関与:出資者は「経営パートナー」、融資者は「債権者」
「お金を出してもらうと、口も出されるのでは?」という不安は当然のことです。
融資者(銀行など)は「債権者」です。彼らの関心事は「貸したお金が利息と共にきちんと返ってくるか」であり、返済が滞らない限り、お店のメニューや内装といった日常の経営に口を出してくることは原則ありません。
対して「出資者」は、株式会社であれば「株主」となり、経営パートナーの一員です。出資者は、出資した割合(持株比率)に応じて、会社の重要な意思決定に参加する権利(議決権)を持ちます。つまり、経営に関与する権利があるのです。もちろん、親族や知人の場合、「経営は任せるよ」と言ってくれるケースも多いですが、法律上は経営に口を出す権利を持っているという事実は重要です。
飲食店開業で出資を受けるメリットとデメリット
出資と融資の違いを踏まえ、飲食店開業時に「出資」を受けることのメリットとデメリットを整理します。
■出資を受けるメリット
・ 元本の返済義務がない
これが最大のメリットです。融資とは異なり、万が一事業がうまくいかなくても元本を返済する義務はありません。これにより、特に開業初期のキャッシュフローの圧迫を防げます。
・ 自己資本が強化される
出資金は「自己資本」となるため、会社の財務体質が強くなります。自己資本比率が上がると、将来的に金融機関から追加融資を受ける際にも有利に働くことがあります。
・ 経営パートナーを得られる
出資者は単なる資金提供者ではなく、事業を応援するパートナーです。経営に関するアドバイスや、人脈の紹介など、資金面以外でのサポートが期待できる場合もあります。
■出資を受けるデメリット
・ 経営権(議決権)の希薄化
出資比率に応じて議決権を渡すため、創業者(あなた)の経営権が弱まる可能性があります。多くの株式を渡してしまうと、経営の意思決定が自由にできなくなるリスクがあります。
・ 利益の分配(配当)が必要
事業で利益が出た場合、それを出資者に分配(配当)する必要があります。大きな利益が出た場合、融資の利息よりも多くの金額を支払う(還元する)結果になる可能性もあります。
・ 出資者との関係性への配慮
出資者は株主・パートナーであるため、定期的な業績報告や経営方針の説明が求められます。特に親族や知人の場合、関係性がこじれると精神的な負担が大きくなるリスクも伴います。

飲食店開業で出資者に利益を還元する3つの主な方法
では、無事に飲食店が開業し、利益が出るようになった場合、出資者には具体的にどうやって還元すればよいのでしょうか。主な方法を紹介します。
方法1:株式の配当
最も一般的で正式な方法が、株式の配当です。これは、あなたが「株式会社」を設立して飲食店を経営する場合に用いられます。
決算で利益(税引後当期純利益)が確定した後、その一部を「配当金」として、出資者(株主)の持株比率に応じて分配します。例えば、あなたが70%、叔父さんが30%出資して株式会社を設立した場合、利益の中から100万円を配当に回すと決めれば、あなたは70万円、叔父さんは30万円を受け取ることになります。
いつ、いくら配当するかは、株主総会(あなたと叔父さんの会議)で決定します。
方法2:金銭以外の特典
出資者が親族や知人である場合、飲食店ならではの金銭以外の特典も喜ばれる利益還元策となり得ます。
例えば、「お店での飲食代を生涯無料にするパスポート」や「毎月、季節の特別コースにご招待」、「お店の定休日に家族や友人を招いたプライベートパーティを開催できる権利」などです。
ただし、注意点もあります。これはあくまで出資者との良好な関係を築くための付加価値的なものです。特に高額な出資を受けた場合や、出資者がプロの投資家である場合、こうした特典だけで利益還元の代わりとすることは難しいでしょう。金銭的な配当と組み合わせて行うのが現実的です。
方法3:匿名組合契約(GK-TKスキーム)
「経営には一切口出しせず、利益だけを分配する」という形で出資を受けたい場合に有効な方法として「匿名組合契約」があります。
これは、あなたが「個人事業主」のまま、あるいは「合同会社(GK)」を設立して事業を行い、出資者は「匿名組合員(TK)」として事業から生じる利益の分配だけを受ける権利を持つ、という契約形態です。出資者は経営に対する議決権を持たないため、創業者は経営の自由度を保ったまま資金調達ができます。
この方法は、いわゆるGK-TKスキームとして投資ファンドなどで使われる手法ですが、個人間の出資(例えば、本人とその親族間)でも契約を締結することは可能です。ただし、契約内容が複雑になるため、専門家への相談が不可欠です。
方法4:クラウドファンディング(購入型・出資型)
近年、飲食店開業の資金調達手法として一般化したのが「クラウドファンディング」です。これは、インターネットを通じて不特定多数の人から少額ずつ資金を集める方法です。
特に飲食店と相性が良いのが「購入型」クラウドファンディングです。これは、出資(支援)してくれた見返りとして、金銭(配当)ではなく、商品やサービス(例えば「オープン後の食事券」や「レセプションへの招待」「オリジナルグッズ」など)を提供するものです。これは資金調達であると同時に、開業前のお店のファン作りや宣伝広告にもなる大きなメリットがあります。
ほかにも、利益を金銭で分配する「投資型(ファンド型)」のクラウドファンディングもありますが、まずは購入型が飲食店開業の選択肢として有力です。親族や知人からの出資とは別に、こうした現代的な資金調達を組み合わせることも検討に値します。
ただし、クラウドファンディングによって資金調達する場合はデメリットもあります。開店後しばらくは「リターン」を求める支援者で賑わいますが、実際の売上が立たないという「前借り」現象が起こりえます。魅力的なリターンは支援者を集めますが、開業後のことをしっかりと見通して利用すべきでしょう。

飲食店の出資者には「いくら」渡すべき? 利益還元の相場観
出資者への利益還元について、最も悩ましいのが「どれくらい渡すべきか」という相場観でしょう。
重要なのは「出資比率」
まず理解すべきは、利益還元の額は「いくら」で決めるのではなく、全体の資金の「何パーセントを出したか」で決めるのが基本である、という点です。そして、そのパーセンテージは、開業時に決めた「出資比率(持ち株比率)」によって決まります。
例えば、開業資金が800万円必要で、自己資金300万円、叔父から500万円の出資を受けたとします。この場合、あなたと叔父さんの出資比率(持ち株比率)は3対5(あなた37.5%、叔父さん62.5%)となります。この比率に基づき、将来の利益配当や、万が一会社を売却した際の売却益を分配するのが原則です。
飲食店の創業者(あなた)の経営権を守るためには?
ここで非常に重要な注意点があります。それは「経営権」の問題です。
株式会社の意思決定は、株主総会での多数決(持株比率に応じた議決権の数)で決まります。もし、上記の例のように叔父さんが62.5%の株式を持つと、叔父さんがあなた(創業者)の意見に反対した場合、会社の重要な決定(例えば、取締役の選任や利益配当の額など)はすべて叔父さんの意向で決まってしまいます。
飲食店の経営者として事業をコントロールし続けるためには、創業者であるあなたが最低でも過半数(50%超)、できれば重要事項(定款変更や会社の解散など)を単独で決められる3分の2(約66.7%)以上の議決権(株式)を保有することが強く推奨されます。
「お金は叔父さんが出すが、自分は経営ノウハウやシェフとしての腕を提供する」という考え方もあります。資金(500万円)と技術・労務(金額換算)をどう評価し、出資比率を決めるかは、出資者と事前によく話し合う必要があります。
飲食店の出資者が期待するリターンの相場とは
出資者がどれくらいのリターンを期待しているかは、その人が誰かによって全く異なります。
エンジェル投資家と呼ばれるプロの投資家は、将来の株式上場(IPO)や事業売却(M&A)による大きなリターン(投資額の数倍~数十倍)を期待しています。
一方で、親族や知人(今回の例でいう叔父さんなど)の場合は、「夢を応援したい」という気持ちが先行していることも多く、必ずしも高い金銭的リターンを求めていないかもしれません。「安定した配当(銀行預金の利息よりは高い程度)」や、「お店が繁盛して成功すること」自体をリターンとして期待しているケースも多いでしょう。
ただし、これも思い込みは禁物です。期待値は人それぞれ異なるため、契約前に「どの程度のリターンを期待しているか」をすり合わせておくことが重要です。

飲食店の出資者とのトラブル回避! 契約前に決めておくべき重要事項
出資を受ける上で最も重要なことは、後々のトラブルを避けるために、ルールを明確に書面化することです。
必ず作成する「出資契約書(株主間契約書)」
本記事の例をとると「叔父さん相手に契約書なんて、堅苦しくて水臭い」と感じるかもしれません。しかし、お金が絡むと、どれだけ親しい間柄でも関係がこじれるリスクは常にあります。
むしろ、お互いの良好な関係を将来にわたって守るためにこそ、契約書が必要です。「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いの認識を合わせるために、必ず「出資契約書」(株式会社設立後であれば「株主間契約書」)を書面で交わしてください。
契約書に盛り込むべき項目
契約書には、最低限以下の項目を盛り込むようにしましょう。
・ 出資者名と出資額
・ 取得する株式数(または出資比率)
・ 出資金の払込期日と方法
・ 利益配当のルール(いつ、どれくらいの利益が出たら、どの程度配当するかの基本方針)
・ 経営への関与の度合い(例:役員として経営に参加するか、議決権行使のみか)
・ 株式の譲渡制限(第三者に勝手に株式を売却できないようにするルール)
・ 契約解除や株式買取に関する条項
これらの項目を二人で確認し、合意の上で署名・捺印することで、将来の不安を大きく減らすことができます。
事業撤退時のルール(清算方法)
開業時には考えたくないことですが、万が一、飲食店経営がうまくいかず廃業(閉店)する場合のルールも決めておくべきです。 前述の通り、出資は「融資(借金)」ではないため、元本の返済義務はありません。つまり、お店が失敗して資産が残らなかった場合、出資金は戻ってこない(=ゼロになる)のが原則です。これは出資者が負う最大のリスクです。
この「出資金は戻らないリスクがある」ことを、出資者(叔父さん)に契約前に明確に説明し、理解してもらう必要があります。これを曖昧にすると、廃業時に「貸した金(出資金)を返せ」という、出資と融資を混同した最悪のトラブルに発展しかねません。
不安なら専門家へ相談を。飲食店開業の資金調達
ここまで出資と融資の違い、契約の重要性について解説してきましたが、出資契約は法律や税務が絡む非常に専門的な分野です。
特に、出資比率の決定(創業者の経営権の確保)や、匿名組合契約の活用、出資契約書の作成といった実務は、自分だけで判断するのは危険です。
親族からの出資であっても、必ず税理士や弁護士、司法書士といった専門家に相談してください。彼らは、あなたの状況に合わせた最適な資金調達の方法や、法的に不備のない契約書の作成をサポートしてくれます。
資金調達や契約に関する悩みは、各地域の商工会議所や、日本政策金融公庫などの公的金融機関が設置している無料相談窓口で相談することも可能です。まずはこうした公的機関で情報収集するのも良いでしょう。
本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスを行うものではありません。大切な夢と、応援してくれる人との関係を守るためにも、専門家の助けを借りることを強く推奨します。
飲食店開業の出資に関するQ&A
Q1: 叔父から500万円の出資を受けたら、贈与税がかかりますか?
A1: 「出資」として受け取り、株式会社の設立であれば「株式」を対価として発行(株主になってもらう)、匿名組合であれば「契約」を締結するなど、事業への投資であることが明確であれば、原則として贈与税の対象にはなりません。単に「500万円をもらった」という形になると贈与とみなされる危険性があるため、必ず契約書を作成し、「投資」であることを明確にしてください。ただし、税務の詳細は非常に複雑なため、必ず税理士に確認してください。
Q2: 個人事業主のままで叔父さんから出資を受ける場合、契約書はどうすればいいですか?
A2: 個人事業主のままで経営権(議決権)を渡さずに出資を受ける場合、「匿名組合契約」を結ぶのが一般的です。これは、叔父さんが匿名組合員としてあなたの事業に出資し、あなたは営業者として事業を行い、利益が出たらその一部を叔父さんに分配する、という契約です。この場合も、利益分配のルールや出資金の扱い(返還義務がないことなど)を明記した契約書が必須です。
Q3: 出資金は、お店の運転資金に使ってもいいのでしょうか?
A3: はい、問題ありません。出資金は、飲食店の開業資金(内装費、厨房機器代など)だけでなく、開業直後の運転資金(食材費、人件費、家賃など)に充てることも一般的です。ただし、出資者(叔父さん)には、受け取った資金を何に使うのか(事業計画)を事前にしっかり説明し、合意を得ておくことが信頼関係のために重要です。
Q4: もし利益がなかなか出なかった場合、叔父との関係が悪化しないか不安です。
A4: 最も重要なのは、契約前のすり合わせと、開業後の誠実な報告です。契約時に「飲食店経営はリスクがあり、すぐに利益が出ない可能性もある。出資金はゼロになるリスクもある」ことをしっかり説明し、理解してもらうことが大前提です。その上で、開業後は、たとえ赤字であっても経営状況(売上、経費、課題など)を定期的に(例えば3ヶ月に一度など)誠実に報告し、懸命に経営している姿勢を見せ続けることが、良好な関係を維持するために不可欠です。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
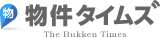



 トップへ
トップへ