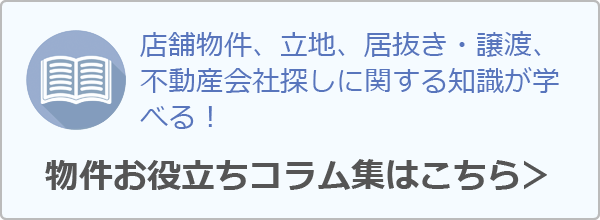飲食店の物件契約における「賃貸借契約書」の重要チェックポイントとトラブル回避術
2025年7月1日

物件契約に関する法的基礎知識と交渉のポイントを押さえておくことは、トラブルを防ぎ、安心して店舗運営をしていくために大切です。そこで、飲食店物件の契約時に見落としがちな「賃貸借契約書」にある専門用語や重要条項をわかりやすく解説します。
不動産賃貸借契約は2種類ある
はじめに知っておきたいのは、賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」があることです。普通賃貸借契約は更新を前提とした契約で、定期借家契約ではあらかじめ契約期間が決まっており、期間満了をもって契約が終了します。その他に次のような特徴があります。
■普通賃貸借契約
・基本的には借主が退去の意思を示さなければ、契約が切れることはありません。・契約期間途中での解約も可能。ただし、賃貸借契約で取り決められている解約予告(借主が貸主に対して解約の意思を通知する)期間を守らなければなりません。例えば解約予告期間が6ヶ月間の場合、解約予定日の6ヶ月前までに通知します。
・貸主から解約を申し入れることもありえます。理由としては家賃の滞納、ごみ問題や騒音、建物の老朽化による建て替えなどが考えられます。ただし、貸主からの解約には「正当な事由」(立ち退きを求めるのに十分な理由)が必要で、これが認められるケースは多くありません。そのため、貸主は「立ち退き料」を支払うことで正当事由を補完するのが一般的です。
■定期借家契約
・書面での契約が必須です。また、貸主は借主に対し、契約前に「この契約は更新がなく、期間満了で終了する」ことを記載した書面を交付して説明しなければなりません。もしこの説明がなければ、その契約は普通賃貸借契約として扱われます。・契約満了により賃貸借契約は終了します。ただし、新たな契約を締結することも可能です。これは新規の契約となるため、借主は契約金を支払う必要がありますし、条件や賃料が変わることもあり得ます。
・契約満了前に借主から解約することは原則できません。ただし、契約に規定があれば可能です。契約満了までの期間の賃料を支払うことが条件になることが多いようです。
定期借家契約を適用することの多い物件は?
どのような物件で定期借家契約が適用されやすいのかを知っておくことも、トラブル回避につながります。商業施設内の物件や、築年数が古い物件がその代表例です。・商業施設内の物件
テナントの入れ替えやフロアの大規模な改装を定期的に行うため、契約期間を定めた定期借家契約が採用される傾向にあります。・築年数が古い物件
将来的な建て替えや取り壊しを計画している場合、スムーズに立ち退きを進めるために、あらかじめ契約の終了時期が定まっている定期借家契約が用いられます。その他には、過去に貸主と借主とで何らかのトラブルがあり、貸主が予防のために契約方法を見直したというケースもあるようです。
まずは内見を。契約前に詳細を確認すべき記載事項を解説
飲食店を開業するための物件契約では、契約書の内容確認と並行して、まず現地に足を運ぶ「内見」が不可欠です。書類だけではわからない、営業に直結するような問題点が隠れていることも少なくありません。内見では、図面と実際の状況が一致しているかはもちろん、厨房設備の動作状況や残置物の有無、給排水管からの異臭や水漏れの跡、上階や隣接店舗からの騒音などを五感で確認しましょう。また、平日と休日、昼と夜など、時間帯や曜日を変えて複数回訪れることで、周辺の人通りの変化や地域の雰囲気をより正確に把握でき、出店後のミスマッチを防ぐことにつながります。
また、内見と並行し、契約書の以下の項目について注意深く確認してください。
■物件内の修繕費用の負担
営業中は様々な修繕が必要になります。貸主と借主の負担区分は明確に定められていますか? 一般的に、小規模な修繕は借主、建物の構造に関わる大規模な修繕は貸主の負担ですが、どの範囲までがどちらの責任かを具体的に確認してください。■水道光熱費の計算や支払いの方法
テナントビルでは、貸主等が電力会社等と一括契約している場合があります。その場合、借主への請求方法は「子メーターを設置して使用量を把握する」「面積に応じて按分する」など様々です。また、請求額に管理手数料が上乗せされることもあります。水道光熱費は経費を大きく左右するため、計算方法や支払い方法に認識のズレがないか確認しましょう。共益費や空調設備費も同様に、負担の有無や計算方法の確認が必要です。
■設備の変更の可否
厨房設備のレイアウト変更、給排水・電気・換気設備の増設や変更などが必要となる可能性があります。どこまでの工事が可能か、費用負担はどうなるかを事前に明らかにしましょう。貸主が工事業者を指定するケースもあるため、合わせて確認が必要です。業者を自由に選べないと、費用が割高になるなど、借主が不利になる可能性があります。
■賃料の改定
賃料は物価の変動や公租公課(国や地方公共団体により、公の目的のために賦課徴収される金銭負担の総称)の増額を理由に改定されることがあります。改定の基準が契約書に明記されていると安心です。特に記載がない場合は貸主に質問してみましょう。■原状回復義務の範囲
退去時は原状回復工事を行うのが一般的です。この「原状回復」の範囲が曖昧だと、退去時に高額な費用を請求されるなど、トラブルの原因になります。「原状」がどのような状態(例:入居時の状態、スケルトン状態)を指すのか、設備の撤去は必要か、床や壁はどこまで修繕するのかなどを明確にしましょう。契約時に現状の図面や写真を添付し、退去時の状態を相互に確認・記録しておくのが理想です。
■保証金(敷金)と償却の条件
保証金(敷金)は、賃料滞納や原状回復費用の担保として貸主に預ける金銭です。退去時に返還されるのが原則ですが、契約内容には注意が必要です。特に「償却」や「解約引」といった条項があると、預けた保証金の一部(例:保証金の20%、賃料の2カ月分など)は、理由を問わず返還されません。この割合は物件によって大きく異なるため、契約前に必ず確認しましょう。償却の有無と、その金額や計算方法が契約書にどう記載されているかを明確にすることが、退去時の資金計画において非常に重要です。
■禁止事項・特約の内容
契約書には、法律で定められた内容以外に、その物件独自のルールである「特約」が記載されていることがほとんどです。飲食店の場合、「深夜営業の禁止」「定休日の指定」「臭いや煙が多く発生する『重飲食』の禁止」といった業態に関する制限が設けられていることがあります。また、看板の設置場所やデザイン、内装工事に関する細かなルールが定められているケースも少なくありません。自店の営業スタイルやコンセプトとこれらのルールが合致するか、契約前に必ず確認し、遵守できない条件があれば交渉の余地がないか確認しましょう。

専門家への相談も視野に
賃貸借契約書は専門用語が多く、複雑な内容を含んでいるため、少しでも不安や疑問が残る場合は、契約を締結する前に専門家へ相談することを検討しましょう。不動産取引に詳しい弁護士や行政書士に依頼すれば、法的な観点から契約書全体をチェック(リーガルチェック)してもらえます。これにより、自社に不利益な条項や、将来トラブルになりそうなリスクを事前に発見できる可能性が高まります。相談費用はかかりますが、後々の大きなトラブルを回避できると考えれば、安心のための重要な投資と言えるでしょう。
物件トラブルは、店舗運営という本業に集中できなくなる大きな要因です。契約書は隅々まで目を通し、不明確な点や少しでも疑問に思う点があれば、必ず契約前に解消しておきましょう。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
新着記事一覧へ
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
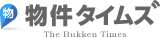



 トップへ
トップへ