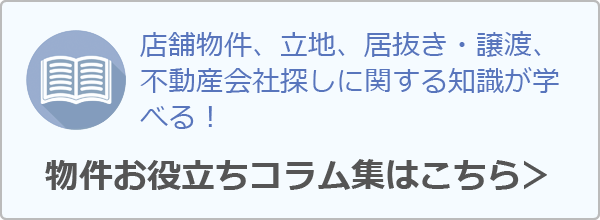【2025最新】「消防法」は飲食店を開業するのに必須の知識! 改正後のポイントも完全解説
2025年9月11日

飲食店の開業において、知っておきたい法律のひとつが「消防法」です。近年、飲食店の火災は増加傾向にあり、お客様とお店を守るための消防法の遵守がより一層重要になっています。この記事を読めば、複雑で分かりにくい消防法の全体像から、あなたの店に必要な設備や手続き、万が一の罰則まで、開業前に知るべき全てが分かります。
・この記事は、こんな人におすすめです
・これから初めて飲食店を開業する方
・内装工事の計画中で、必要な消防設備を知りたい方
・消防署への届出の流れやタイミングが分からず不安な方
・自分の店の規模で、どの消防法の規定が適用されるか確認したい方
・消防法の違反によるリスクや罰則について、正しく理解しておきたい方
「消防法」とは飲食店の開業において重要な法律のひとつ
消防法とは、火災の発生を未然に防ぎ、もし火災が起きても被害を最小限に抑え、人々の命や財産を守ることを目的とした法律です。
飲食店は日常的に火を扱い、さらに不特定多数が利用する施設であることから、火災のリスクが常に伴います。お客様と従業員の安全を確保し、安心して過ごせる空間を提供するため、飲食店には消防法に基づいた厳格なルールが定められています。
飲食店の消防法対策が重要な理由とは
消防法への対応は、単なる法律上の義務に留まりません。
飲食店にとって、事業の根幹を支える重要なリスク管理です。
飲食店の火災は近年増加傾向に
全国の火災件数全体は長期的には減少傾向にありますが、一方で飲食店からの火災は増加傾向を示すデータが報告されています。
例えば、東京消防庁の統計では近年、飲食店からの火災が増加しており、京都市においても令和5年中の飲食店火災は24件と、前年に比べ16件も増加するという憂慮すべき事態となっています。
(参照元:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/kijun/chubou_kasai_guideline.html)
https://www.syou-bou.com/media/2025/03/04/81
出火原因の多くは厨房での調理中にあり、消防庁の分析でも建物火災における出火原因の上位は常に「こんろ」が占めています。
特に飲食店では、調理中に火をかけたままその場を離れるといった不注意に加え、普段目の届きにくい排気ダクト等に溜まった油脂への着火が大規模な火災につながるケースもあり、常に高い火災リスクに晒されていると言えるでしょう。
消防法改正で、飲食店の義務も変化している
こうした状況を受け、法規制も強化されています。
特に大きな変更点が、令和元年10月1日に施行された改正消防法です。これにより、従来は小規模な店舗で義務化されていなかった消火器の設置が、原則として全ての飲食店に義務付けられました。
このように、法改正によっても対策の重要性は増しており、お客様と従業員の安全、そしてご自身の財産を守るために、消防法への対応は「必須の義務」となっているのです。
あなたのお店はどれ?消防法の対象となる飲食店の条件
「自分の小さな店も、消防法の対象になるのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。
結論として、店舗の規模に関わらず、原則としてすべての飲食店が消防法の対象となります。
消防法では、飲食店は「特定防火対象物(5項イ)」という区分に分類されます。これは、火災が発生した場合に人命への危険性が高いと判断される施設群のことで、特に厳しい防火安全対策が求められます。
ただし、求められる義務のレベルは、お店の「収容人数」と「延べ面積」によって変わってきます。収容人数は「従業員の数+客席の数」で計算します。延べ面積とは、お店全体の床面積の合計です。
まずは、ご自身の計画しているお店がどのくらいの規模になるのかを正確に把握することが重要です。
自身の店舗にどのような義務が発生するのか、以下の表で確認してみましょう。
| 店舗の規模(収容人数・延べ面積) | 主な義務 |
|---|---|
| すべての飲食店 | 消火器の設置(※火気設備等がある場合) |
| 収容人数 30人以上 | 防火管理者の選任、消防計画の作成・届出、消防訓練の実施 |
| 延べ面積 300㎡以上 | 自動火災報知設備の設置 ※ |
| 延べ面積 700㎡以上 | 屋内消火栓設備の設置 |
※地階または無窓階の場合、床面積100平方メートル以上の店舗にも設置義務がある
ポイントは「収容人数30人」と「延べ面積300㎡」
上の表で特に重要な基準となるのが、「収容人数30人」と「延べ面積300㎡」という二つのラインです。
もしあなたのお店が、従業員とお客様を合わせた収容人数で30人以上になる場合、「防火管理者」を選任し、消防署に届け出る義務が発生します。防火管理者とは、店舗の防火管理に関する責任者で、消火・避難訓練の実施や消防用設備の点検などを盛り込んだ「消防計画」を作成し、従業員に周知徹底する役割を担います。
また、お店の延べ面積が300㎡以上になる場合は、火災の発生を自動で検知し、ベルなどで知らせる「自動火災報知設備」の設置が義務付けられます。
また、自動火災報知設備は
地階または無窓階の場合、床面積100平方メートル以上の店舗も同様に設置義務があります。これらの基準に該当するかどうかで、開業時の初期費用や準備内容が大きく変わるため、設計段階で必ず確認しておく必要があります。
開業前に揃えるべき、消防法で定められた4つの必須設備
消防法で求められる設備は、大きく分けて4つのカテゴリーに分類されます。これらは、火災の発生から避難、そして消火活動までの一連の流れを想定して定められています。
ご自身の店舗に何が必要になるのか、具体的に見ていきましょう。
(1)火を消すための「消火設備」
まず最も基本的な設備が、火を初期段階で消し止めるための「消火設備」です。その代表格が「消火器」です。
前述の通り、令和元年の法改正により、調理のためにコンロなどの火を使用する設備や器具を設けた飲食店では、原則として店舗の広さに関わらず消火器の設置が義務となりました。特に厨房など火を直接扱う場所の近くには、業務用消火器を設置する必要があります。万が一のボヤを大火事に発展させないための、最後の砦となる重要な設備です。
(2)危険を知らせる「警報設備」
火災の発生をいち早く察知し、店内にいる人々へ危険を知らせるための設備です。代表的なものに「自動火災報知設備(自火報)」があります。煙や熱を感知器が自動で捉え、建物全体に警報ベルを鳴らすシステムです。
先ほど説明した通り、延べ面積が150㎡以上の飲食店など、一定規模以上の店舗で設置が義務付けられています。また、ガスコンロなどを使用する場合は、ガス漏れを検知する「ガス漏れ警報器」の設置も必要となるケースがほとんどです。

(3)安全に逃げるための「避難設備」
万が一火災が発生した際に、お客様と従業員が安全かつ速やかに屋外へ逃げるための「避難設備」も不可欠です。緑色のランプでおなじみの「誘導灯」は、停電時でも避難口や避難経路を示す重要な役割を果たし、ほとんどの飲食店で設置が義務付けられています。
また、店舗が2階以上にある場合や、地下にある場合など、構造によっては「避難はしご」や「緩降機」といった避難器具の設置が必要になることもあります。
(4) 消防隊の活動を助ける「消防活動用設備」
最後に「消防活動用設備」です。これは、火災が大きくなった際に、駆けつけた消防隊が消火活動をスムーズに行うための設備です。
具体的には、消防ポンプ車から水を送り込むための「連結送水管」や、消防隊が活動するための電源を確保する「非常コンセント設備」などがあります。これらは主に大規模なビルや施設に設置されるもので、多くの個人経営の飲食店で直接設置義務が発生するケースは少ないですが、知識として知っておくと良いでしょう。
開業時に必ず行う、消防署への届出と検査の流れ
必要な設備がわかったら、次は行政手続きです。消防法に関する手続きは、適切なタイミングで行わないと、最悪の場合オープンが遅れてしまう可能性もあります。
ここでは、工事開始前から開店までの具体的な流れを4つのステップで解説します。
ステップ1【内装工事開始前】消防署への「事前相談」
これが最も重要なステップです。内装業者と打ち合わせを行い、店舗の設計図や内装プランがある程度固まった段階で、必ず店舗の所在地を管轄する消防署の「予防課(予防係)」へ相談に行きましょう。
「事前相談」では、計画中の内装が消防法に適合しているか、どのような消防設備の設置が必要かなどを、図面を見ながら直接確認してもらえます。
工事が始まってから「この壁は設置できない」「ここに追加の設備が必要」といった手戻りが発生するのを防ぐため、いわば転ばぬ先の杖となる crucial な工程です。相談に行く際は、店舗の平面図や内装の仕様がわかる資料を持参してください。
ステップ2【工事開始7日前まで】「防火対象物工事等計画届出書」の提出
事前相談を経て工事内容が確定したら、次は届出です。収容人数が30人以上の特定防火対象物(多くの飲食店が該当)で、壁や天井などを新たに取り付けたり、改装したりする内装工事を行う場合、工事を開始する7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を消防署に提出する必要があります。
この届出は、これから行う工事が消防法令の基準に適合していることを事前に知らせるためのものです。自身の店舗がこの届出の対象になるかどうかは、事前相談の際に確認しておくと確実です。
ステップ3:【店舗オープン7日前まで】「防火対象物使用開始届出書」の提出
いよいよ工事が完了に近づき、オープン日が現実的になってきたら、次の届出を行います。お店をオープンさせる7日前までに、すべての飲食店が提出義務のある「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ提出します。
これは、「この建物(テナント)を、消防法に則って飲食店として使用開始します」という公式な宣言です。この届出書には、店舗の案内図、平面図、設置した消防用設備の届出書の写しなどを添付する必要があります。
ステップ4:【オープン前】消防署の「立入検査(消防検査)」
防火対象物使用開始届出書を提出すると、オープン前に消防署員が店舗を訪れ、現地で「立入検査(消防検査)」が行われます。この検査では、提出された書類通りに工事が行われているか、必要な消防設備が正しく設置・作動するかなどが厳しくチェックされます。例えば、誘導灯が適切に点灯するか、消火器が定められた場所に設置されているか、避難経路が確保されているかなどを直接確認します。
この検査に合格して初めて、お店をオープンすることができます。もし不備が見つかった場合は、是正されるまで営業は許可されません。
無事合格すると「消防検査済証」が交付され、これが法令を遵守している証となります。この書類は、後の融資や火災保険の加入時に提示を求められることもある重要なものです。

知らないでは済まされない!消防法違反の罰則と注意点
「少しくらいなら大丈夫だろう」「見つからなければいい」といった安易な考えは非常に危険です。
消防法違反は、お客様を危険に晒すだけでなく、経営者自身にも厳しい罰則が科せられます。
違反した場合の重いペナルティ
消防署からの改善命令(措置命令)に従わなかった場合など、悪質な違反に対しては、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」といった重い刑事罰が科される可能性があります。
また、罰金や懲役だけでなく、火災の危険性が高いと判断された場合には、営業停止命令が出されることもあります。そうなれば、お店を続けること自体が不可能になり、投資した資金も夢もすべて失いかねません。
法令遵守は、お金を払えば済む問題ではないのです。
【要注意】居抜き物件に潜む消防法の落とし穴
開業費用を抑えられるため人気の「居抜き物件」ですが、消防法の観点からは特に注意が必要です。「前の店も飲食店だったから、消防設備はそのまま使えるだろう」と考えるのは早計です。
例えば、前の店がカフェで、次にあなたが開業するのが焼き肉店だった場合、火を扱う設備が大きく変わるため、必要な消防設備も変わってきます。
また、客席のレイアウトを変更して収容人数が増えれば、新たに防火管理者の選任が必要になったり、避難経路の確保が問題になったりするケースも少なくありません。居抜き物件を契約する前には、必ず内装プランを持って管轄の消防署に事前相談に行き、現状の設備で問題ないか、追加で何が必要になるかを必ず確認するようにしましょう。
不安な場合は専門家へ相談!安心して開業日を迎えよう
ここまで解説してきたように、飲食店の開業と消防法は切っても切れない関係にあり、その内容は非常に専門的で複雑です。
もし少しでも不安を感じたり、手続きに自信がなかったりする場合は、迷わず専門家に相談することをおすすめします。
内装工事を依頼する設計事務所や工務店はもちろんのこと、「消防設備士」や、消防法関連の書類作成・提出を代行してくれる「行政書士」などが頼れるパートナーになります。
一見、費用がかかるように思えるかもしれませんが、専門家の知見を借りることで、手戻りのないスムーズな計画が進められ、結果的に時間とコストの節約につながります。
あなたのお店を火災リスクから守り、長く愛される場所を築くために、ぜひ専門家の力も活用してください。
飲食店開業の消防法に関するQ&A
Q1. 防火管理者の資格はどうやって取得するのですか?
A1. 防火管理者の資格は、日本防火・防災協会などが実施する「防火管理者講習」を受講し、効果測定に合格することで取得できます。
店舗の延べ面積によって、甲種(2日間)と乙種(1日間)のどちらが必要か変わります。講習の日程は限られているため、開業スケジュールに合わせて早めに計画を立てましょう。
Q2. 消防訓練は、パートやアルバイトも含めて行う必要がありますか?
A2. 必要です。消防計画に基づく消火訓練や避難訓練は、従業員全員が参加できるように計画し、実施する義務があります。
火災はいつ発生するかわかりません。営業時間中に勤務している全てのスタッフが、お客様を安全に誘導し、初期消火にあたれるよう、定期的な訓練が不可欠です。
Q3. 内装に木材をたくさん使いたいのですが、消防法で制限はありますか?
A3. 制限があります。消防法では、火災時の燃え広がりを防ぐため、内装に使用できる材料に「内装制限」を設けています。特に壁や天井には、燃えにくい「準不燃材料」や「難燃材料」などを使用するよう定められている場合があります。
使用したい木材がある場合は、防火塗料を塗るなどの防火処理が必要になることもあります。デザインを決める段階で、必ず内装業者や消防署に確認してください。
Q4. 開業後、消防設備の点検は必要ですか?
A4. 定期的な点検と報告が義務付けられています。設置した消防用設備は、半年に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検を行い、その結果を管轄の消防署長に報告する必要があります(特定防火対象物の場合、1年に1回)。
点検は有資格者(消防設備士など)に行ってもらう必要がありますので、保守点検業者と契約するのが一般的です。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
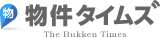



 トップへ
トップへ