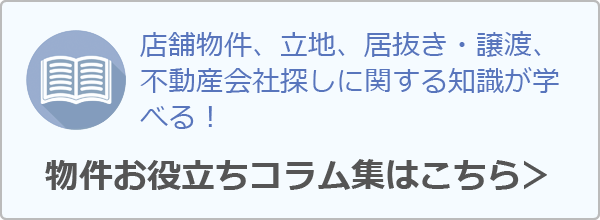【2025年最新】風営法と飲食店の関係を徹底解説! 許可が必要な3つのケースと手続きとは
2025年8月29日
 Photo by iStock.com/agafapaperiapunta
Photo by iStock.com/agafapaperiapunta
風営法は、スナックやキャバクラなどの特定の業種だけに関わる法律だと思われがちですが、一般的な飲食店でも、提供するサービスや設備によっては規制の対象となる可能性があります。
違反した場合、厳しい罰則が科せられ、営業停止に追い込まれることもあります。そうした事態を避けるためには、正しい知識を身につけ、適切な手続きを行うことが不可欠です。
この記事では、飲食店経営者が知っておくべき風営法の基本から、許可が必要になる具体的なケース、申請手続きの流れや費用、そして無許可営業のリスクまで、網羅的に解説していきます。あなたの飲食店が健全な経営を続けられるよう、ぜひ最後までお読みください。
・この記事は、こんな人におすすめです。
・飲食店の開業を準備している方
・自身の店舗が風営法の対象にならないか不安な経営者の方
・ガールズバー、コンカフェ、スナックなどの開業を検討している方
・風営法の許可申請や届出の手続きについて知りたい方
そもそも風営法(風俗営業法)とは?
「風営法」という言葉はよく耳にしますが、その正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、地域の風紀を守り、青少年が安心して過ごせる環境を維持するためのルールを定めた法律です。この法律によって、特定の営業について、営業時間や営業場所、営業方法などが規制されています。
「風俗営業」っていったい何? 再確認してみよう
「風俗営業」には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」、もう一つはいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。ここでは前者の「接待飲食等営業」について詳しく見ていくことにしましょう。接待飲食等営業は下記の5種類に分けられています。■1号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。
■2号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。
■3号営業
カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。カップル喫茶など。
■4号営業
遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。麻雀屋、パチンコ屋など。
■5号営業
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなど。
これらの「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に許可申請を行う必要があります。当然ですが、18才未満の利用は禁じられており、住宅地や学校付近では営業できない、深夜は営業できないなど、様々な規制が設けられています。
 Photo by iStock.com/Kondor83
Photo by iStock.com/Kondor83
飲食店に関わる「接待飲食等営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」
飲食店経営者が特に注意すべきなのが、風営法で定められている営業のうち「接待飲食等営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」の二つです。
一つ目の「接待飲食等営業」は、いわゆる「1号営業」と呼ばれるもので、客を「接待」して飲食させる営業形態を指します。スナックやキャバクラ、ホストクラブなどがこれに該当し、営業するためには都道府県の公安委員会の「許可」が必要です。
二つ目の「深夜酒類提供飲食店営業」は、深夜0時以降に、主食以外の酒類を提供する営業形態です。バーや居酒屋などがこれに該当します。こちらは「許可」ではなく、公安委員会への「届出」が必要となります。
この「許可」と「届出」は大きく異なり、手続きの難易度や期間も変わってきます。
あなたの店は大丈夫?飲食店が風営法に該当する3つのケース
自分の店は該当しないと思っていても、営業の実態によっては風営法の規制対象となることがあります。
ここでは、一般的な飲食店が意図せず該当してしまう可能性のある3つのケースを見ていきましょう。
ケース1:「接待」とみなされる行為をしている
最も注意すべきなのが、この「接待」行為です。風営法における「接待」とは、単にお客様をもてなすことではありません。「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
参照:警察庁ウェブサイト「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf)
具体的には、特定の客の隣に座ってお酌をしたり、会話の相手をしたり、カラオケでデュエットをしたりする行為が典型例です。たとえカウンター越しであっても、特定の客と長時間にわたって談笑するような行為は「接待」と判断されるリスクがあります。料理の提供などではなく、「接待」自体がサービスの中心となると、風俗営業に該当する可能性が高いと考えられます。
ケース2:店内の「明るさ」や「個室」が基準外
飲食店の営業形態によって、風営法が定める店内の「明るさ(照度)」や「仕切り(構造)」の基準は全く異なります。自店の営業形態がどれに該当し、どのルールを守るべきなのかを正確に理解することが不可欠です。
深夜0時以降にお酒を提供する「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしているお店の場合、店内の構造にも注意が必要です。風営法では、客室の床面における明るさ(照度)が20ルクス以下であってはならないと定められています。
また、客室の内部に見通しを妨げる設備、例えば高さが1メートル以上ある仕切りや個室などを設けることも原則として禁止されています。開業前に図面をしっかり確認しておくことが重要です。
ケース3:「ダーツ」や「ゲーム機」の設置方法が不適切
ダーツマシンやシミュレーションゴルフ、テレビゲーム機などを設置しているお店も注意が必要です。これらの設備を設置するだけでは問題ありませんが、お店側が客に遊興をさせ、不特定の客同士が競い合うイベントを主催するなど、積極的に遊び興じさせる行為は「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。
単に設備を置いているだけなのか、それともお店が主体となって「遊興」させているのか、その線引きが重要になります。
風営法の許可を得るための3つの重要要件
風俗営業の許可を得るためには、法律で定められた3つの要件をすべてクリアする必要があります。
人に関する要件(人的要件):欠格事由に注意
風営法ではまず、営業者やお店の管理者になれない人の条件が定められています。これを「欠格事由」と呼びます。例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、特定の犯罪で刑に処せられてから5年が経過していない者、集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者などが該当します。
申請者本人だけでなく、法人の場合は役員全員がこの要件を満たす必要があります。誠実な営業を行うための、基本的な条件といえるでしょう。
場所に関する要件(場所的要件):学校や病院との距離
次に、お店を営業できる場所にも制限があります。第一に、営業が認められている「用途地域」でなければなりません。さらに、学校、図書館、病院、児童福祉施設といった「保護対象施設」の周辺では、一定の距離内での営業が禁止されています。
この距離は、各都道府県の条例によって細かく定められているため、出店を計画する際には、必ず事前に管轄の警察署や役所に確認する必要があります。
出店予定地の市区町村が公開している都市計画図や、各都道府県公安委員会のウェブサイトで、用途地域や保護対象施設に関する情報を確認できます。

お店の構造に関する要件(構造的要件):客室の構造や明るさ
最後に、お店の構造や設備が基準を満たしている必要があります。
・客室の内部に見通しを妨げるような高い仕切りがないこと
・善良の風俗を害するおそれのある写真や装飾がないこと
・客室の床面積が一定基準以上であること
・そして十分な明るさや防音設備が確保されていること
上記が求められます。これらの基準は、申請時に提出する図面によってチェックされます。
風営法の許可申請・届出の手続きと流れ
風営法の対象となる場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは、申請と届出の基本的な流れを解説します。
「許可申請」と「届出」の違いとは?
「許可申請」は、接待を伴う「接待飲食等営業(1号営業)」などで必要となり、警察が要件を満たしているか厳しく審査し、許可が下りて初めて営業を開始できます。
一方、「届出」は、深夜0時以降にお酒を提供する「深夜酒類提供飲食店営業」などで必要となり、要件を満たした書類を提出し、受理されれば営業を開始できます。許可に比べて簡易的な手続きといえますが、もちろん法令を遵守する必要があることに変わりはありません。
手続きの流れと期間、必要書類
許可申請に必要な主な書類は以下の通りです。ただし、申請先の警察署や個別の状況によって異なる場合があるため、必ず事前に管轄の警察署にご確認ください。
・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・賃貸借契約書のコピー、使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図など
・申請者(法人の場合は役員全員)の住民票、身分証明書
・誓約書
※申請に必要な書類の様式や法定手数料の正確な金額については、営業所を管轄する警察署のウェブサイトや、警視庁・各道府県警察本部のウェブサイトをご確認ください。
手続きの一般的な流れは、まず管轄の警察署への事前相談から始まります。その後、膨大な量の必要書類を収集・作成し、申請または届出を行います。
許可申請の場合、申請後に警察署の担当者や風俗環境浄化協会の担当者によるお店の実地調査(実査)が行われ、店舗の構造などが図面通りかチェックされます。すべての審査をクリアして、ようやく許可証が交付されます。期間としては、申請から許可が下りるまで、土日祝日を除いて約55日というのが標準的な処理期間です。
手続きには、申請書のほか、営業方法を記載した書類、住民票や身分証明書、図面類が必須です。
申請にかかる費用としては、まず警察署に支払う法定手数料があります(1号営業の場合、約24,000円)。これに加えて、書類作成や図面作成を行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が必要となります。報酬の目安は、一般的に15万円から30万円程度ですが、お店の規模や申請内容によって変動します。
【業態別】ガールズバー・コンカフェ・スナック… 風営法の注意点
近年多様化する飲食店の業態。
ここでは特に判断が難しい業態について、風営法上の注意点を解説します。
ガールズバー・コンカフェは「接待」なしでも許可が必要?
ガールズバーやコンセプトカフェは、基本的にカウンター越しでの接客が中心のため、「接待」にはあたらないと考える方も多いでしょう。しかし、先述の通り、特定の客と長時間話し込んだり、一緒にゲームに興じたりする行為がエスカレートすれば、「接待」とみなされる可能性があります。
また、これらの業態の多くは深夜まで営業します。午前0時を過ぎてお酒を提供し、かつ、ラーメンや牛丼、定食といった「主食」と認められる食事を提供しない場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必須です。届出をせずに営業すると無許可営業となります。
スナックの接客は接待にあたる?
スナックは、その営業実態から「接待」が行われていると判断される可能性が非常に高い業態です。ママや女性スタッフがお客様の隣に座ってお酌をしたり、おしゃべりをしたり、カラオケでデュエットをしたりする行為は、風営法上の「接待」の典型例です。
そのため、スナックを開業する場合は、原則として「風俗営業1号許可」を取得する必要があります。深夜0時以降の営業はできませんが、風営法のルールに則って堂々と接待営業を行うことができます。
もし無許可営業がバレたら?知っておくべき罰則とリスク
「少しくらいならバレないだろう」という安易な考えは非常に危険です。
風営法の許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合、非常に重い罰則が科せられます。
具体的には、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」という刑事罰の対象となります。また、深夜酒類提供飲食店営業の無届営業にも「50万円以下の罰金」が科せられます。
罰金や懲役だけでなく、営業停止命令などの行政処分を受ける可能性も高いでしょう。一度処分を受けると、その後5年間は風俗営業の許可が取得できなくなります。刑事罰を受ければ前科がつき、社会的信用も失墜するなど、失うものは計り知れません。
風営法のことで悩んだら専門家へ相談を
風営法は、飲食店の健全な経営を守るための重要なルールです。しかし、その解釈は複雑で、手続きも非常に煩雑です。特に、自身の営業が「接待」にあたるかどうかの判断や、許可申請に必要な専門的図面の作成は、一般の方には難しいのが実情です。
もし、ご自身の店舗運営や開業準備で少しでも風営法に関する不安や疑問があれば、専門家へ相談することをおすすめします。適切な手続きを踏み、安心して店舗運営に集中できる環境を整えましょう。
風営法に関するよくある質問
Q1: 普通の居酒屋でも風営法の対象になりますか?
A1: はい、対象になる可能性があります。例えば、深夜0時を過ぎてお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。また、お客様の隣に座って長時間お酌をするなど、従業員の接客が行き過ぎると「接待」とみなされ、風俗営業の許可が必要になるケースもあります。
Q2: 風営法の許可申請は自分でできますか?
A2: 法律上、ご自身で申請することは可能です。しかし、申請には住民票や身分証明書といった公的書類のほか、営業所の平面図や求積図、照明音響設備図など、専門的な知識を要する図面を多数作成する必要があります。書類に不備があれば何度も警察署に足を運ぶことになり、開業が大幅に遅れるリスクもあるため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
Q3: 「主食」とは具体的に何を指しますか?
A3: 風営法における「主食」とは、一般的に米飯、パン、麺類などを指し、社会通念上、主食と認められる食事のことです。深夜0時以降にお酒を提供するお店でも、ラーメンや牛丼、定食といった主食を提供していれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は不要です。ただし、おつまみ程度の軽食しか提供しないバーなどは届出が必要となります。
Q4: 許可や届出をしないで深夜営業をするとどうなりますか?
A4: 許可が必要な「接待」を伴う営業を無許可で行うと、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」という重い罰則が科せられます。また、深夜酒類提供飲食店営業の届出を怠った場合も「50万円以下の罰金」の対象となります。罰則だけでなく、営業停止などの行政処分を受けるリスクもあり、絶対に避けなければなりません。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
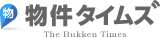



 トップへ
トップへ