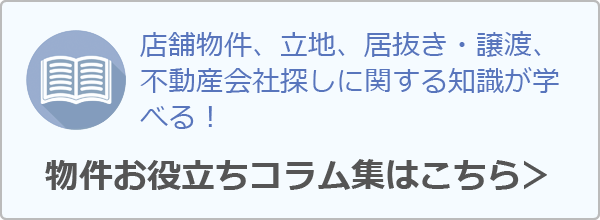【2025年最新】飲食店のデリバリーの始め方を徹底解説! 店舗がなくても売上を伸ばす新戦略
2025年10月1日

店舗の立地によって、客数の伸び悩みはあるもの。原材料費が高騰し、競争が激化する今、従来の店舗営業だけでは、安定した売上を維持することが難しくなっています。
しかし、その悩みは「デリバリー」という新しい販路を開拓することで解決できるかもしれません。この記事では、あなたの店の厨房から、新たな顧客へ料理を届けるための具体的な手順と成功の秘訣を、専門家が分かりやすく解説します。
この記事は、こんな人におすすめです
・デリバリーを始めたいが、何から手をつけていいか分からない方
・Uber Eatsなどの手数料が高いと感じ、他の方法を探している方
・店舗の立地に課題を感じ、新しい収益の柱を作りたいオーナー
・厨房のスペースに限りがあり、効率的に売上を伸ばしたい方
・将来的にはデリバリーだけでなく、通販にも挑戦してみたい方
なぜ今、多くの飲食店がデリバリーに注目するのか
デリバリーは、単に店内飲食の代わりとなる追加サービスではありません。現代の飲食店経営において、売上と可能性を飛躍的に伸ばすための重要な経営戦略となっています。コロナ禍を経て私たちのライフスタイルは大きく変化し、「中食」と呼ばれる、家庭でプロの味を楽しむ需要は一過性のブームではなく、完全に定着しました。
「本当に今から始めても儲かるのだろうか?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、市場は依然として成長を続けています。
引用元:ICT総研「2021年 フードデリバリーサービス利用動向調査」
また、2025年のデリバリー市場規模は7500億円を越えると予測されており、この追い風は、新規顧客の獲得や売上アップを目指すすべての飲食店にとって、大きなチャンスと言えるでしょう。
店舗の席数以上の売上を作るチャンス
飲食店の売上は、基本的に「客席数 × 回転率 × 客単価」で上限が決まってしまいます。しかし、デリバリーを導入すれば、この物理的な制約から解放されます。例えば、ランチタイムやディナータイムのピーク時は満席で断っていたお客様にも、デリバリーという形なら料理を届けられます。
さらに、お客様の来店が少ないアイドルタイムにも厨房を稼働させて注文を受けられるため、設備の稼働率が上がり、新たな売上を生み出します。坪月商という指標で考えた場合、デリバリーは店舗の広さに関係なく売上を積み増せる、非常に強力な武器となるのです。
「うちの店は小さいから」と諦める必要は全くありません。むしろ、小規模な店舗こそ、デリバリーを組み合わせることで売上の最大化を図れる可能性を秘めています。
商圏が広がり新しいお客様と出会える
「店の場所が駅から遠くて、新しいお客様がなかなか増えない」。そんな立地の悩みも、デリバリーが解決してくれます。Uber Eatsや出前館といったデリバリープラットフォームに出店することは、これまであなたのお店の存在を知らなかった何万人もの潜在顧客に対して、お店のメニューを見てもらう絶好の機会となります。
これは、多額の費用をかけて広告を出すことと同じ、あるいはそれ以上の認知度向上効果が期待できるのです。アプリを通じてあなたの店の料理を初めて味わい、その味に感動したお客様が、今度は実店舗に足を運んでくれるようになるかもしれません。
デリバリーは、新たなリピーターを生み出すための入り口にもなり得るのです。
あなたの店に合うのはどれ?デリバリーの3つの始め方
デリバリーを始めるといっても、その方法は一つではありません。お店の状況や目指す方向性によって最適な選択肢は異なります。大きく分けて「デリバリー代行サービス」「自社での配達」「ゴーストキッチン」の3つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
それぞれの特徴を理解し、あなたのお店に最も合った方法を見つけましょう。

方法1:すぐに始められる「デリバリー代行サービス」
最も手軽に、そしてスピーディーにデリバリーを始めたい場合に最適なのが、Uber Eatsや出前館、Woltといったデリバリー代行サービスを利用する方法です。これらのプラットフォームに登録すれば、注文の受付から決済、そしてお客様への配達まで、すべてを代行してくれます。
「でも、手数料が高いのがネック…」と感じる方も多いでしょう。確かに売上の30~40%という手数料は安くありません。しかし、この手数料には、自社で賄う場合の配達スタッフの人件費、注文システムの開発・維持費、そして何よりプラットフォームが抱える膨大な利用者への広告宣伝費が含まれています。
これらをすべて自前で用意するコストと手間を考えれば、一概に「高い」とは言えない側面もあります。まずはこの手数料を必要経費と捉え、それを上回る利益を生む戦略を立てることが重要です。
飲食店パートナー向けフードデリバリープラットフォーム比較表
| 項目 | Uber Eats | 出前館 | menu | Wolt | その他(楽天ぐるなびデリバリー等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用(通常/キャンペーン) | 通常: 50,000円 キャンペーン適用で0円の場合が多い |
通常: 20,000円 キャンペーン適用で0円の場合が多い |
通常: 50,000円 キャンペーン適用で0円の場合が多い |
0円 | サービスにより異なる。例: 5,000円 |
| 月額固定費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 月額プランが存在する場合がある |
| 手数料(配達代行) | 35% ※海外では複数プラン(15-30%)が存在し、将来日本でも導入の可能性あり |
35% (内訳: サービス利用料10% + 配達代行料25%) | 35% | 30% | 40% |
| 手数料(自社配達) | 15% | 10% | 13%(テイクアウト)自社配達オプションは目立たない。 | 利用可能。手数料は配達代行より低い | 該当なし |
| 決済手数料 | 手数料に含まれる | 別途発生: キャッシュレス決済時に最大約3% | 手数料に含まれる | 手数料に含まれる | 手数料に含まれる |
| タブレット・機材費 | 自前で用意、またはレンタル | レンタル可: 月額2,200円 または月額2,000円 | 初期費用に含まれる場合あり。キャンペーン時は自前で用意 | 自前でiPadを用意、またはリース | 該当なし |
| 主な強み・市場での位置付け | 都市部での高い集客力、世界的なブランド認知度、優れたUI | 全国を網羅する配達エリア、巨大で忠実な利用者層、高いブランド信頼性 | テイクアウト機能との両立、サブスクリプション「menu pass」によるリピーター創出 | 質の高いレストランの厳選、優れた顧客サポート、洗練されたブランドイメージ | 巨大な楽天経済圏とポイントプログラムの活用 |
| 配達エリア | 全国の主要都市 | 全国対応 | 主要都市中心に拡大中 | 都市部中心 | 全国対応 |
| テイクアウト機能 | あり(手数料12%) | なし(デリバリー特化) | あり(主要機能、手数料13%) | あり(手数料はデリバリーより低い見込み) | あり |
※費用や手数料はプランや地域によって変動します。詳細は各公式サイトでご確認ください。
方法2:利益率が高い「自社での配達」
手数料をできるだけ抑えて利益率を高めたい、そしてお客様との関係性を直接築きたいと考えるなら、自社で配達まで行う方法が有効です。注文は電話や自店のホームページで受け付け、スタッフが直接お客様のもとへ料理を届けます。最大のメリットは、代行サービスに支払う手数料がかからないため、売上の多くが利益として手元に残ることです。
ただし、配達スタッフやバイク、自転車などを自前で用意する必要があり、人件費や車両の維持費といったコストがかかります。また、注文を受けるためのWebサイトや電話応対の体制、配達中の事故に備えた保険加入など、準備すべきことが多いのが課題です。
方法3:低リスクで挑戦できる「ゴーストキッチン」
ゴーストキッチンは、客席を持たず、デリバリー専門の調理施設(キッチン)で営業する新しい飲食店の形です。クラウドキッチンとも呼ばれ、厨房設備が整ったスペースをレンタルして開業します。この方法の最大のメリットは、店舗取得費や内装工事費といった高額な初期費用を大幅に抑えられることです。
すでに営業しているお店がある場合は、既存の厨房の空きスペースやアイドルタイムを活用し、デリバリー専門の別ブランドを立ち上げる「バーチャルレストラン」という手法も可能です。厨房設備への追加投資なしで、新たな売上の柱を作れる可能性がある魅力的な方法です。

開業から売上アップまで!デリバリー成功の8ステップ
デリバリーの成功は、思いつきで始めてもうまくいきません。事前の計画と準備が成功の9割を占めると言っても過言ではないでしょう。
ここでは、明日から何をすべきかが明確になるよう、デリバリー事業を軌道に乗せるための具体的な8つのステップを解説します。
ステップ1:コンセプトとメニューを決める
まず考えるべきは、デリバリーで「何を」「誰に」「どのように」届けるかというコンセプトです。重要なのは「冷めても美味しさが損なわれないか」「配達の振動で崩れたり、汁がこぼれたりしないか」という視点です。お店の看板メニューは残しつつ、デリバリー専用のメニューを開発することも有効です。原価計算をしっかり行い、手数料や容器代を考慮した販売価格を設定しましょう。また、デリバリーはお客様が写真を見て注文を決めるため、「写真映え」も非常に重要な要素です。
ステップ2:必要な許可と資格を確認する
すでに「飲食店営業許可」を取得して営業しているお店であれば、デリバリーを始めるために追加の許可が不要なケースがほとんどです。ただし、自家製の加工品や冷凍食品を販売する場合には、別途許可が必要になることがあります。必ず事業を始める前に、管轄の保健所に事前相談し、必要な手続きがないかを確認しましょう。
ステップ3:事業計画と資金の準備
デリバリーを始めるには、どれくらいの資金が必要になるか、事前に計算しておくことが大切です。初期費用(容器代、備品代など)と運転資金(手数料、広告宣伝費、原価など)を算出し、どれくらいの売上があれば利益が出るのかという損益分岐点を把握しておきましょう。緻密な計画が、後の安定経営に繋がります。
ステップ4:補助金・助成金を活用して賢く資金調達
デリバリーの導入や販路開拓にかかる費用は、国や自治体の補助金を活用して負担を軽減できる可能性があります。闇雲に資金繰りを心配する前に、利用できる制度がないか調べてみましょう。
代表的なものに「小規模事業者持続化補助金」があります。これは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するもので、デリバリー開始に伴うチラシ作成や広告掲載、新たな容器のパッケージ開発、デリバリー注文用ウェブサイトの構築費用などが対象となる可能性があります。
どこに相談すれば良いか分からない場合は、まず地域の「商工会議所」や「商工会」が最初の窓口になります。申請のサポートも行っているため、力強い味方になってくれるはずです。公募期間が限られているため、常に最新の情報を公式サイトで確認するようにしましょう。
飲食店で利用できる補助金:助成金に関しては、下記の記事でも詳しく解説しています。
▼【2025年8月最新】飲食店の開業に使える補助金・助成金を一挙紹介!
ステップ5:容器や備品を揃える
デリバリーにおいて、容器は料理の品質を保ち、お店のブランドイメージを伝える重要なツールです。保温性や保冷性、汁漏れしない密閉性はもちろんのこと、お客様が蓋を開けたときに「美味しそう」と感じるデザイン性も考慮して選びましょう。お客様への感謝を伝える手書きのサンクスカードを一枚添えるだけでも、顧客満足度は大きく向上します。
ステップ6:デリバリーサービスへ登録・システム導入
利用する方法が決まったら、具体的な手続きに進みます。代行サービスを利用する場合は、各プラットフォームのウェブサイトから事業者登録を行います。この際、お客様が最も目にする店舗ページを作り込むことが注文数を増やす鍵となります。プロが撮影したシズル感のあるメニュー写真、料理の特徴やこだわりが伝わる説明文、正確な店舗情報などを丁寧に設定しましょう。
ステップ7:集客・販促活動を行う
デリバリーサービスに登録しただけで、自動的に注文が殺到するわけではありません。サービスを開始したら、積極的にお客様へ告知することが不可欠です。店内のPOPやポスター、InstagramなどのSNS、Googleビジネスプロフィールの整備、近隣へのチラシのポスティングなど、オンラインとオフラインの両面から地道な販促活動を続けましょう。
ステップ8:オペレーションを構築し改善する
注文を受けてから調理、梱包、配達員への受け渡しまでの一連の流れをスムーズに行えるよう、事前にオペレーションを構築しておくことが重要です。実際に運用を始めると、様々な課題が見えてきます。お客様からのレビューには真摯に耳を傾け、メニューやサービス、オペレーションを常に改善し続けるPDCAサイクルを回していくことが、長期的に愛されるデリバリーサービスを育てる秘訣です。
「デリバリーは儲からない」は嘘?よくある失敗と利益を出すためのヒント
「デリバリーを始めたけど、思ったより儲からない…」。そうした声が聞かれるのも事実です。しかし、それはデリバリー自体が儲からないのではなく、利益を出すための構造を理解せずに始めてしまったケースがほとんどです。
失敗から学び、成功へのヒントを掴みましょう。
なぜ利益が出ないのか?よくある失敗例
価格設定のミス: 店内と同じ価格で販売し、手数料や容器代で赤字になる。
メニューのミスマッチ: 伸びた麺や冷めた揚げ物など、デリバリーに向かないメニューで低評価を受ける。
オペレーションの混乱: 店内業務が忙しく、デリバリーの調理や提供が遅れ、クレームに繋がる。
リピーター施策の不足: 新規顧客の獲得だけで満足し、リピートに繋げる工夫をしていない。
これらの失敗を避けるためには、手数料などのコストを正確に把握し、それを反映した「デリバリー専用価格」を設定することが絶対条件です。その上で、デリバリーに最適化したメニュー開発、無理のないオペレーションの構築が必要です。
そして最も重要なのが、一度注文してくれたお客様に「また頼みたい」と思ってもらうための工夫です。手書きのメッセージや次回使えるクーポン、SNSでのコミュニケーションといった小さな積み重ねが、安定した利益を生み出すための鍵となります。
お店に合った方法で、多くのお客様に自店の料理を届けよう
ここまで、飲食店のデリバリーを始めるための3つの選択肢から、成功に導く8つの具体的なステップ、そして利益を生み出す秘訣まで網羅的に解説しました。手数料やオペレーション構築など、始める前は難しく感じるかもしれません。
しかし、デリバリーは店舗の物理的な制約を超え、新たなファンを獲得するための強力な武器となります。この記事を参考に、あなたのお店に合った方法で着実な一歩を踏み出し、こだわりの味を一人でも多くのお客様に届けましょう。
飲食店デリバリーに関するQ&A
Q1. デリバリーとテイクアウトはどう違うのですか?
A1. テイクアウトは、お客様が店舗に来店して商品を受け取り、持ち帰る形態を指します。一方、デリバリーは、店舗側がお客様の指定する場所(自宅やオフィスなど)まで商品を配達する形態です。テイクアウトは配達コストがかからない分、利益率が高くなる傾向にありますが、お客様が来店できる範囲に限られます。デリバリーは商圏を広げられるのが大きなメリットです。
Q2. デリバリー代行サービスの手数料を、商品の価格に上乗せしても良いのでしょうか?
A2. 多くの飲食店が、デリバリーでの販売価格を店内価格よりも高く設定しています。これは、手数料や容器代などの追加コストを吸収するためです。お客様に納得していただける価格設定が重要であり、そのためにもメニュー説明や写真で価格以上の価値を伝える工夫が求められます。競合店の価格をリサーチし、適正なバランスを見つけることが重要です。
Q3. 雨の日など、注文が殺到したときはどう対応すれば良いですか?
A3. 悪天候の日はデリバリーの需要が急増するため、事前に対策を考えておくことが大切です。代行サービスの管理画面で、一時的に新規の注文受付を停止する機能があります。調理が追いつかない場合は、早めに受付を停止して、すでに入っている注文を丁寧に対応することを優先しましょう。あらかじめピーク時を想定した人員計画を立てておくことも有効です。
Q4. お客様からクレームが入った場合はどうすれば良いですか?
A4. 「商品が冷めていた」「写真と違う」など、デリバリーでは様々なクレームが発生する可能性があります。まず、お客様の言い分を真摯に傾聴し、誠心誠意謝罪することが第一です。その上で、状況に応じて返金や商品の再配達などの対応を迅速に行いましょう。クレームの内容を記録・分析し、調理工程や梱包方法の見直しに繋げることで、サービス品質の向上と再発防止に努めることが重要です。
<飲食店.COM>店舗物件を探す
<飲食店.COM>譲渡情報を探す
- カテゴリ
- 調査・ランキングデータ
- 街・地域の立地動向
- 開業者の声
- 物件探しのコツ
- 新着記事
物件タイムズについて
飲食店ドットコムが出店希望者の方々へお届けする店舗物件マガジン。
出店エリアの立地動向、独自の調査データに基づくトレンド情報やランキング、物件探しのコツ、開業者の体験談など、店舗物件探しをテーマに、飲食店舗の物件探しに役立つ情報を定期配信しています。
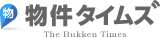



 トップへ
トップへ