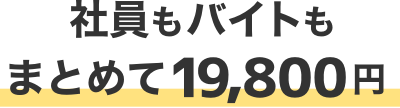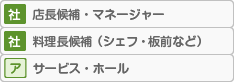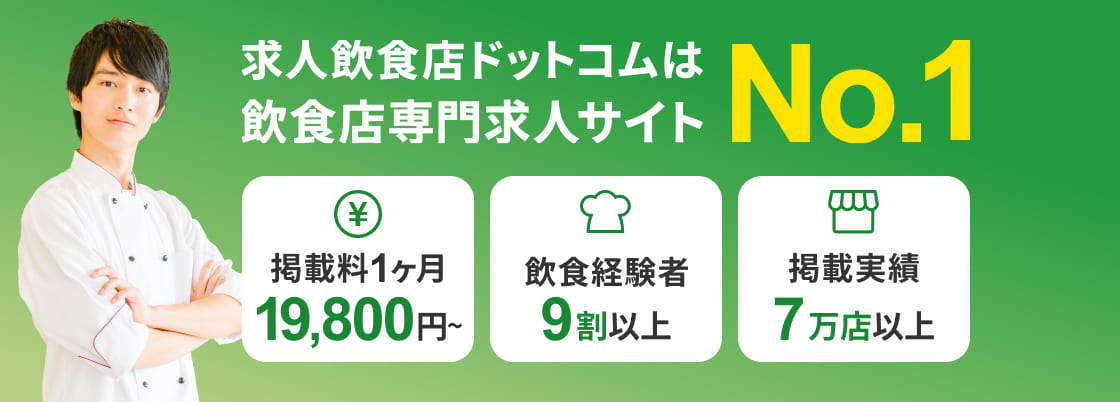この記事は、こんな方におすすめです。
- ・昇給やボーナスの意味と違いを正しく理解したい
- ・昇給やボーナスを飲食店で無理なく導入するポイントを知りたい
- ・昇給やボーナスの導入でスタッフが前向きに働ける職場を作りたい

画像素材:PIXTA
そもそも「昇給」「ボーナス」とは?意味と違いを解説
良い人材の確保・定着のためには、「昇給」や「ボーナス」は欠かせない給与制度です。 どちらもまったくない場合、自分の未来が見えないため、スタッフのやる気は下がってしまう恐れがあります。また、給与制度の見直しを前向きに考えているものの、昇給とボーナス、どちらを取り入れたら良いのかわからないという場合も多いと思います。まずはそれぞれの意味と特性を知り、目的によって使い分けることをおすすめします。
●「昇給」とは?ベースアップと評価による昇給の違い
昇給とは、基本給が上がることを言い、賃金を決める際に基準になる給与テーブルそのものが変わります。「全体ベースアップ」と「個別評価による昇給」があり、「全体ベースアップ」は全従業員が一律で昇給するのに対し、「個別評価による昇給」は、個人のスキルや役職の昇格時など、経験値や成果をもとに個別に行います。全体ベースアップは、勤続年数や役職にかかわらず全従業員が対象になるため、繁盛している時に一気に上げたとしても、業績が低下した場合に人件費が経営を圧迫する恐れがあります。そのため、社会情勢や流行によって売上が変化しやすい飲食店においては、個別評価による昇給を採用するほうが現実的な選択と言えます。
●「ボーナス」とは?賞与・インセンティブ・歩合給の違い
必ず支払う固定給とは別に特別に支給する報酬は、一般的にはボーナスと呼ばれます。厳密には、主に会社全体の業績に応じて出す「ボーナス」「賞与」と、個人の成果報酬である「インセンティブ」「歩合給」に分けられます。「ボーナス」は一時金の支給のことで、基本給とは別のものです。「賞与」は「ボーナス」とほぼ同義で使われますが、業績に応じた額を年1~2回支給するなど、企業の規定に則り支払いを行います。
「インセンティブ」は個人の成果に応じて一定の割合額を都度支給すること。「歩合給」は、売上の◯%など数字連動型であることが特徴で、目標を達成した場合に支給します。 飲食店が導入しやすいのは、個人が出した成果に応じて支給する歩合給やインセンティブでしょう。
●昇給とボーナスの違い・位置付けを正しく理解しよう
昇給により給与は増額するので、人材確保や定着を推進するには効果的な制度です。注意したいのは、固定給が上がれば、毎月の人件費が増える点です。そして一度上げたら下げることは難しいので、将来的に負担が大きくなってしまうこともあり得ます。そのため、慎重な設計が必要です。一方、ボーナスなどの一時金支給であれば、「今期は売上が良かったから、前期より多めに支給する」など、店の状況に合わせて都度判断することができ、柔軟な運用が可能です。固定給のように必ず出さなくてはいけないというものではないので、出さない、下げるという判断もできます。ただし、その場合、スタッフのモチベーションに影響することも考えられます。
昇給とボーナス、それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが大切です。
飲食店で昇給・ボーナス制度を導入するメリット
飲食店において昇給・ボーナス制度を導入するメリットは、主に・スタッフのモチベーションが向上し定着率アップや離職防止につながる
・昇給・ボーナス制度や明確な評価制度の提示により優秀な人材を採用・確保できる
・数値目標に向けた努力によりスタッフが自律的に働けるようになったり、店の生産性や売上にプラスに働いたりする
などがあります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
●スタッフのモチベーション向上と定着率アップ
昇給とボーナスは、どちらもスタッフのモチベーションを上げる効果があります。その1番の理由として、受け取れる金銭が増えるということが挙げられるでしょう。もちろんそれだけではなく、日頃の頑張りが報酬に反映されることで「評価されている実感」を得られますし、「もっと頑張ってステップアップしよう」とキャリアアップ意欲を刺激するきっかけにもなり、精神面でスタッフの支えになります。その結果、定着率がアップするというメリットにつながるのです。
また定期的なインセンティブの支給も離職率の低下にも効果的。優秀な人材の流出を防ぎます。
●優秀な人材の採用・確保につながる
転職サイトやエージェントなどの求人媒体では、待遇面に「昇給・ボーナスあり」と記載があるものは応募率が上がる傾向にあるため、この点を強みとしてアピールするケースが増えています。飲食業界は他業種に比べて給与水準が低めであることがネックになりがちですが、昇給やボーナスがあれば他店舗との差別化要素になり、「ここで働きたい」と思えるような店になれるでしょう。
さらに、面接時に、個人の貢献を給与面でしっかりと反映すると求職者に伝えることで、「評価の見える化」を行うための制度があることを知ってもらい、経営側の思いや誠実さをアピールすることができます。求職者の信頼を得ることができれば、優秀な人材の採用・確保にもつながっていきます。
●店舗全体の生産性・売上アップにも寄与
努力や成果を評価する売上インセンティブ制度などがあれば、店舗全体に数値目標に向けた一体感が生まれます。 例えば、月間目標を達成したスタッフに支給すると決めておけば、一人ひとりがそこへ向かって努力し、能動的に動きます。切磋琢磨しながら目標達成のために生産性を上げるので、スタッフが自ずと成長していくのです。 スタッフが成長すれば、売上も顧客満足度も上がる好循環が生まれますし、自律的に動くスタッフが増えるため、店長の負担軽減にも寄与するでしょう。
画像素材:PIXTA
飲食店でも実践しやすい昇給・ボーナスの具体例
「全員一律で行う昇給・ボーナス捻出は負担が大きすぎて無理」という場合でも、店舗の業績や個人の貢献度に応じた形の制度であれば取り入れやすいでしょう。どのようなものがあるのか、いくつか具体的な例をご紹介しますので、参考になさってください。●売上や利益に連動させた「歩合型ボーナス」
歩合型ボーナスは、店舗の売上や利益などの成果に対して、一定の割合で支給されるものです。金額は売上・利益の◯%という連動型なので、売上・利益が良かった分だけ割合も上がり、売上・利益が下がったらその分割合も下がります。業績に応じて支給額が変動するので、店舗が好調な時に多く出してスタッフのモチベーションを上げることができ、業績が下がったらその分だけ削減することができるため、店舗の状況に合わせて柔軟に対応することが可能です。
●スキルや資格取得を評価する「スキル昇給」
スキル昇給は、ホールであればコミュニケーションなどの接客スキル、調理担当であれば調理技術というように、個人のスキルに応じて昇給する制度です。ただし、後の章でも解説しますが、導入するには評価基準が明確化されている必要があります。
この場合、「接客サービスマナー検定」や「食品衛生責任者」など、業務に関連する特定の資格を取得したスタッフに手当を支給する、いわゆる「資格手当」という形であれば、よりスタッフからの納得感も得られます。
スキルアップや資格取得のための努力を昇給という形で認めることで、スタッフの育成・能力開発を促進できます。
●店舗貢献度を見える化する「評価制度型ボーナス」
評価制度型ボーナスは、個人がどの程度店舗に貢献しているかを可視化することにより、貢献度に応じて手当を支給するというものです。例えばテーブル担当制を導入するなどして、スタッフごとの売上を集計し、成果を上げた担当者に支給する方法などが考えられます。
顧客やスタッフ内でのアンケートを実施するなどして、評価の高いスタッフに特別手当を付けるというのも良いでしょう。
●継続勤務年数に応じた「勤続ボーナス・昇給」
勤続ボーナス・昇給は、何年継続勤務したかに応じて賃金を上げたり、別途ボーナスとして支給したりするものです。この制度を導入することで、長年勤務してくれているスタッフを労うことができます。適切に評価していることを示すことで、本人の帰属意識を高め、離職を防止するためにも効果的です。離職率が高く、人手不足に陥りがちな飲食店にとってはおすすめの制度といえます。
昇給・ボーナス制度を上手に運用するためのポイント
昇給・ボーナス制度の運用を成功させるために大切なのは、透明性・客観性のある評価基準を明確にすること、少額でも良いので頻度やタイミングを重視すること、インセンティブなどの組み合わせを検討することなどが挙げられます。●「公平感」「透明性」のある評価基準をつくる
評価基準は公平性や透明性を感じられるものにします。そのため、・「なぜ昇給・ボーナスがもらえたか」について基準を明確化し、スタッフから説明を求められたら合理的な理由を伝えられるようにする
・スタッフと定期的に面談を行い、十分な説明を果たして納得感を醸成する
・評価者の主観に頼りすぎない、客観性を備えたルールづくりを徹底する
これらを行い、スタッフの納得を得られるような評価システムをつくることが重要です。
●金額にこだわらず、頻度やタイミングでモチベート
昇給やボーナスというと、決まった時期にまとまった額を支給するものと思いがちですが、小額であっても、こまめな評価や即時フィードバックを行い、ここぞというタイミングで支給することがモチベーションアップに効果的です。例えば繁忙期終了後に、頑張って乗り切ったスタッフへの「労いボーナス」を支給するのも有効です。
モチベーション維持のためには、一度だけ多めに支給して終わるよりも、小出しにするなどの頻度を重視すると良いでしょう。
●昇給・ボーナス以外のインセンティブとの組み合わせ
昇給・ボーナス以外には、インセンティブを組み合わせることは、よりスタッフのモチベーションを上げる効果があります。例として、
・優秀な成果を上げたスタッフを表彰する「社内表彰制度」
・スタッフ同士が評価し合い、感謝や称賛の気持ちを報酬として贈る「ピアボーナス」
・店長がスタッフへ送り、感謝を伝える「ありがとうカード」
など、心の報酬である「承認・評価」も意識することで、士気を上げる効果が倍増します。
飲食店でよくある昇給・ボーナス制度導入の失敗例と対策
飲食店における昇給・ボーナス制度の導入の際には、注意しなくてはいけないポイントがいくつかあります。評価基準が不透明で曖昧なためスタッフの不信感を招いてしまう、昇給・ボーナス制度導入に期待したものの制度が形骸化する、いつのまにか人件費が利益を圧迫してしまうなど、失敗してしまうケースもあります。
●「基準が曖昧」で不満が噴出するケース
ベースアップ型であれば全員一律に賃金を引き上げるので問題はありませんが、個別の評価昇給型の場合、評価の方法に注意が必要です。例えば、店長の気分や主観で決めてしまうと、スタッフの不信感を招き逆効果になります。具体的な行動指標を設け、数値化できる部分は数値化するなどして、基準を明確化しましょう。
さらに、定期的なフィードバック面談を通じスタッフと意見交換をする中で、改善点が見つかれば早急に改善を行うようにします。
●「制度が形骸化」して効果が薄れるケース
いくら離職率を下げようと「昇給・ボーナスあり」を掲げても、初回だけ支給してその後予算が続かずに制度が形骸化してしまっているのでは、スタッフのモチベーションが下がる一方です。そうならないためには、一度に大幅昇給などをするのではなく、運用し続けられる「無理のない設計」をすることが重要です。小額でも定期的に支給を行うか、 成果に応じた柔軟な運用を行ったほうが効果的です。
●利益を圧迫しないための事前シミュレーションと工夫
人件費が膨らみすぎると、いくら売上が良くても利益を圧迫してしまいます。昇給やボーナス制度を導入する際は、売上・利益を良くシミュレーションした上で制度設計を行います。スタッフの人数に応じて「固定額支給」と「成果連動型」を使い分けるのも、予期せぬ人件費超過を防ぐコツです。まずは試験的に導入し、様子を見てから本格導入へと踏み切るのが良いでしょう。
まとめ:「昇給」「ボーナス」をうまく取り入れて、定着率の高い職場づくりを
昇給制度やボーナス制度は、法律上の義務ではないので、必ず取り入れなくてはいけないというわけではありません。ただ、どちらの制度も、求人採用の際のアピールになったり、スタッフのモチベーションや帰属意識を高め、「ずっとここで働きたい」と思ってもらえたりする大事な要素になります。
定着率を上げてスタッフのスキルを高めれば、店舗全体の生産性や売上も向上します。ぜひ、自社に合った制度をうまく取り入れてみてください。
飲食業界専門の求人サイト『 求人飲食店ドットコム 』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせ ください。
【関連記事】
■ 給与体系を見直して、優秀な人材を獲得!注意点や設計のコツは?■ 飲食店の人材採用は、給与面で差をつけよう。賃金引上げを支援する助成金を紹介
#飲食店ドットコム #求人飲食店ドットコム
#飲食店 #求人 #採用 #正社員 #アルバイト #パート
#採用お役立ちコンテンツ