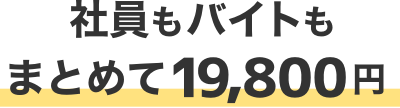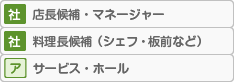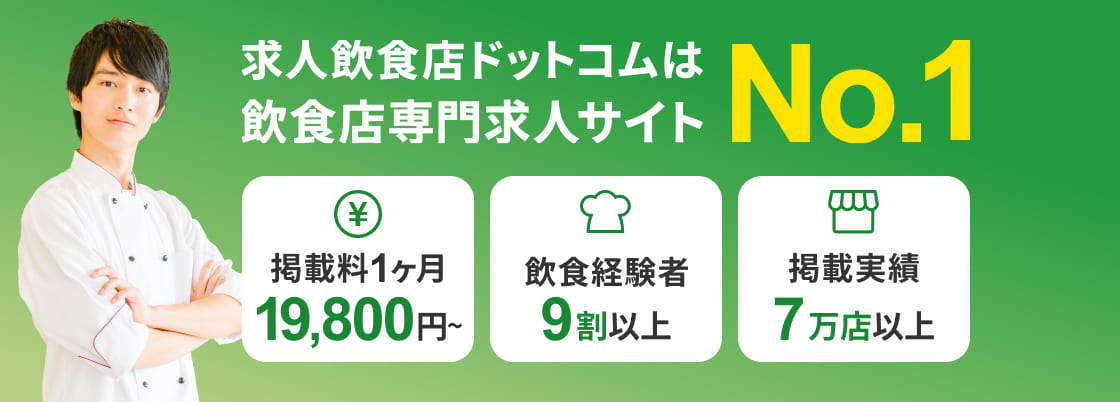画像素材:PIXTA
飲食店の「適切な人員数、配置」を算出する方法を知ろう
店舗の「人員配置」を考える際、忙しさでサービスが充分に行き届かなくなるといったリスクを避けるために「できるだけ多めに人を配置しておきたい」と考える人もいるかもしれません。しかし、本来、人員配置とは、店舗の利益率を高めるために「必要最低限の人員を投入する」ことです。では、1店舗当たりに必要なスタッフ数とは、どのように決めるのが良いのでしょうか。
◆客席数から必要なスタッフ数を考える
よく知られているのは、客席数をもとにその店舗に必要なスタッフの数を算出する方法です。適正なスタッフ数は「座席数÷10」で計算します。
例えば席数(収容人数)が30人の店舗であれば、スタッフ数は3人程度がひとつの目安になるということです。ただし、テーブル数や客席稼働率、調理の手間などを考慮する必要があります。計算でスタッフ数の目安を知り、大きくかけ離れている場合は、ひとり一人のスタッフがどんな役割を担っているか、業務量はどうかといったことを見直してみると自分の店舗の適正人数に近づけることができるはずです。
◆合わせて意識しておきたい「人時売上高(にんじうりあげだか)」
とはいえ“計算上”人員数が適正でも、その結果、しっかりと利益が出なければ、飲食店の経営としては成り立ちません。そこで、気にかけたいのが「一人のスタッフが一時間当たり、いくらの利益を出したか」を算出できる人時売上高です。
「人時売上高=店舗の月商÷スタッフの総労働時間」
人時売上高の理想額は5,000円程度といわれていますが、平均値である3,000~4,000円が目安になります。
売上アップを狙い、5,000円を超える人時売上高を追求する経営もありますが、それは「少ない人数で売上を上げている」ということなので、スタッフに大きな負荷をかけている、もしくはお客様の満足度低下につながっている可能性があるため注意が必要です。
◆人件費率は30%以内に抑えるのが理想
同時に、売り上げに対してかかる人件費の割合も確認しておきましょう。人件費率を算出する計算式は以下の通りです。
「人件費率=人件費÷売上高×100」
飲食店の場合、この人件費率を30%以内に抑えることが目安といわれています。必要なアルバイトの人数を割り出す時も、売上予算に対して人件費率が30%に収まるように人員を調節するのが良いとされています。
正社員とアルバイトの「適切な」配置とは?
人件費の無駄を省きつつ、満足度の高いサービスを提供する「最適な人員配置」を考えるうえで欠かせないのが、ランチやディナーなどピーク時以外の時間帯の人件費をいかに抑えるかということです。お客様の来店数には必ず波や特徴があります。まずは自分の店舗のピーク時、そして閑散期がいつなのかをはっきりと把握しましょう。そして、その時間、曜日に合わせて人員配置を考えていくのが基本です。
正社員は稼働していない時間でも給与が発生します。そのため、飲食店において正社員の雇用はシフトや店舗運営の管理に携わるといった最低限必要な人数に絞るのがオススメ。そして「忙しい時間や曜日だけ」といった短時間の労働力はアルバイトやパートを活用すると効率的です。
短時間でも働けるようなシフトを用意すると、スキマ時間に働きたいといったニーズが高い学生や主婦の方も応募しやすく、人材が確保しやすくなります。また運営面でも、短時間勤務のスタッフは健康保険や厚生年金への加入が不要であるため、正社員や長時間勤務のスタッフを多く採用するよりも社会保険加入費用などの負担を抑えることができるといったメリットもあります。
「満足度の高いサービス」の提供を追求するあまり、常に多くの人員を配置すると、人件費がかさんで利益を圧迫する可能性もあります。人時売上高や人件費率などを常に気にかけ、上手に社員とアルバイトのシフトを組み立てていくようにしましょう。
【関連記事】
■ 飲食店の役職にはどんなものがある? 適切な人員配置で営業効率アップを目指そう■ 飲食店の人件費はどう考える? 給料・ボーナスを決める基準や算出方法をチェック