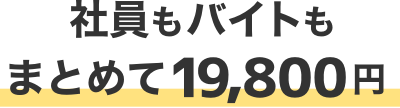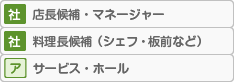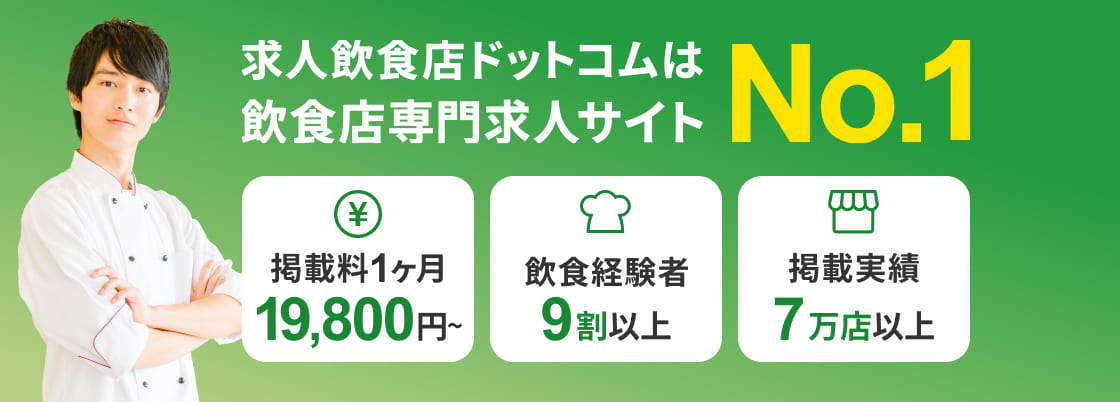画像素材:PIXTA
「職業安定法施行規則」の改正でどうなる?
労働契約締結時には、労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示する必要があります。職業安定法施行規則が改正されると、事業主・人事労務担当者が労働者に対して明示する労働条件に、新たな明示事項が追加されます。事業主・人事労務担当者は労働条件通知書の内容を変更する必要があるため、改正点についてきちんと理解し、備えておきましょう。さっそく、追加される新たな明示事項について説明します。
■すべての労働者に対して:就業場所・業務の変更の範囲
現行法では、すべての労働契約に対し、労働条件通知書や雇用契約書を通して「雇い入れ直後の就業場所」と「業務の内容」を明示することが義務づけられています。
改正後はこれらの事項に加え、将来の配置転換などを想定した「変わり得る就業場所や業務内容」も明示する必要があります。 明示するタイミングは、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時です。
■有期契約労働者に対して
1.更新上限の有無と内容
有期労働契約の締結時と更新時には、通算契約期間、または更新回数の上限を明示する必要があります。なお、更新上限を新設・短縮しようとする場合は、その理由をあらかじめ説明しなければなりません。2.無期転換申込機会
無期転換ルールとは、同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、契約社員、アルバイトなどの有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのこと。企業は、有期契約労働者から無期転換を希望された場合にその申し出を断ることができず、無期労働契約に変換することが定められています。改正後は、無期労働契約への申込機会があることを明示しなければなりません。
就業場所・業務の変更の範囲はどう記載する?
飲食店の事業主・人事労務担当者が特に抑えておくべきポイントは、すべての労働者に対して行う「就業場所・業務の変更の範囲」の明示でしょう。店舗展開をしている場合、就業場所の変更はあり得ますし、店舗から離れて本社で運営業務を担当する、通販部門やセントラルキッチンで働くといったケースも考えられます。4月からは次のように明示をします。
例
【業務内容】 (雇入れ直後) ホール業務 (変更の範囲) 運営業務
【就業場所】 (雇入れ直後) ○○店 (変更の範囲) △△本社
「変更の範囲」を明示するのが難しい場合、以下の記載例が参考になります。
「就業の場所」変更範囲例
会社の定める店舗/本店及びすべての直営店舗
「業務」変更範囲例
会社の定める業務/会社内での全ての業務/全ての業務への配置転換あり
このように、範囲を広く明示することが認められています。従業員が不満を持ったり、トラブルに発展したりしないようにするために、可能な限り情報を出して労使間のコミュニケーションを深め、認識にズレがないようにしておくことが大切です。
求人募集時の変更点も要チェック!
ハローワーク等への求人の申込みや求人広告の掲載を行う場合も、求人票や募集要項において「就業場所・業務の変更の範囲」「無期転換申込機会」などを明示する必要があります。これらは基本的には求人広告を載せるハローワークや求人企業側が行うことですが、飲食店側が求人原稿を作成するときにも注意しておきたいポイントです。また、自社ホームページでの募集の際にも労働条件の明示が必要となるため、しっかりと覚えておきましょう。
ただし、求人広告のスペースが足りないといったやむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと書き添えたうえで、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則として面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
なお、選考の過程で当初明示した労働条件を変更することもあるでしょう。その場合は、変更内容を速やかに明示してください。
事業主・人事労務担当者は、労働条件通知書の内容変更、求人原稿や自社ホームページでの募集要項の変更などの対応を迫られます。4月の改正までに準備を進めておきましょう。
制度改正等について不明点が出てきた場合は、 厚生労働省のウェブサイトや 無期転換ポータルサイト、 多様な働き方の実現応援サイトが参考になります。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
【関連記事】
■ 作成するメリットがたくさん! 飲食店経営者必見、「就業規則」の作り方とは?■ 飲食店に最適な「人的資本経営」!従業員の強みを活かした組織づくりの極意