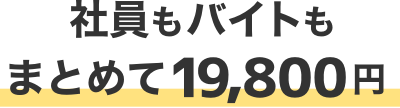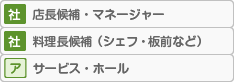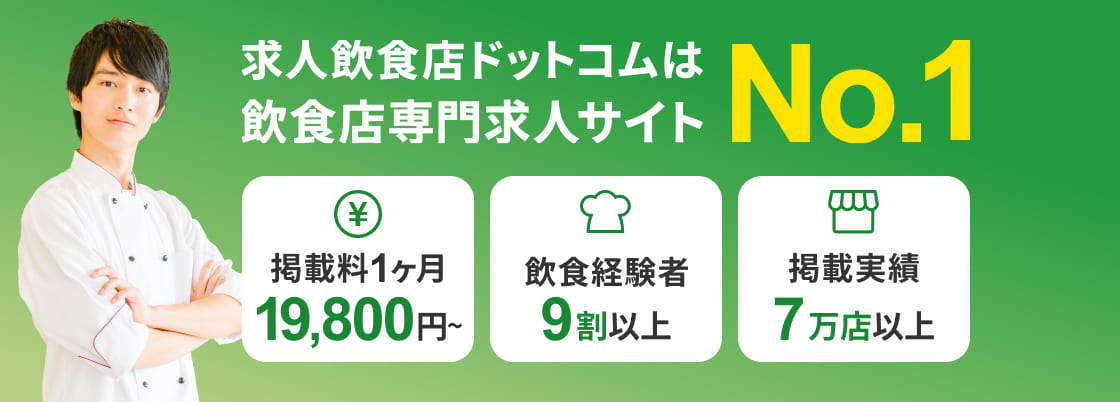画像素材:PIXTA
「就職先を安易に決めた」と感じている学生は4割超
2025年卒学生のうち、「民間企業に就職する」割合は84.9%で、「民間企業以外(公務員、教員、その他団体職員など)」も含めると就職確定率は91.7%となり、2012年の調査開始以来、最も高い数字になりました。人手不足を背景に、学生に優位な売り手市場が続いています。就職活動の各プロセスの実施状況を見ると、プレエントリー、エントリーシートの提出など応募に関する活動量が減少しており、応募社数が少なくなっていることがわかります。また、「Web開催」の説明会やセミナーへ参加したりと、面接選考を受けたりすることは減り、「対面」での活動(リクルーターとの接触、説明会・セミナーへの参加、面接選考)が増加しました。労力の費やし方を考え、効率的な就職活動をする傾向が強まっているようです。
インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに参加した学生は73.6%で、参加期間で多かったのは「1日(57.9%)」と「半日(39.4%)」でした。「キャリア形成支援プログラム参加企業へ入社予定」の学生は41.2%、「同業種の企業への入社予定」も含めると75.8%に達し、特定の企業・業界をよく知りたいという目的を持ち、参加していることが伺えます。
ただし、期間が「5日以上~2週間未満」は18.4%、「2週間以上~2ヵ月未満」は5.3%、「2ヵ月以上」となると2.9%まで参加は減ることから、気軽に参加できる日程のプログラムが好まれていることがわかります。
就職先の決定を振り返り、「安易に決めてしまったと感じるか」の質問には、10.8%が「当てはまる」、32.8%が「どちらかというと当てはまる」と回答。さらに、「就職先を決めるにあたって自分が重視する基準がわからなかった」と答えた学生は65.8%いました。仕事選びの軸を持てないまま就職活動をしていた学生は少なくないことが数字に表れています。
企業には学生との丁寧なコミュニケーションが求められる
企業へ新卒採用の採用数計画に対する充足状況を尋ねたところ、「計画よりかなり多い」「計画より若干多い」「計画通り」を合わせると37.2%で、4割近くの企業は手応えを得られたようです。「前年から負担が増加した採用業務」については、「内定者とのコミュニケーション」「応募者とのコミュニケーション」「面談・面接に関する業務」「書類選考に関する業務」の4項目で、未充足企業より採用充足企業の方が割合が高くなりました。また、「初任配属に関する取り組み」でも、「なぜそのポジションに配置されたかを説明している」「組織・事業の観点から、なぜそのポジションに配置されたかを説明している」「本人のキャリアや成長の観点から、なぜそのポジションに配置されたかを説明している」の3点すべてで充足企業が未充足企業より実施割合が高いことがわかりました。学生一人ひとりとコミュニケーションをとる、キャリアを大切に考える姿勢を見せることが企業にとって重要になっていると言えそうです。
2026年も柔軟な採用活動が不可欠
採用計画を尋ねたところ、35.1%の企業が通年採用を実施予定と回答しました。採用方法としては、「スカウト・オファー型」「リファラル採用」「採用直結と明示したインターンシップ等からの採用」の伸びが目立ちました。さまざまな方法で人材確保を目指す企業が多くなりそうです。注視していきたいのは生成AIの活用です。就職活動において生成AIを使用した学生の割合は、昨年から+20.0ポイントで34.5%に急増。「生成AIから得た回答をそのままエントリーシート等に使用した」について「当てはまる・計」は+8.6ポイントで39.7%、「生成AIを使用して、エントリーシート等の内容を本来の自分以上に良く見せても良いと思う」に「当てはまる・計」は+7.6ポイントで59.2%になりました。これは入社後のミスマッチを引き起こす可能性をはらんでいるため、応募者と関わり方を見直したり、工夫したりすることも必要になっていきそうです。
【関連記事】
■ 人材育成の悩みは「教えても覚えない」!? 効果的な育成のポイント■ 新人への声掛け・指導はどうすればいい? 信頼関係を築くために押さえたいポイント
#飲食店ドットコム #求人飲食店ドットコム
#飲食店 #求人 #採用 #正社員 #アルバイト #パート
#採用お役立ちコンテンツ