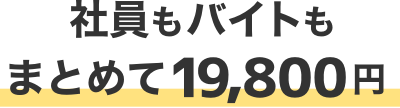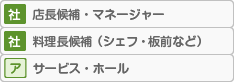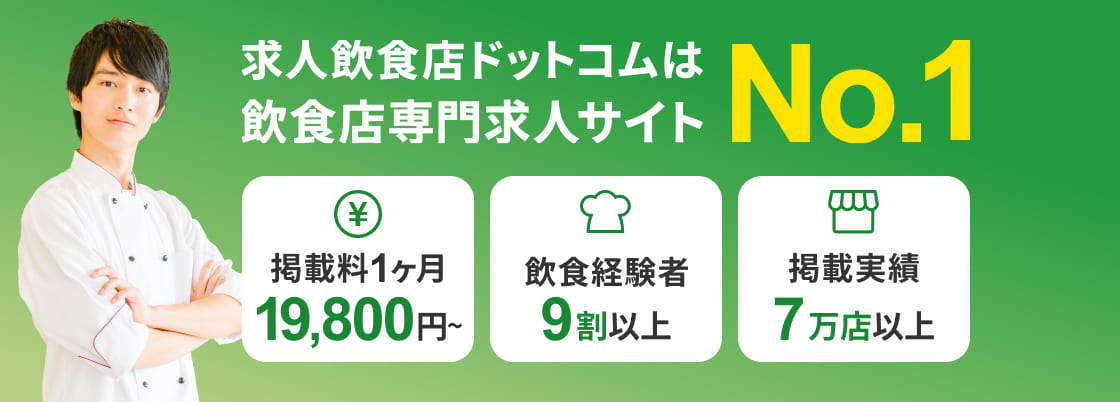画像素材:PIXTA
「冬の感染症」への徹底対策を!
毎年、冬期(11月~翌3月)になると、ウイルスによる感染症胃腸炎が発生し、時に大きな流行となることがあります。胃腸炎を引き起こすウイルスには「ノロウイルス」や「ロタウイルス」「アデノウイルス」などがあり、その中でも「ノロウイルス」は非常に感染力が強いことで知られています。また、乾燥や熱に強く、自然環境下でも長期間生存することができるため、集団感染の事例は数多く報告されています。ノロウイルスに感染する経路としては
1. ウイルスが蓄積した牡蠣などの二枚貝を加熱不十分な状態で食べる
2. ウイルスに感染した人が調理もしくは配膳することで汚染された食事を食べる
3. 患者の便や嘔吐物からの二次感染
という3つが挙げられます。「この店から感染が広がった」「スタッフ間で感染が広がって営業ができない」とならないよう、調理法はもちろんスタッフの体調管理にも気を配るようにしたいものです。
衛生管理体制をもう一度見直そう!
とはいえ、単に「体調管理に気を付けるように」と口頭で呼びかけるだけでは、健康・衛生管理を徹底することは難しいもの。そこで、ぜひ導入を考えたい3つの施策をご紹介します。1.体調管理シートの作成
勤務前に必ず各個人に体調に関するチェックシートの記入をしてもらいます。下痢や嘔吐、発熱の有無、爪が伸びていないか、食材を扱う手や指に傷やケガがないか……など、食中毒や感染症につながる恐れのあるポイントをチェックシートに入れてください。出勤のたびにチェックすることで、従業員側も自分の体調と真剣に向き合うようになり、体調の変化に気づきやすくなるはずです。
2.出勤停止などの規則を整備する
コロナやインフルエンザなど、感染症法や労働安全衛生規則などによって「罹患した場合は出勤停止」の扱いにするよう定められた感染症もありますが、ノロウイルスは対象外。しかし、飲食店においては大規模な食中毒を引き起こす可能性もあるので、出勤停止の処置をとるなどの規則を整備すべきです。その際は有給休暇を利用することを可能とする、または、休業手当を申請できるよう就業規則に盛り込むのもよいでしょう。
3.「経費」扱いにして予防接種を促す
インフルエンザなどの予防接種は「個人で受けるもの」というイメージが強いですが、その予防接種が業務上必要なものであり、全ての従業員を対象とした常識の範囲内の金額のものであれば、その費用を「福利厚生費」として経理処理することができます。インフルエンザもノロウイルスも感染から完治までに1週間近くかかるもの。長期間の欠員を出さないためにも、経費扱いとして予防接種を促すというのも有効な感染対策といえます。
知っておきたい「安全配慮義務」
健康は個人で管理するものだと思いがちですが、企業には、従業員が快適な環境で働け、安全と健康を確保できるように取り組む「安全配慮義務」があります。健康診断の実施や労働時間管理、メンタルヘルスケア対策などがよく話題になりますが、土台となるのは日常での体調管理への取り組みであることを忘れないでください。また、従業員を感染症から守るための対策はもちろん、万が一、感染症にかかってしまっても従業員が安心して休めるよう、就業規則の整備や代わりのスタッフを迅速に補填するためのシステム作りも非常に大切です。従業員が「安心して働きやすい」と感じられる環境づくりを心がけましょう。
従業員の安全と健康の守るは企業の責務です。真剣に取り組んでいくことで企業の強みになり、人材の確保と定着につながっていくでしょう。冬の従業員の健康管理をきっかけに、日々の取り組みを強化してください。
飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM 』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。
【関連記事】
■ コロナ禍でスタッフのストレスが増加。飲食店で取り組みたい、メンタルヘルスケアとは?■ 飲食店経営の肝はスタッフとの信頼関係にアリ! 信頼関係を築くメリットとコツは?