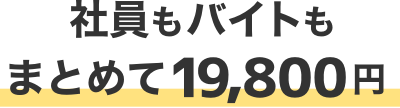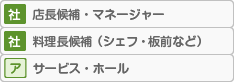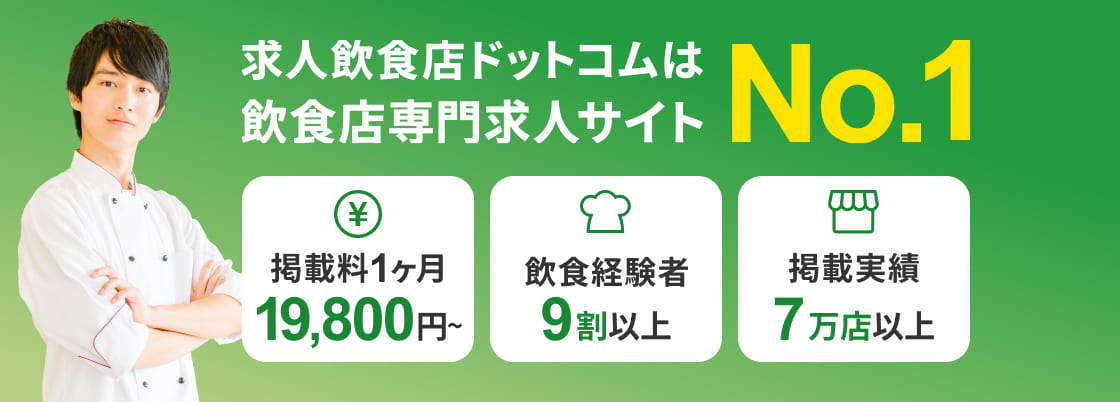画像素材:PIXTA
国がカスハラ対策を義務化
「カスハラ(カスタマーハラスメントの略称)」とは、客(カスタマー)が従業員に対して、暴言を吐いたり、過度な要求を突きつけたりすることです。本来、客からの苦情は、サービスや接客を改善するためのヒントになり得るものですが、単なる文句や言いがかりであったり、暴力的な行為が伴ったりする場合には従業員に過度なストレスを与えてしまいます。増加するカスハラに対して企業が対策に取り組むようにと、政府は法改正に動き出しました。従業員からのカスハラ被害相談に適切に対応するための体制整備などを求めていくようです。こうした流れを受けて東京都では「東京都カスタマーハラスメント防止条例」を2025年4月1日に施行。罰則規定はないものの、カスハラ禁止が明示されています。
業種別カスハラ被害、飲食店は3位
マイナビが「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査(2025年1月)」を実施し、結果を発表しました。「企業のアルバイト採用担当者に、直近1年以内に自社のアルバイト従業員が、顧客からハラスメント疑惑のある被害を受けたか」を尋ねると、45.7%が「何らかの被害があった」と回答。被害が多い業種の上位は「販売・接客(パチンコ・カラオケ等)77.7%」「販売・接客(コンビニ・スーパー)70.3%」で、「ホールキッチン・調理補助(飲食・フード)」は55.7%で3番目に多いことがわかりました。
また、アルバイト従業員の1カ月以内の早期離職の有無と、カスタマーハラスメント被害の関連を調査すると、カスハラがあった企業の34.2%が「早期離職があった」と回答し、被害がなかった企業と比べると11.5ポイントも高い結果が出ました。カスハラがアルバイトの定着を妨げている現状が見えてきました。
飲食店も積極的にカスハラ対策を
従業員に「働き続けたい職場だ」と思われるためには、カスハラ対策の整備が非常に重要です。飲食店ではどんな取り組みができるでしょうか?■クレームの初期対応方法を明示する
苦情やクレームの段階でうまく対応できれば、カスハラに発展させずに済む可能性があります。初期対応をどうすればよいのかを従業員に周知しておきましょう。例えば次の点が大事です。- ・客の言葉は遮らずに最後まで聞く。
- ・話の中から何に対して苦情やクレームが出ているのか「原因」を理解し、謝罪する場合は対象部分のみにする。
客の言い分をオウム返しし、謝罪の言葉を組み合わせると、客は「わかってもらえた」という印象を得やすくなります。また、原因が把握できていない段階では、謝罪の言葉は使うべきではありません。
■クレームかカスハラかの基準を設定する
客からの理不尽な要求は、受け入れてはいけません。従業員にクレームとカスハラの違いを示しておくと、正しい対応が取りやすくなります。- ・従業員に差別的な発言をしたり、身元証明を出すように求めたりしてくる
- ・従業員に差別的な発言をしたり、身元証明を出すように求めたりしてくる
- ・「ネットでさらずぞ」などと脅してくる
上記のような場合には「カスハラ」と言えます。謝罪の言葉を使うと、店側が非を認めたと客がヒートアップするかもしれません。「お時間を頂いておりすみません」「ご気分を害されたのであれば、申し訳ございません」といった言葉で対応します。
■カスハラ対応マニュアルを作成する
カスハラが発生した場合でも、「まずは〇〇さん(〇〇部署)に報告をする」「自店には弁護士に相談できる環境がある」といったことが事前にわかっていると、従業員は自信を持って対応できます。対応マニュアルを作成し、社内研修で活用しましょう。厚労省が作成した資料 「飲食分野におけるカスタマーハラスメント対策の取組について」も参考になります。
■監視カメラの設置や録音機器の準備も検討する
万が一に備えて、店内にカメラを設置したり、話し合い時に使うために録音機器を店舗に置いたりしておくと、従業員は安心感を得やすくなります。精神的・身体的な安全を確保できなければ、従業員が離職するのは当然のこと。カスハラ対策を整備し、採用記事や面接時にアピールしていきましょう。
【関連記事】
■ スタッフの離職を防ごう!心と体の健康を保つ“職場づくり”の秘訣■ 労務のプロに聞く! 「アルバイトスタッフが離職しない店づくり」とは
#飲食店ドットコム #求人飲食店ドットコム
#飲食店 #求人 #採用 #正社員 #アルバイト #パート
#採用お役立ちコンテンツ