飲食店のインバウンド対応状況を調査。77%が、ベジタリアン向けメニューなどの「対応予定なし」
2023年10月25日
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
<本調査について>
■調査概要
調査対象:飲食店ドットコム会員(飲食店経営者・運営者)回答数:370名
調査期間:2023年9月13日~2023年9月28日
調査方法:インターネット調査
■回答者について
本調査にご協力いただいた回答者のうち68.9%が1店舗のみを運営。また、回答者のうち東京にある飲食店の割合は54.3%(首都圏の飲食店の割合は69%)となっており、こうした背景が結果に影響していると推測される。<調査結果について>
インバウンド顧客の来店経路、上位は「Instagram」や「トリップアドバイザー」
最初に、新型コロナウイルスが5類に移行した2023年5月8日以降における、インバウンド顧客の来店状況について質問したところ、「来店した」が58.9%、「来店していないor分からない」が41.1%となった。

次に、インバウンド顧客が来店した店舗に、コロナ前のインバウンド顧客の来店頻度を尋ねたところ、「週に1回以上」と回答した店舗が54.6%(ほぼ毎日=15.6%、週に2-3回程度=21.6%、週1回程度=17.4%)に及んだ。5類移行後にインバウンド顧客が来店した店舗の半数以上は、コロナ禍以前からインバウンド顧客が定期的に来店する店舗だったことがわかる。

続いて、インバウンド顧客が来店した店舗に、海外からのお客様はどのメディアをきっかけに店のことを知り、来店しているか答えてもらった。すると、最も多かったのは「何のメディアを見ているかわからない(53.7%)」との回答で、詳細な来店経路を把握していない店舗が目立った。そうした中、来店時に参考にしたメディアの上位として挙がったのは、「Instagram(14.7%)」や「トリップアドバイザー(9.2%)」だった。また、「その他(18.8%)」の意見として「Google」と回答する店舗も複数見られた。

外国人観光客との「言語の壁」が、多くの飲食店で悩みの種に
インバウンド顧客が来店した店舗に、海外からのお客様が最も注文するメニューについて尋ねると、多くの店舗で“日本らしさ”を感じるメニューが注文されやすいことがわかった。なかでも「日本酒」や「ジャパニーズウィスキー」といった日本ならではのお酒や、「ラーメン」、「刺身」、「唐揚げ」、「和牛を使った料理」などが人気のようだ。
続いて、インバウンド顧客が来店した店舗に、海外のお客様に対し、困っていることを答えてもらった。すると、多くの店舗から「外国語対応」に関する悩みが寄せられた。ほかにも、国内においては常識的なルールに関する問題など、各店さまざまな悩みを抱えているようだ。
言葉の壁によるコミュニケーションの難しさ
- 外国語がわからずオーダーに時間がかかる、コミュニケーションが取りづらい(東京都/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 日本を満喫してもらえるように、満足してもらいたいのですが、細かなニュアンスやコミュニケーションが取れなく、行き届かない(東京都/イタリア料理/1店舗)
- 言葉がわからない場合が多いことポケトークをはじめとする翻訳機で対応中(京都府/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
飲食店の一般的なルールを理解してもらえない
- 勝手に持ち込みをして食べる(東京都/イタリア料理/51~100店舗)
- お一人ワンオーダーを守れない方が多い。それを説明する手間が大変(愛知県/カフェ/1店舗)
- 連絡なしのキャンセルや寸前でのキャンセル(神奈川県/鉄板焼き・お好み焼/1店舗)
その他
- 食べ残しが多い(埼玉県/イタリア料理/6~10店舗)
- トイレの使用方法。非常に不衛生な使用が目立つ(大阪府/その他/101店舗以上)
- お通しの説明が難しい(大阪府/その他/6~10店舗)
- 困る人は日本人・外国人関係なく、個人差(東京都/カフェ/1店舗)
ベジタリアン・ヴィーガンに対応している店舗は1割未満
次に、各店のインバウンド対応状況について質問したところ、「WiFiの導入(50.8%)」や「モバイル決済・クレカ対応範囲の拡大(銀聯やアリペイ、WeChatPayなど)(43.2%)」を実施している店舗が目立つ結果となった。
一方、集客面や外国語対応といった部分に関しては、実施に前向きな店舗はあるものの、実際に対策を打っている店舗は少ない様子が明らかとなった。特に、「インバウンド顧客向けのコース設定・メニュー開発」や「ベジタリアン・ヴィーガン等への対応」といった食材や調理方法に関わる対策はさまざまな面でハードルが高いようで、実施店舗は共に1割未満、今後の実施予定がないとの回答も77.0%で同率トップとなっている。

続いて、インバウンド対応策を実施、もしくは検討している店舗に、最もインバウンド対策に繋がると思われる施策を選んでもらった。すると、「インバウンド顧客向けの観光情報媒体掲載」との回答が27.3%で最多に。続いて「インバウンド顧客向けのSNS発信(20.2%)」と、集客に関わる施策が上位となった。

その施策を選んだ理由について尋ねたところ、「インバウンド顧客向けの観光情報媒体掲載」と「インバウンド顧客向けのSNS発信」を選んだ店舗からは、「認知や来店に繋がる」という意見が挙がった。ほかに「自身や周りの店舗の集客経験」というコメントも見られた。
▼「インバウンド顧客向けの観光情報媒体掲載」を選んだ理由
- 店を認知していただくことが最優先(埼玉県/カフェ/1店舗)
- 多くの方が観光情報誌を片手にご来店されているため(長野県/中華/1店舗)
- 過去働いていたお店ではインバウンド向けのグルメ雑誌に掲載していたが、そこからの予約が週1以上あったから(東京都/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 顧客が店舗の情報を知るためには何よりもまず、顧客の母国語での案内が必要であると考えているため(東京都/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
▼「インバウンド顧客向けのSNS発信」を選んだ理由
- 最も発信力が強く、来店に繋がるのがSNSと感じるから(東京都/その他/11~30店舗)
- 顧客に対する影響力が一番あるツールであると考えるから(神奈川県/バー/1店舗)
- やはり世界的にもSNSで情報を得ていると思うので(福岡県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 来られた方の大半はSNSで見たとのことだったので(東京都/バー/1店舗)
土地柄を理由にインバウンド顧客獲得に消極的な店舗も
インバウンド顧客は「来店していない(わからない)」と回答した店舗に、今後、積極的にインバウンド顧客の獲得をするか尋ねたところ、「特にインバウンド顧客を意識していない(国内顧客と同様に考えている)」が60.5%という結果に。また「できれば、インバウンド顧客は避けたい」との回答も32.2%見られた。

上記のように回答した理由については、「土地柄やターゲット層の違い」を挙げる店舗が多く見られた。また、「外国語対応ができない」ことを理由にする店舗もあるなど、さまざまな事情からインバウンド顧客の獲得に積極的ではないようだ。
▼「特にインバウンド顧客を意識していない」を選んだ理由
リピーターや地元のお客様を大切にしたいから
- 小さいお店なのでリピーターのお客様を大事にしたい(東京都/イタリア料理/1店舗)
- インバウンドは、高価格帯、閑散期の来客が見込めるが、世界情勢に影響されやすく、経営の不安定に繋がる懸念がある。長期経営目標の中では第一に地元常連顧客の支持が大切だから(東京都/洋食/1店舗)
- 設備、メニューを含む手間を考えると国内を先ずは固めたい(埼玉県/中華/1店舗)
インバウンド需要が高くないエリアだから
- エリア的にインバウンド需要がそれ程高いとは思っていないから(大阪府/イタリア料理/1店舗)
- 地域的に、インバウンド需要が見込めないと考えているため(三重県/その他/1店舗)
▼「できれば、インバウンド顧客は避けたい」を選んだ理由
外国語対応ができないため
- 言語が通じないためトラブル回避(埼玉県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 外国語が苦手(兵庫県/専門料理/1店舗)
リピーター化を見込めないため
- 一見さんを当てにしてないので(埼玉県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 続けていらっしゃるわけではないので(東京都/その他/1店舗)
今回のアンケートでは、約6割の店舗で外国人客が訪れている一方、全体としてはさほどインバウンド対応が進んでいない実態が明らかとなった。今後、インバウンド需要は回復すると見られており、外国人観光客がさらに増えることも予想される。インバウンド需要を取り込みたい店舗は、今回のアンケート結果も参考にしながら、対策を進めてみてはどうだろうか。
飲食店経営者が集う「飲食店リサーチ」
アンケート調査結果が見れる!店舗経営に役立つ!

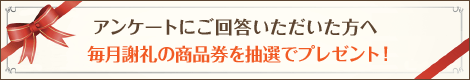
最近のアンケート調査結果
- 月例アンケート:2025年12月の経営状況は? (2026/01/15)
- 飲食店の「労働時間」に関するアンケートのお願い (2026/01/05)
- カテゴリ
- 飲食店経営に関する調査レポート
- その他
- 新着記事
新着記事一覧へ
飲食店リサーチマガジンについて
『飲食店リサーチ』で実施した調査によって得られたデータなど、『飲食店ドットコム』が保有するデータに対し様々な考察を加えて記事を作成。飲食店の経営に役立つ情報を毎月定期配信しています。


