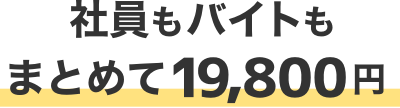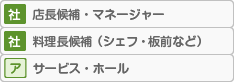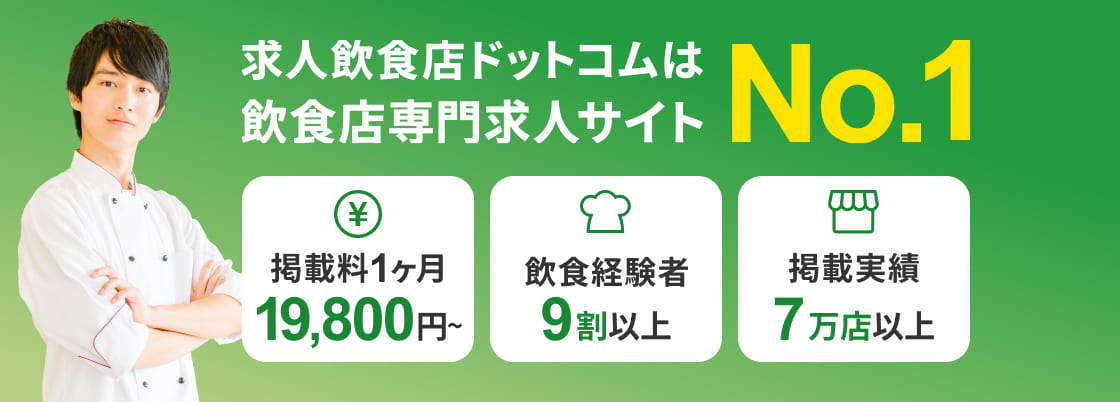画像素材:PIXTA
コロナ後に採用ミスマッチが増えた理由
慢性的な人手不足に陥っている飲食業界。厚生労働省発表の令和3年雇用動向調査結果の主要産業別労働移動者をみると、入職者数は「宿泊業,飲食サービス業」が1,179.5千人と最も多かったものの、離職者数も「宿泊業,飲食サービス業」が 1,270.9 千人と最も多い結果に。離職率は25.6%となっており、せっかく人材を確保しても、4人に1人が辞めていることが明らかになりました。早期離職の背景のひとつが、採用後のミスマッチです。飲食店側の「こんな人に働いてほしい」という思いと、従業員側の「こんな職場で働きたい」という希望とがかみ合わず、社員が職場に居心地の悪さを感じたり、失望したりして離職してしまうケースは後を絶ちません。
こうしたミスマッチは、コロナ禍を経ていっそう起こりやすくなっているようです。政府が多額の助成金や補助金を投入して失業者の発生を抑えたことが影響しているという意見があります。
例えば、コロナ流行中でお客さまの来店がほとんどなく、助成金や補助金で経営を支えている時期に、居酒屋に雇用されていた人がいるとしましょう。その人は平常時の居酒屋の忙しさを知らないために「居酒屋の仕事は楽だ」と思ってしまい、何かのきっかけで転職する際も、居酒屋勤務を希望します。
しかし「忙しい環境での仕事は向かず、ゆったりと働けるカフェで働く方が合っている」、もしくは「そもそも飲食業界が向いていない」人材という可能性も十分に考えられます。つまり、コロナ禍を乗り切ったプラスの思い出が思い込みを生み、それがミスマッチを引き起こしているのです。
採用後のミスマッチを防ぐ方法
採用後のミスマッチを防ぐには、求職者に「本当にここで働きたいのか」「働けると思うか」を真剣に考えてもらうことが大切です。ここからは、より具体的な対策を見ていきましょう。■企業・店舗のことを具体的に知ってもらう
採用活動では、企業・店舗の情報を詳しく開示してください。募集要項などに記載する基本的な情報だけでなく、お店としての価値観や働き方を十分に理解したうえで入社してもらうことで、入社後の「こんなはずじゃなかった」を減らすことができます。■欲しい人物像を明確にする
企業・店舗がどんな人物を求めているかを明確にすることも、イメージのすり合わせには欠かせません。ポジションやキャリアイメージを具体的に挙げ、入社後はどのように活躍してほしいのかきちんと伝えれば、そうした働き方を希望する人材とのマッチングが叶いやすくなるはずです。■飲食店側の要求をきちんと伝える
採用後の不満として新入社員から多く聞かれるのが「仕事内容が想定と違った」というもの。採用の際は、任せたい仕事の内容や求めるスキルなどをできるだけ詳しく伝えられるといいでしょう。採用後の人材教育も欠かせない
採用活動中、企業・店舗が自社を魅力的に見せたいのと同じように、求職者も「自分をよく見せたい」もの。採用活動の進め方を工夫するだけでは、ミスマッチをなくすことはできません。提示した条件と多少ズレがあった人材にも、自社で成長し定着してもらえるよう、採用後は人材教育に力を入れていきましょう。企業・店舗側が「徐々に仕事を覚えてもらおう」という教育姿勢では、新人は仕事を覚えることができず、モチベーションは落ちていきます。人材教育でまず見直したいのは、関わり方です。新入社員が「自分は組織で大切にされている、期待されている」と感じられているか、考えてみましょう。
例えば、基本的なことから段階的に教えていく、一方的に指示を出すのではなく、指示された側が理解しやすいよう配慮するなどぜひ意識してください。また、真剣に取り組んでいる中で失敗したときにはしっかりとフォローしてください。安心感につながり、帰属意識が高まっていきます。
離職を決意する人の多くは、人間関係や労働環境に違和感を覚えています。誰もが働きやすい環境を整備できれば、採用後のミスマッチを防ぐことにもつながるはず。ぜひ、企業・店舗全体で取り組んでみてくださいね。
【関連記事】
■ 応募が来ない、内定辞退が多い… 人材確保を阻む「採用課題」を見つけよう■ 飲食店がすべき“採用の事前準備”とは? ミスマッチを防ぐ効率的な採用活動