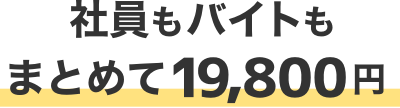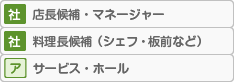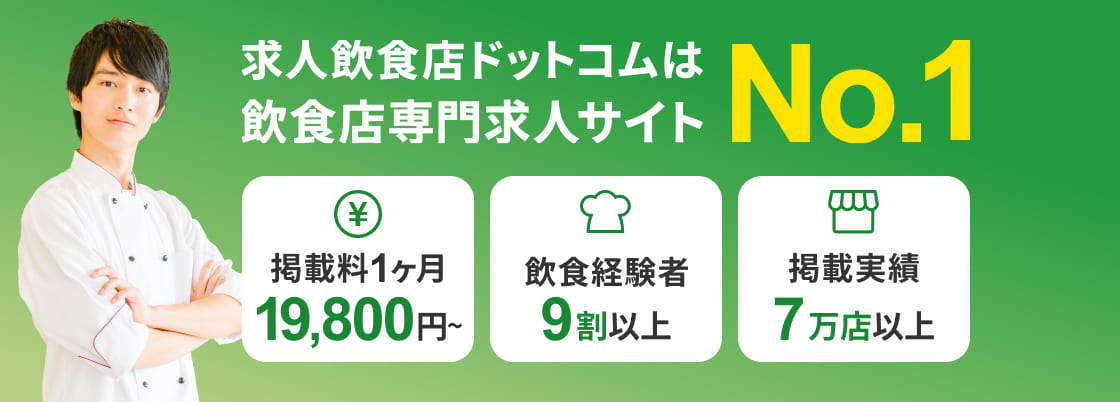画像素材:PIXTA
そもそも…「採用課題」とは?
採用課題とは、求人を掲載しても応募が集まらない、応募があっても望むような応募者ではないなど、「採用活動がうまくいかない原因」のこと。採用課題が生じやすいのは、次の3つの段階だと言われています。1 求人を募集している時
2 応募者の選考を行っている時
3 採用して入社まもない時
まずは自社の採用フローを見直したうえで、それぞれの段階でどのくらいの脱落者が発生しているのかを確認してください。
課題を発見し、改善することで、採用活動の成果は出やすくなりますし、費用対効果を高めることもできます。
「そもそも応募が来ない」、「思うような人材が集まらない」場合は?
求人を出しても応募が来ない場合、ありがちな課題は・求人の露出が少ない
・掲載媒体が合わない
・求人内容、アピールが求職者に届いていない
・給与や福利厚生などの待遇が相場より低い
などが考えられます。
求人サイトには、それぞれ特性があり、正社員募集に強い媒体があれば、アルバイト募集を得意とする媒体もあります。一つの媒体にとらわれず、アピールしたい層とより相性の良いサイトに切り替えたり、SNSでも求人募集を掲載していることを発信したりして、「欲しい求職者の目に触れる」場を増やしてください。
仕事内容だけでなく、「職場の雰囲気」や「将来性」についてもわかりやすく記載することをおすすめします。特に「将来性」は重要で、会社として目標を伝え、従業員になった後はどういった働き方をしていくのかをイメージできるようにすると良いでしょう。
他社と比べて自社の待遇に大きく劣る部分がある場合には、求職者に選ばれる会社になれるチャンスと捉え、出来る範囲での改善を検討してください。
選考中に課題がある場合は、採用フローの見直しを
選考段階で起こりがちなのは、・連絡をしていても採用面接に来ない
・面接して採用連絡をしても辞退される
という2点。もし書類選考後、採用面接に来ない、断られることが多いようなら、まず応募が来てから面接予定を連絡するまでにどのくらいの時間を要しているかを確かめてください。面接の辞退率を下げるための第一歩は、応募から24時間以内に返信をすることです。
面接して採用の連絡をしても内定辞退されることが多いなら、内定から入社までの間も定期的にコミュニケーションをとるよう心がけましょう。例えば経営層と気軽に話せる機会をつくると、「自分は歓迎されている」という気持ちが高まり、仕事へのモチベーションを引き出すこともできるはずです。
そして、もう一つ、面接時の面接官の態度や質問内容を確認し、そこに何か問題がないか検証することも大切です。応募者は面接官の応対はもちろん、店舗を訪れた時の雰囲気や周りにスタッフがいれば、その対応などもしっかりと見ているものです。「会社全員が新たな人材を歓迎している」ことが伝わるよう徹底しておきましょう。
入社しても退職が続くのは、「ギャップ」があるから
せっかく採用した人材が短期間で辞めてしまう…ということが多いなら、募集記事に記載している仕事内容や職場の雰囲気、待遇と現実にギャップがあるのかもしれません。応募数を増やしたいからと良いところばかりを並べていませんか?魅力ばかりを伝えるのではなく、大変さも隠さずに伝え、入社後の「こんなはずでは…」を避けるようにしたいものです。入社後のフォロー体制に問題がないかも確認してください。昔ながらの「見て覚えろ」では今は受け入れられません。挫折者が続出する恐れもあります。気兼ねなく何でも質問できる先輩スタッフを指導役につける、上司との定期的なカジュアル面談を設けるなど不安を感じさせないためのフォロー体制を整えておきたいものです。
思うような採用活動を展開できないのには、必ず「理由」があります。慢性的に人材不足が続く中、優秀な人材確保のチャンスを逃さないために、しっかりと自社の採用フローとその問題点を見直し、できるところから改善に取り組んでいきましょう。
【関連記事】
■ 応募が来ない!ハードルを下げて、応募前後の離脱を防ぐポイントは?■ 応募者は見ている! 飲食店の採用活動・面接におけるNG行動とは?