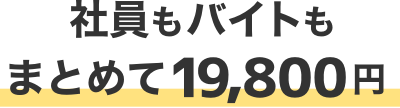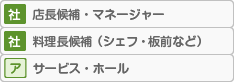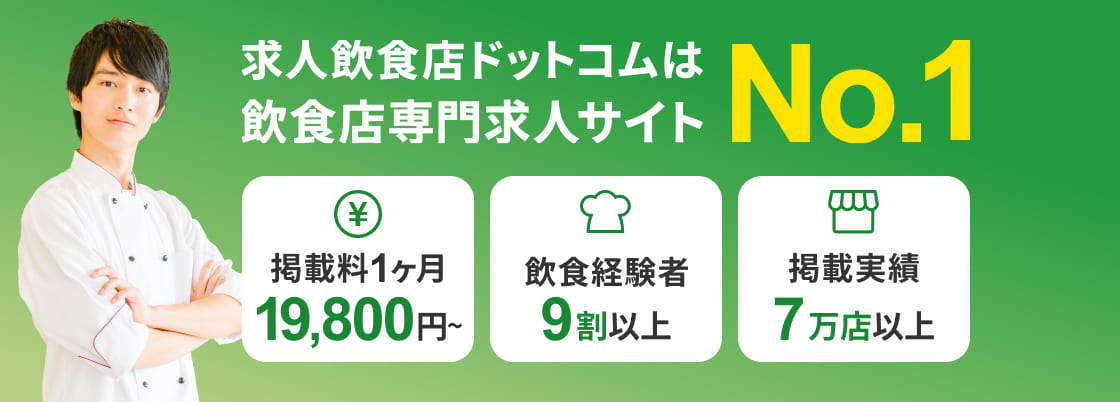画像素材:PIXTA
「福利厚生」とは?
福利厚生とは、簡単にいうと従業員やその家族に提供する給与以外の報酬のこと。生活の安定・向上、モチベーションアップなどを目的に整備されます。福利厚生には法律で定められた「法定福利」と、会社ごとに独自に設ける「法定外福利」の2種類があります。法定福利に該当するのは社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)です。一方、法定外福利は会社によって異なります。例えば食事や飲料の提供、社員旅行などが該当します。
個人事業主も福利厚生を導入できる
福利厚生は法人化をしていない個人事業主でも導入することが可能です。ただし、経営形態によっては導入できません。個人事業主の形態は大きく3つに分けられます。
・事業主1人で事業を営む
・事業主とその家族で事業を営む
・事業主と雇用した従業員の複数で事業を営む
このうち、福利厚生を導入できるのは、「事業主と雇用した従業員の複数で事業を営む」場合のみ。個人事業主が自分自身に福利厚生を設けたり、家族従業員へ適用したりすることはできません。
また、どんなものでも福利厚生として認められるわけではありません。福利厚生費として処理が認められるのは次の2つの条件を満たす場合に限られます。
・すべての従業員が平等に利用できる
・社会通念上妥当だと思われる金額の範囲内である
つまり、役員や一部の従業員しか使える条件を満たさないようなものや、著しく高額なものなどは認められないということです。
個人の飲食店でも導入しやすい福利厚生
福利厚生費は経費として計上できるため、税金の負担を減らすことにつながります。また、福利厚生を利用したからといって、従業員の収入が減るようなことはありません。個人事業主と従業員の双方にメリットがある制度と言えます。では、個人事業主でも導入しやすいのはどんなものでしょうか。
・まかない制度
・自店利用時の割引制度
・慶弔休暇制度
・給与前払い制度
・人間ドックや各種予防接種の実施
まず、ここで知っておきたいのは、無料でまかないを提供することは給与の現物支給とみなされることです。給与となれば、所得税・住民税の課税対象になります。
ただし、以下の条件を満たせば課税対象にはなりません。
1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2. (食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
※国税庁では「食事の価額(まかないの価額)」を「食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額」と定義しています。
個人店では、求人広告に“美味しいまかない食べ放題”といった打ち出しをしていることがあるかもしれません。支給のルールをしっかりと理解することが大切です。
個人事業主が福利厚生を導入する場合の注意点
まかない以外にも次のような点を理解しておきましょう。・従業員のために出費は福利厚生費、取引先の接待は交際費
例えば従業員の結婚祝いは福利厚生費、取引先への結婚祝いは交際費として処理します。
・健康診断費用は福利厚生費に計上できる
事業主は従業員に年1回健康診断を受診させる「義務」がありますが、帳簿上では福利厚生費として計上できます。
計上に関しては、専門家や税務署により意見が分かれるケースがあります。不安がある場合、問合せをしてください。
アルバイトにも福利厚生の導入を
アルバイトへのまかない制度などがあるように、福利厚生はアルバイトも利用できます。むしろ「同一労働同一賃金」が導入された現在では、正社員と同様の働き方をするアルバイトは、正社員と同等の福利厚生が利用できるように整備すべきです。 また、求人募集において給与では差別化が難しくなっている今、待遇面で魅力を出すことはアルバイトを確保していくためにも非常に重要です。コロナの影響などもあり、「従業員の給与を上げたいけど難しい」「人材確保に苦労している」という飲食店は少なくないでしょう。新たな福利厚生の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【関連記事】
■ 飲食店が導入しやすい「福利厚生」は? 従業員の満足度&モチベーションアップに有効■ 【飲食店の働き方改革】あの店のスタッフ待遇がスゴイ! 飲食店の好待遇事例を5つ紹介