飲食店における価格高騰の影響を調査。68%が値上げを実施するも、73%が「客足に影響なし」
2023年5月22日
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
<本調査について>
■調査概要
調査対象:飲食店ドットコム会員(飲食店経営者・運営者)回答数:374名
調査期間:2023年3月6日~2023年3月13日
調査方法:インターネット調査
■回答者について
本調査にご協力いただいた回答者のうち72.5%が1店舗のみを運営。また、回答者のうち東京にある飲食店の割合は48.7%(首都圏の飲食店の割合は66.7%)となっており、こうした背景が結果に影響していると推測される。<調査結果について>
98%の飲食店が物価高騰を実感、うち95%が仕入れ額増加
はじめに、物価高騰の影響を感じているか答えてもらったところ、98.1%が「実感している」(とても実感している=81.3%、やや実感している=16.8%)と回答。「実感はない」との回答はわずか1.9%で、大半の飲食店が物価高騰の影響を受けていることがわかる。
 次に、物価高騰の影響を実感している(とても実感している、やや実感している)と回答した方に、物価高騰を実感し始めた時期を尋ねたところ、86.7%の人が「2022年中」に物価高騰を実感し始めたと回答した。全体をみると、物価高騰を実感し始める人の割合は徐々に増えていっており、2022年3月までに物価高騰を感じ始めた人は22.9%だったが、6月末には44.2%、12月末には94.3%にまで増加している。
次に、物価高騰の影響を実感している(とても実感している、やや実感している)と回答した方に、物価高騰を実感し始めた時期を尋ねたところ、86.7%の人が「2022年中」に物価高騰を実感し始めたと回答した。全体をみると、物価高騰を実感し始める人の割合は徐々に増えていっており、2022年3月までに物価高騰を感じ始めた人は22.9%だったが、6月末には44.2%、12月末には94.3%にまで増加している。
 また、物価高騰の影響を実感している主な対象について答えてもらったところ、最も多かったのは「電気」で79.8%。次いで、「食用油(73.3%)」、「ガス(60.8%)」と、多くの飲食店にとって必要不可欠なものの回答が目立つ結果となった。このほかにも、「酒類(58.3%)」、「鶏卵(57.8%)」、「小麦粉、小麦加工品(52.6%)」が5割を超えるなど、さまざまな製品の価格に影響がでている様子がうかがえる。
また、物価高騰の影響を実感している主な対象について答えてもらったところ、最も多かったのは「電気」で79.8%。次いで、「食用油(73.3%)」、「ガス(60.8%)」と、多くの飲食店にとって必要不可欠なものの回答が目立つ結果となった。このほかにも、「酒類(58.3%)」、「鶏卵(57.8%)」、「小麦粉、小麦加工品(52.6%)」が5割を超えるなど、さまざまな製品の価格に影響がでている様子がうかがえる。 続いて、物価高騰の影響を実感している方に、2023年2月の仕入れ総額を昨年同月と比較してもらったところ、95.2%が「昨年同月より上昇した」と回答し、多くの店舗で昨年より仕入れ総額が増加していることがわかった。なお、「21%以上上昇」した店舗は、全体の半数近くにもおよんでいる。
続いて、物価高騰の影響を実感している方に、2023年2月の仕入れ総額を昨年同月と比較してもらったところ、95.2%が「昨年同月より上昇した」と回答し、多くの店舗で昨年より仕入れ総額が増加していることがわかった。なお、「21%以上上昇」した店舗は、全体の半数近くにもおよんでいる。

物価高騰受け、「値上げ」や「食材ロス削減」を実施する店舗も
物価高騰の影響を抑えるための取り組みを尋ねたところ、「既存メニューの値上げ」との回答が、67.9%で最多。次いで、「仕込み、仕入れ過多等による食材ロスの削減(43.3%)」、「新メニューの開発(34.8%)」と、料理や食材といった部分で、物価高騰の影響を抑えようとしている店舗が多いようだ。
 次に、先ほど回答した取り組みについて、具体的にどのようなことをしているか答えてもらった。すると、「既存メニューの値上げ」を一つとっても、各店さまざまな工夫をしている様子がわかった。以下では、上位となった3つの取り組みについて、いくつか抜粋して紹介する。
次に、先ほど回答した取り組みについて、具体的にどのようなことをしているか答えてもらった。すると、「既存メニューの値上げ」を一つとっても、各店さまざまな工夫をしている様子がわかった。以下では、上位となった3つの取り組みについて、いくつか抜粋して紹介する。既存メニューの値上げ
- 売れ筋商品の価格を据え置きにして、全体的に値上げをおこなった(神奈川県/カフェ/1店舗)
- 主力商品は30円程の値上げ。その他は50円からの値上げ(長野県/中華/1店舗)
- 単純な値上げではなく、メニューをリニューアルしつつ客単価が上がるような構成に変えた(東京都/イタリア料理/51~100店舗)
仕込み、仕入れ過多等による食材ロスの削減
- グランドメニューをなくし、日替わりのみにして、食材ロスを削減(神奈川県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- (保存用の)真空パック器を使い、ロスの削減に努める(神奈川県/カフェ/1店舗
- 使いまわせる食材を増やして、食材ロスを激減させている(神奈川県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
新メニューの開発
- ロスの少ない食材を使い、シンプルなオペレーションで満足感の高い商品を開発(東京都/中華/2店舗)
- 早めの時間帯に来店するお客様に向けた食事を増やした(東京都/バー/1店舗)
- 少量、短時間で作れるメニューの開発(長野県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
続いて、「既存メニューの値上げ」をしている店舗に対し、値上げをしたメニューの割合を答えてもらったところ、22.8%が「51%~70%」と回答し、最多となった。また、全体をみると「91%~100%」との回答は14.6%にとどまり、メニューの値上げについては“部分的に”行った店舗が多いことがわかる。
 さらに、何%程度値上げしたか尋ねたところ、最多は「6~10%」との回答で、48.4%。続く、「11%~15%(27.2%)」、「5%以下(15.7%)」と合わせると、15%以内の値上げが9割を占めることがわかる。20%を超える値上げは、2.4%にとどまった。
さらに、何%程度値上げしたか尋ねたところ、最多は「6~10%」との回答で、48.4%。続く、「11%~15%(27.2%)」、「5%以下(15.7%)」と合わせると、15%以内の値上げが9割を占めることがわかる。20%を超える値上げは、2.4%にとどまった。
 また、既存メニューの値上げをした後に、客足に変化があったか回答してもらった。すると、72.8%が「変化はない」と回答。「減った」(とても減った=1.6%、やや減った=20.5%)との回答は22.1%で、多くの店舗で値上げが客足に影響しなかったことが明らかとなった。
また、既存メニューの値上げをした後に、客足に変化があったか回答してもらった。すると、72.8%が「変化はない」と回答。「減った」(とても減った=1.6%、やや減った=20.5%)との回答は22.1%で、多くの店舗で値上げが客足に影響しなかったことが明らかとなった。

外食の安値思考、変化を求める一方で「難しい」との声も
最後に、現代の外食文化における「低価格であることを良しとする価値観(安値思考)」について、率直な感想を尋ねたところ、「安値思考が変わって欲しい」という意見がでる一方、「現実問題として安値思考を変えるのは難しい」という声も聞かれた。また、「低価格でも経営が上手くいっていれば良い」といった、肯定的な回答もみられるなど、さまざま意見が寄せられた。以下では、いくつかを抜粋してご紹介する。
物やサービスの価値に見合った価格設定をすべき
- 価値に見合った価格の設定をすることで、外食における産業全体の地位向上をめざすべき(愛知県/和食/1店舗)
- 原価の掛かっているもの、手の掛かっているものに対してはそれに見合った価格を設定しなければならないし、オーナーも含めた提供する側・売り手はプライドを持ってそのことを続けなければならないと思う(東京都/バー/1店舗)
価格帯ごとに業態の棲み分けができればよい
- 高い価格でもクオリティを維持すれば客足はキープできると思う。安価なチェーン店と棲み分けするしかない。価格ではどうしても対抗できない(東京都/その他/1店舗)
- いいものは高い、安すぎるものは質がよくない。高くていいものを求める人、それぞれ求めるところを棲み分けできていれば自然に経済が回ってくれると思う(長野県/居酒屋・ダイニングバー/3~5店舗)
お客様に適正価格の重要性を理解して欲しい
- 価格努力はすべきであるが、従業員の就業環境を整える余裕のある価格をお客様に理解してもらいたい。このままでは飲食店で働く人がいなくなってしまう(東京都/和食/3~5店舗)
- 全てのものには適正価格があり、安価なものにはそれなりの理由がある。高値がつくものにもそれなりの理由があるのでお客様にはそのことをきちんと理解していただければと思っています(兵庫県/和食/1店舗)
低価格でも経営が成り立ち、商品・サービスの質が保持されているなら良い
- 低価格も一つの企業努力なので良いと思う(福岡県/居酒屋・ダイニングバー/6~10店舗)
- 低価格でも、美味しければいいと思う(大阪府/カフェ/1店舗)
現在の安値思考を変えるのは難しい
- 昨今の物価上昇をきっかけにして 適正価格で販売すべきとは思うが、現実問題はそうもいかないと感じる(長野県/中華/1店舗)
- 長年、大手飲食店がデフレ競争をしてきたので、一般客はその金額がベースになってしまっている。その感覚を引き上げていくのはかなり難しい(東京都/イタリア料理/3~5店舗)
その他
- どこでもいつでも体験、飲食できる物は、価格競争でしか生き残れない。この店でしか提供、体験できない物を作り上げていくことが大切(沖縄県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 大手のチェーン店などは企業努力で低価格を実現出来るかも知れないが、それを個人店に求められるのは正直辛い(東京都/イタリア料理/1店舗)
今回のアンケートでは、ほぼ全ての飲食店が価格高騰の影響を受けていることがわかったが、各店さまざまな工夫をし、この苦難を乗り越えようとしている。食品などの値上げは今後も続くとみられ、不安を感じている飲食店も多いと思うが、できる範囲の努力を続け売上アップにつなげていきたい。
飲食店経営者が集う「飲食店リサーチ」
アンケート調査結果が見れる!店舗経営に役立つ!

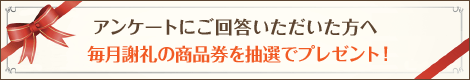
最近のアンケート調査結果
- 月例アンケート:2025年12月の経営状況は? (2026/01/15)
- 飲食店の「労働時間」に関するアンケートのお願い (2026/01/05)
- カテゴリ
- 飲食店経営に関する調査レポート
- その他
- 新着記事
新着記事一覧へ
飲食店リサーチマガジンについて
『飲食店リサーチ』で実施した調査によって得られたデータなど、『飲食店ドットコム』が保有するデータに対し様々な考察を加えて記事を作成。飲食店の経営に役立つ情報を毎月定期配信しています。


