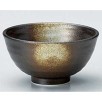- 厨房備品ECトップ
- 厨房マガジン
- 厨房用品・調理道具の選び方
- 記事詳細

Photo by iStock.com/yukihipo
日本料理店や居酒屋などで欠かせない和の器「やきもの」。カフェやレストランなど、料理のジャンルにとらわれず使われることも増えています。「陶磁器」とひとくくりに呼ばれることもありますが、陶器と磁器では、製造方法や特徴が異なります。そこで今回は、それぞれの違いやお手入れ方法などをご紹介します。
■陶器の特徴
主な原材料は陶土という粘土で「つちもの」とも呼ばれます。成型し、ゆう薬をかけ、1100~1300度の温度で焼き上げます。吸水性が高いのが特徴ですが、ゆう薬は、器の強度を高め、吸水力を減らします。また、ゆう薬もさまざまな種類があり、焼成するとそれぞれの色に変化し、器を彩ります。素朴な味わいのある『笠間焼』(茨城県)や『益子焼』(栃木県)などは若い作家も多く、日本料理だけでなくカフェなどでもよく使われています。
■磁器の特徴
主な原材料は長石、石英で「いしもの」とも呼ばれます。ガラス質を形成するゆう薬をかけ1700度ほどの温度で焼成します。白く透き通るような下地に絵付を施されたものが、和食器ではよく使われます。色絵の磁器で代表的なものは『九谷焼』(石川県)『伊万里焼』『有田焼』(佐賀県)。また、カジュアルな磁器として狙い目なのが『波佐見焼』(長崎県)です。
陶磁器の全国シェア60%以上を占める『美濃焼』(岐阜県)や「瀬戸もの」と食器の代名詞ともなった『瀬戸焼』(愛知県)は陶器と磁器の両方が作られています。
■せっ器の特徴
陶器と磁器の中間的なものを「せっ器」といいます。ゆう薬をかけず、高温で「焼締め」をするのが特徴です。吸水性はありません。素朴な地肌が趣深い『備前焼』(岡山県)、朱色の急須で有名な『常滑焼』(愛知県)などがあります。

■陶器
吸水性があるため、お手入れに少々手間がかかります。初めて使う際には「目止め」が必要です。食器を鍋に入れ、お米のとぎ汁に浸して15~20分ほど弱火で煮沸します。そして、鍋ごと冷まし、よく洗い、充分に乾燥させます。ひび状の貫入が入ったものは、油などがしみこむ恐れがあるので、使う前に必ずぬるま湯に浸してから使いましょう。また、汚れがしみこまないよう使用後はすぐ洗い、よく乾かしてからしまいましょう。
■磁器
磁器は吸水性が低いのですが、やはり洗った後はよく乾かしてから片付けましょう。金彩・銀彩のものは柔らかい布やスポンジで丁寧に洗うなど取扱いに注意が必要です。絵付きのものは傷つく恐れがあるので、和紙などを挟んで積み重ねます。また、磁器は陶器より硬いので、この2種類を積み重ねると陶器が傷つきます。必ず分けて収納しましょう。
陶器の場合、冷たい料理を盛り付ける前に氷水に漬けておくと水が染み込み「冷たいものは冷たいままに」提供することができます。また、魚料理などのにおいが食器に移らず、汚れも付きづらいというメリットもあります。なお、磁器は急冷に弱いので、冷蔵庫などで急激に冷やさないよう注意しましょう。
■温かい料理の盛り付け
陶器の場合、50度ぐらいのお湯を張って器を温めながら水を染み込ませておくと、料理が冷めにくくなります。磁器は急激な温度変化に弱いため、冷えた食器を急激に温めることはNGです。ぬるま湯にくぐらせるとよいでしょう。
いかがでしたか。和のやきものは、使ってお手入れをするたびに風合いが出てきます。陶器、磁器それぞれの特性を生かして料理を提供するのに、ぜひ参考にしてください。
陶器と磁器の違いとは?「やきもの」の種類
陶器と磁器の違いは一見すると分かりづらいかもしれません。おおまかな見分け方としては、見た目がやわらかく指ではじくと鈍い音がするのが陶器で、薄手で冷たい感じがあり、指ではじくとキンと硬い音がするのが磁器です。■陶器の特徴
主な原材料は陶土という粘土で「つちもの」とも呼ばれます。成型し、ゆう薬をかけ、1100~1300度の温度で焼き上げます。吸水性が高いのが特徴ですが、ゆう薬は、器の強度を高め、吸水力を減らします。また、ゆう薬もさまざまな種類があり、焼成するとそれぞれの色に変化し、器を彩ります。素朴な味わいのある『笠間焼』(茨城県)や『益子焼』(栃木県)などは若い作家も多く、日本料理だけでなくカフェなどでもよく使われています。
■磁器の特徴
主な原材料は長石、石英で「いしもの」とも呼ばれます。ガラス質を形成するゆう薬をかけ1700度ほどの温度で焼成します。白く透き通るような下地に絵付を施されたものが、和食器ではよく使われます。色絵の磁器で代表的なものは『九谷焼』(石川県)『伊万里焼』『有田焼』(佐賀県)。また、カジュアルな磁器として狙い目なのが『波佐見焼』(長崎県)です。
陶磁器の全国シェア60%以上を占める『美濃焼』(岐阜県)や「瀬戸もの」と食器の代名詞ともなった『瀬戸焼』(愛知県)は陶器と磁器の両方が作られています。
■せっ器の特徴
陶器と磁器の中間的なものを「せっ器」といいます。ゆう薬をかけず、高温で「焼締め」をするのが特徴です。吸水性はありません。素朴な地肌が趣深い『備前焼』(岡山県)、朱色の急須で有名な『常滑焼』(愛知県)などがあります。

Photo by iStock.com/yukihipo
お手入れ方法は?
陶器と磁器、それぞれお手入れ方法があり、注意が必要です。■陶器
吸水性があるため、お手入れに少々手間がかかります。初めて使う際には「目止め」が必要です。食器を鍋に入れ、お米のとぎ汁に浸して15~20分ほど弱火で煮沸します。そして、鍋ごと冷まし、よく洗い、充分に乾燥させます。ひび状の貫入が入ったものは、油などがしみこむ恐れがあるので、使う前に必ずぬるま湯に浸してから使いましょう。また、汚れがしみこまないよう使用後はすぐ洗い、よく乾かしてからしまいましょう。
■磁器
磁器は吸水性が低いのですが、やはり洗った後はよく乾かしてから片付けましょう。金彩・銀彩のものは柔らかい布やスポンジで丁寧に洗うなど取扱いに注意が必要です。絵付きのものは傷つく恐れがあるので、和紙などを挟んで積み重ねます。また、磁器は陶器より硬いので、この2種類を積み重ねると陶器が傷つきます。必ず分けて収納しましょう。
料理を美味しくする豆知識
■冷たい料理の盛り付け陶器の場合、冷たい料理を盛り付ける前に氷水に漬けておくと水が染み込み「冷たいものは冷たいままに」提供することができます。また、魚料理などのにおいが食器に移らず、汚れも付きづらいというメリットもあります。なお、磁器は急冷に弱いので、冷蔵庫などで急激に冷やさないよう注意しましょう。
■温かい料理の盛り付け
陶器の場合、50度ぐらいのお湯を張って器を温めながら水を染み込ませておくと、料理が冷めにくくなります。磁器は急激な温度変化に弱いため、冷えた食器を急激に温めることはNGです。ぬるま湯にくぐらせるとよいでしょう。
いかがでしたか。和のやきものは、使ってお手入れをするたびに風合いが出てきます。陶器、磁器それぞれの特性を生かして料理を提供するのに、ぜひ参考にしてください。
飲食店ドットコム 厨房備品ECでは、飲食店専門の厨房機器・料理道具、店舗備品・衛生用品などを多数取り揃えています。
和食器・そば・丼のカテゴリ一覧はこちら
<関連記事>業務用和食器の種類と特徴を知る!~基礎知識~
<関連記事>世界で愛される有田焼 ~やきものの歴史と特徴を知ろう~