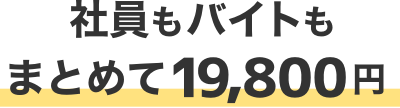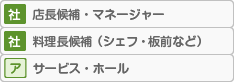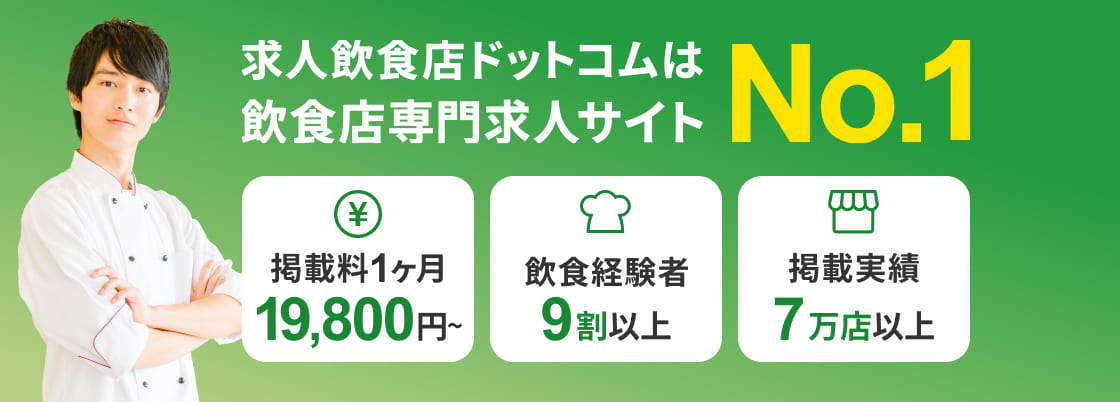Photo by iStock.com/visualspace
Photo by iStock.com/visualspace
一週間単位の変形労働時間制について
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできません。この時間を超えた労働に対しては、割増賃金を支払う義務があります。ただし、業務の繁閑の差が激しい場合に、1週間40時間以内であることを前提に、1日10時間まで働いてもらえることが認められており、これを変形労働時間制といいます。
例えば、土日が平日に比べて何倍も忙しく、従業員数が少ないため、土日の人数を十分に揃えることができない店舗であれば、平日の休みを多くする分、土日に10時間まで働いてもらうことができるという制度になります。
一週間単位の変形労働時間制の導入にはいくつか条件があります。まずは、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店等の事業であること。1週間40時間を超えて労働した場合には割増賃金を支払うこと。これらを記載したうえで労使協定を結び、就業規則に記載する必要があります(有効期限を定める必要はありません)。
また、1週間前に週のスケジュールを書面にて通知し、客観的にみてやむを得ない事情以外は変えてはいけません。台風や豪雨などで当初予想した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合のみ、前日までに通知をすることで変更は可能とされています。
例えば、土日が平日に比べて何倍も忙しく、従業員数が少ないため、土日の人数を十分に揃えることができない店舗であれば、平日の休みを多くする分、土日に10時間まで働いてもらうことができるという制度になります。
■一週間単位の変形労働時間制を導入する条件
一週間単位の変形労働時間制の導入にはいくつか条件があります。まずは、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店等の事業であること。1週間40時間を超えて労働した場合には割増賃金を支払うこと。これらを記載したうえで労使協定を結び、就業規則に記載する必要があります(有効期限を定める必要はありません)。
また、1週間前に週のスケジュールを書面にて通知し、客観的にみてやむを得ない事情以外は変えてはいけません。台風や豪雨などで当初予想した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合のみ、前日までに通知をすることで変更は可能とされています。
18歳未満のアルバイトの労働時間について
労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」として区分し、年少者の健康や福祉の確保のためにさまざまな
保護規定を設けています。18歳未満の年少者については、労働時間は原則として1日8時間、週40時間までと定められています。
ただし、例外がいくつかあり、1週間のうちの1日の労働時間を4時間以内にすれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。週休2日であれば、3日間を10時間・2日間を5時間ずつ働いてもらっても、問題ないということになります。 なお、18歳未満の年少者は勤務時間帯にも制限があり、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に勤務させることはできません。
ただし、例外がいくつかあり、1週間のうちの1日の労働時間を4時間以内にすれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。週休2日であれば、3日間を10時間・2日間を5時間ずつ働いてもらっても、問題ないということになります。 なお、18歳未満の年少者は勤務時間帯にも制限があり、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に勤務させることはできません。
働き方改革によりインターバル規制が努力義務に
現状日本で法的規制はありませんが、努力義務で「インターバル規制」が定められています。インターバル規制とは、勤務終了から翌日の勤務開始までに、一定の休息時間を与えることを定めた勤務時間の仕組みです。ヨーロッパでは11時間以上の休息時間を与えることを義務付けており、これを適用すると、22時まで勤務したスタッフは、翌日の9時までは勤務させてはいけないことになります。
日本では2019年4月に施行された「働き方改革関連法」に基づき、前日の終業時刻から翌日 の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが使用者の努力義務と定められました。働き方改革の流れを考えると、日本も今後普及や義務化を検討される規制となりそうです。
日本では2019年4月に施行された「働き方改革関連法」に基づき、前日の終業時刻から翌日 の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが使用者の努力義務と定められました。働き方改革の流れを考えると、日本も今後普及や義務化を検討される規制となりそうです。
着替えの時間は労働時間?
労働基準法において、労働時間とは、労働者が使用者に対して労務を提供し、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。朝礼や新メニューの研修などに関しても、参加が義務付けられているものであれば、労働時間となります。
制服へ着替える時間についても同様で、制服着用が必須である場合は指揮命令下にあるため、労働時間とみなされます。とはいえ、ゆっくり着替える人の労働時間が必要以上に長くなるのは困りもの。労働時間に含まれる着替えの時間を一律5分、または10分と予め決めておくと、労働時間を必要以上に増幅させずに済みます。
制服へ着替える時間についても同様で、制服着用が必須である場合は指揮命令下にあるため、労働時間とみなされます。とはいえ、ゆっくり着替える人の労働時間が必要以上に長くなるのは困りもの。労働時間に含まれる着替えの時間を一律5分、または10分と予め決めておくと、労働時間を必要以上に増幅させずに済みます。
休憩時間の長さと与え方について
労働基準法において、休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。与える位置については特に定めはなく、始業から何時間以内に与えなければならないといった規制もありません。
5時間働いた後、45分の休憩を経てまた1時間働くというように前半と後半の労働時間が極端に違っていても、法律上は問題ありません。しかし、従業員が働きやすいようにバランスよく休憩時間を提供するのは店側としても重要なことといえます。
5時間働いた後、45分の休憩を経てまた1時間働くというように前半と後半の労働時間が極端に違っていても、法律上は問題ありません。しかし、従業員が働きやすいようにバランスよく休憩時間を提供するのは店側としても重要なことといえます。
2店舗で勤務した場合の労働時間の考え方
労働基準法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています。たとえば、同一事業主が経営するA店とB店があったとします。あるスタッフが同じ日にA店で5時間、B店で4時間働いた場合、労働時間は事業場が異なっても通算しなければなりません。このケースでは1日9時間働いたとみなされ、8時間を超える分に対しては割増賃金を支払う必要があります。
スタッフが最高のパフォーマンスを発揮できるように
いかがでしたか。法律上認められているかどうか、適法かということは大事です。一方で、インターバル規制や休憩時間の与え方など、法律に定めや罰則がなくても、スタッフが最高のパフォーマンスを発揮できるような配慮をすることも経営者として必要となってきます。労働時間については両方の視点で考えるようにしましょう。
飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。
【飲食店の労働時間・人件費に関する記事】
■ 知らなきゃマズい「労務知識」!? 飲食店の採用担当が押さえておきたいポイント
■ 飲食店が知っておきたい残業代、深夜割増の算出方法。どこからが残業になる?
■ 飲食店の人件費は売上の30%、その正しい意味とは? 経営者が知っておくべき人件費の考え方
■ 飲食店の人件費はどう考える? 給料・ボーナスを決める基準や算出方法をチェック
飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。
【飲食店の労働時間・人件費に関する記事】
■ 知らなきゃマズい「労務知識」!? 飲食店の採用担当が押さえておきたいポイント
■ 飲食店が知っておきたい残業代、深夜割増の算出方法。どこからが残業になる?
■ 飲食店の人件費は売上の30%、その正しい意味とは? 経営者が知っておくべき人件費の考え方
■ 飲食店の人件費はどう考える? 給料・ボーナスを決める基準や算出方法をチェック