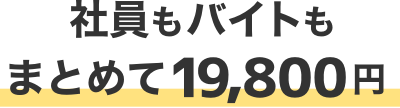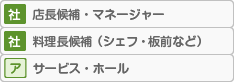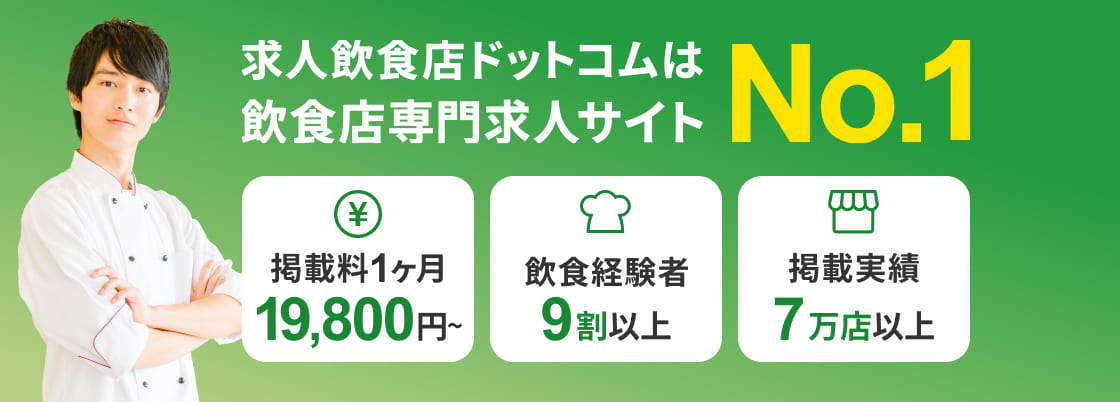画像素材:PIXTA
長すぎる勤務時間に潜む「無駄な時間の使い方」とは
飲食店は営業時間が長いうえ、仕込みや清掃、締め作業といった開店前・閉店後の業務も多いため、一日の勤務時間がどうしても長くなりがちです。こうした勤務時間(拘束時間)の長さは、飲食業に対する「キツい仕事」というイメージを助長する大きな要因の一つとなっています。勤務時間の中には、どうしても削減できない時間がある一方で、次のような「無駄な時間」も多く存在します。
・その日の締め作業を終わらせてから棚卸を始めるなど、効率の悪いタイミングで棚卸をしている
・締め作業に費やす時間が長く、他の従業員が自分の持ち場の仕事を終えても帰宅できない
また、次のような慣例もよく見られます。
・あらかじめ定められた勤務時間が終了してから清掃をする流れができている
・出勤時・退勤時の着替えの時間が勤務時間に含まれていない
効率の悪い働き方や、他の従業員の仕事が終わるのをただ待つだけの時間、労働の基本的なルールを無視した納得感のない慣例などは、従業員のモチベーションを削ぎ、離職を招くことに直結します。こうした「無駄な時間」が隠れていないか見直し、従業員の職場に対する満足度を高めることが大切です。
マルチタスクで勤務時間内に濃く働き、無駄な残業を無くす
人手不足に悩む飲食業では、複数の業務を同時並行で行う「マルチタスク」に取り組む店舗も増えてきています。一人の従業員が特定の業務に集中するのではなく、どの仕事も万遍なくできるようになれば、チームの業務が停滞しづらく仕事の効率が上がります。また、マルチタスク化が進めば縦割りの組織構造が改善され、横との連携が強化されるため、団結力がアップします。仕事の全体像が把握しやすくなったり、従業員同士のコミュニケーションが活性化するといったメリットもあります。新人教育の段階で、マルチタスクをこなせる従業員を育てることを意識してみましょう。
業務の平準化の視点も大切
マルチタスクとともに考えてみたいのが「業務の平準化」です。業務の平準化とは、特定の従業員や時間帯に業務量が偏って集中してしまわないように、業務を均等にすることです。「これは遅番(早番)の仕事だから」「〇〇さんにしかわからないから」状態では、無理や遅れが積み重なっていき、長い勤務時間のモチベーションの低下につながってしまいます。何の業務を、誰が、いつ、どのようにこなしているのかを洗い出し、業務の振り分けを見直してみることも有効です。
求人原稿では「勤務時間」だけでなく「営業時間」も書くのがトレンド
飲食店は勤務時間が長いため、人事担当者は「求人広告に本当の勤務時間を書いたら、応募が来ないかもしれない」と考えがちになります。しかし、勤務時間をごまかしてしまうのはご法度。採用後、従業員に「求人広告に記載されていた勤務時間と実態が違う。不誠実だ」と感じさせ、職場への信頼感を損なって離職を招く原因となります。そこで、近年多くの飲食店が実践しているのが「あらかじめ定めた勤務時間と、営業時間の両方を求人広告に記載する」という方法です。
【勤務時間】10時00分~2時00分 シフト制/休憩あり
【営業時間】11時00分~1時00分
併記することで、「早番は10時までに出勤し、11時までに開店準備を終える。1時までお店が営業しているので、遅番は1時間以内に清掃や締め作業を終える」といったように、具体的な働き方がイメージしやすくなるのです。
具体的な働き方があらかじめイメージできていれば、応募時の不安や、実際に働き始めてからの「こんなはずではなかった」というギャップは少なくなるはず。もちろん、飲食店側も求人広告に記載した勤務時間を遵守できるよう、無駄な時間の削減に勤めましょう。
【関連記事】
■ 飲食店の労務トラブルを防ぐ! 労働基準法に基づく『労働時間』6つのポイント■ 営業時間短縮、土日休み…飲食業界の働き方改革! 正社員が働きやすくなる事例を紹介