約9割の飲食店が酒の注文量に「変化なし」。 「飲酒ガイドライン」の影響を調査
2024年4月22日
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
そこで今回は、こうした指標の発表に対する飲食店の反応や考えを調査するため、飲食店経営者や運営者に対しアンケートを実施。ガイドライン発表から約1か月後のリアルな声をお伝えする。
<本調査について>
■調査概要
調査対象:飲食店ドットコム会員(飲食店経営者・運営者)回答数:404
調査期間:2024年3月8日~2024年3月18日
調査方法:インターネット調査
■回答者について
本調査にご協力いただいた回答者のうち70.8%が1店舗のみを運営。また、回答者のうち東京にある飲食店の割合は52.5%(首都圏の飲食店の割合は67.6%)となっており、こうした背景が結果に影響していると推測される。<調査結果について>
「飲酒ガイドライン」、45.3%の飲食店が「特に何も思わなかった」
はじめに、自店でアルコールメニューを提供しているか尋ねたところ、「提供している」と回答した店舗は、95.6%(※1)となり、本アンケートに回答したほとんどの飲食店が何らかのかたちでアルコールメニューを提供していることがわかった。
(※1)「アルコール提供がメイン・アルコール提供に注力しているお店である」64.9%+「アルコール提供がメインではないが、提供はしている」30.7%

次に、厚労省が今年2月に発表した「飲酒ガイドライン」をきっかけに、お客のアルコールの注文量・注文内容に変化があったかを聞くと、「変化があった」との回答は1.3%に留まり、87.3%が「特に変化はない」と答えた。話題にはなったものの、個人の習慣や意識においてはほぼ影響が見られていない。

次いで「飲酒ガイドライン」の発表に対して、どのような思いを持ったか尋ねた。最も多かったのは「特に何も思わなかった(45.3%)」だったが、続く35.6%は「発表された内容を知らなかった」と回答。一方で、「リスク・脅威だと感じた」との回答も15.8%見られた。

上記の回答の理由については、以下のような声が寄せられた。
<「特に何も思わなかった」理由>
■個人の飲酒意識に影響はなさそう
- お酒に限らず嗜好品というのは、好きな人は嗜むものなので(東京都/洋食/1店舗)
- 飲酒を日常的にされているお客様は、喫煙のリスクと同様に何も感じないと思ったから(神奈川県/洋食/1店舗)
- 酒飲みは、ガイドラインを気にせず、飲みます(東京都/その他/1店舗)
■過度な飲酒が健康に悪影響を与えることは周知の事実だから
- 以前から既知の内容であったし、一般論と大した違いは無い(東京都/和食/3~5店舗
- 昔から健康に良いものとは誰も認識してない。普通に飲む(神奈川県/カフェ/1店舗)
- 今更感が否めない(東京都/イタリア料理/1店舗)
■お客の認知度が低いと思う
- あまり周知されてないと思う(東京都/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
- 飲酒ガイドライン、そのものの知名度が低すぎて何も影響はないと思う(東京都/ラーメン/1店舗)
- 皆さんが認知していないかも(東京都/鉄板焼き・お好み焼/1店舗)
<「リスク・脅威だと感じた」理由>
■アルコールの売上が減少しそう
- 居酒屋なのでドリンクの売上低減になると思った(東京都/鉄板焼き・お好み焼/1店舗)
- 飲酒量が減ると売上にも影響する(東京都/フランス料理/1店舗)
- 予想以上にガイドラインに記載された「適正量」が少なく、おかわりの杯数が減少している。その結果、客単価の減少や来客数の減少に繋がり、売上ダウンになる(長野県/中華/1店舗)
■長期的に見て、飲酒人口が減少しそう
- 少しずつですが、意識に刷り込まれていくだろう。わたし自身も気をつけなければと思っているので無意識に減っていくのだろう(東京都/イタリア料理/2店舗)
- 飲酒もたばこと同じようにみんな控えていくようになるかと思う(東京都/和食/1店舗)
- 若い年代層のアルコール摂取が減っているのにこの発表で更に減りそう(兵庫県/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
<「チャンスだと感じた」理由>
■アルコールをメインに提供する業態ではないため
- 当店は食堂であり、食事を目的に来店される方が圧倒的に多い。居酒屋等に飲みに行かずに当店で食事をして頂きたい(東京都/和食/1店舗)
- お酒メインの居酒屋やバーは脅威なことだと感じますが、レストランだと食事に合わせて飲むので、ペアリングなどの機会も増やせるし、ノンアルも充実させられる可能性はあると感じた(東京都/専門料理/101店舗以上)
■ノンアルコール飲料の売上拡大が期待できる
- 従来よりノンアルカクテル等力を入れてきたが、利益率が高いか手離れの良い商品を売り込む好機だと感じる(福井県/洋食/1店舗)
- ガイドラインと関係なく、お客様の動向から昨年より大幅にノンアルコールドリンクを増やしたから(東京都/バー/1店舗)
- ソバーキュリアスに取り組みだしたところだったので(広島県/カフェ/6~10店舗)
ノンアルコール飲料を提供している飲食店は約8割
続いて、自店におけるノンアルコール飲料(アルコール度数0.00%)の提供の有無について聞いたところ、81.4%が「提供している」と回答。

一方で、低アルコール飲料(アルコール度数10%未満)に関しては、24.3%の提供率に留まった。

さらに、ノンアルコール飲料・低アルコール飲料の提供店舗に、直近一年でそれぞれの注文量が増えたか尋ねると、最多は74.9%の「変わらない」だったものの、「増えた」との回答も22.8%寄せられた。

ノンアルコール・低アルコール飲料の提供状況についてうかがった質問では、「最低限のメニューを用意している」との回答が最も多く、80.2%。「メニュー数・内容など工夫して注力している」という店舗は19.8%で、あくまでも「選択肢を増やす」というところに留まっているようだ。

最後に、ノンアルコール・低アルコール飲料の提供に関する今後の方針について聞くと、58.2%が「現在提供しており、今後も現在と同様に販売していきたい」と回答。次いで「現在提供しており、今後はさらに強化・注力していきたい(15.6%)」、「現在は提供しておらず、今後も方針を変えない予定である(10.6%)」と続いた。この結果からは、多くの店舗が現在の提供形態を大きく変えない意向であることがわかる。

上位の回答の理由については、以下のようなコメントが寄せられた。
<「現在提供しており、今後も現在と同様に販売していきたい」「現在提供しており、今後はさらに強化・注力していきたい」理由>
- お酒を飲まないお客様にも価値ある飲料を提供したいから(神奈川県/居酒屋・ダイニングバー/101店舗以上)
- 飲めない方も多くいるので、特に気にせず提供している。また、飲まない方が飲むものがないと何も注文がないのも困るので、ある程度用意している(東京都/専門料理/1店舗)
- ノンアルコールの需要は増えている。ソフトドリンクだと、客単価が下がってしまうので、見た目が華やかなノンアルコールを増やし、客単価を少しでも上げる必要がある(長野県/中華/1店舗)
<「現在は提供しておらず、今後も方針を変えない」理由>
- あくまでお酒を楽しんでもらいたいから(東京都/バー/1店舗)
- あまり美味しいとは思わないのと、本当に身体にいいのか不明なため(東京都/アジア料理/1店舗)
- ノンアルの需要がどの程度かわからない。ロードサイド店でもないので運転者はほぼ皆無。ソフトドリンクがあれば問題はないと思っています。今後のノンアル需要次第ではないか(千葉県/洋食/1店舗)
適正な飲酒量は個人によって異なるからこそ、ひとつの目安が示されたことは有意義だと言える。とはいえ、飲食店(特にアルコールを提供する業態)においては、売上に影響を与える可能性もあり、それぞれの思いが垣間見えた。ノンアルコール・低アルコール飲料なども、必要に応じて自店のメニューに取り入れていくなど、工夫の幅を拡げていくことができそうだ。
飲食店経営者が集う「飲食店リサーチ」
アンケート調査結果が見れる!店舗経営に役立つ!

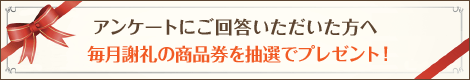
最近のアンケート調査結果
- 食料品消費税ゼロ化について (2026/02/03)
- 月例アンケート:2025年12月の経営状況は? (2026/01/15)
- カテゴリ
- 飲食店経営に関する調査レポート
- その他
- 新着記事
新着記事一覧へ
飲食店リサーチマガジンについて
『飲食店リサーチ』で実施した調査によって得られたデータなど、『飲食店ドットコム』が保有するデータに対し様々な考察を加えて記事を作成。飲食店の経営に役立つ情報を毎月定期配信しています。


