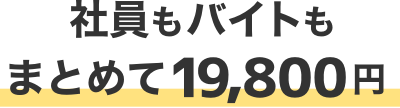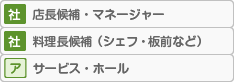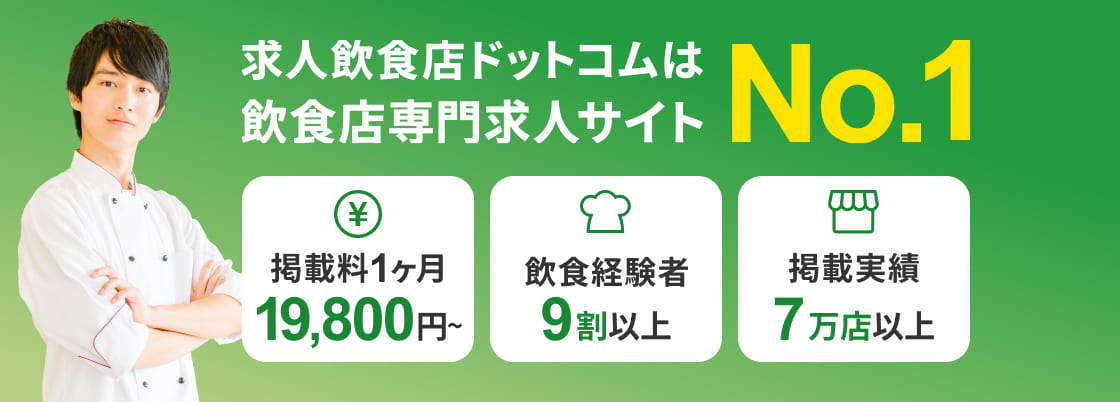画像素材:PIXTA
そもそも…業界用語はなぜ必要なの?
飲食店で業界用語が多く使われている理由は、主に3つあるといわれています。まずは、仕事をする上での意思疎通をスムーズにするため。時間に追われる飲食店においては、普段使っている言葉で説明をしていては、ミスが起きたり、業務が滞ったりする原因になりかねません。例えば「食べ終わったお客さんのお皿を下げてきて」という指示も、業界用語を使えば「バッシングして」と一言で済みます。こうした業界用語は「その職場で働く人」にしかわからないものです。そのため業界用語での会話は仲間意識を強くし、チームワークを高めるメリットも期待できます。
また、業務を行う上で、お客様には聞かれたくないようなことを従業員同士で話す必要があるときにも業界用語は役立ちます。例えば、急にトイレに行きたくなった時や、ゴキブリが出たときなどです。業界用語を使えば「3番行きます」「太郎さんお願いします」とさりげなく意思を伝えることができます。このように、業界用語にはお客様を不快にさせない重要な役割もあるのです。
面接時の多用は応募者との意思疎通の妨げにも…
メリットも多い業界用語ですが、あくまでもその業界で働く人だけが分かる“隠語”のようなもの。そのため、飲食業界未経験者にとっては、「聞いたことがない」「意味が分からない」言葉でしかありません。そのため未経験者を面接する際や、採用した直後には心遣いが必要です。例えば面接時、業務内容を説明する際に、
「ラウンド(手が空いた時にテーブルをまわり、サービスをすること)やワンモア(追加注文を聞く)をお任せしたい」
「毎朝、カスター(各テーブルに置いてある調味料や小物類を入れた容器)のセットや整理も必ずやって欲しい」
「ハンディ(ハンディターミナルの略。オーダーを取る時に使う端末)をつかって」 …などと伝えても、飲食業界未経験者は何をしたらよいのか全く予想することもできません。場合によっては応募者に「コミュニケーションが取りづらい」「未経験者に不親切」といった負の印象を与え、それが採用辞退へとつながる恐れもあります。
また、業界経験者であっても、在籍していた店だけの独自の言い方・使い方をしていた、もしくは、そもそも業界用語をほとんど使っていないという方もいます。「わかっているから大丈夫だろう」と、業界用語を多用すると、途中で会話がかみ合わなくなる可能性も考えられます。面接時や採用後の入社研修時など、「誰にでもわかるように教える」ことが必要な場面では、多用しないようにするのがベターです。
未経験者へは「業界用語」をどう教えるべき?
仕事をするうえで、業界用語を使うことが多い場合は、採用後、未経験者や経験の浅い人を中心に、研修などを通じてしっかりと教え、覚えてもらう必要があります。特に、お客様への配慮を目的として使用している用語に関しては、真っ先に覚えてもらう必要があります。配属される場所でよく使われる業界用語に関しては、その意味を書き添えた用語集などを作っておき、入社時や研修の際に配布するのもいいでしょう。
【ホールの場合】
・ダスター…いわゆる台拭きのこと
・ウェイティング…お客様に待っていただいていること
・バッシング…食べ終わった食器を下げること
【キッチンの場合】
・ポーション…一皿に盛る料理の量
・ストッカー…いわゆる冷蔵庫のこと
・掃除…調理できる状態まで食材を処理すること
スムーズな作業をサポートし、チームワークを高める目的もある業界用語が、未経験&経験の浅いスタッフのストレスになってしまったら本末転倒。「わかっているだろう」「やりながら覚えてもらおう」ではなく、用語を早く一通り理解できるよう、丁寧にサポートするようにしましょう。
【関連記事】
■ 飲食店スタッフのモチベーションをUP! 知っておきたい「目標管理」の基礎知識■ 未経験者を即戦力に! 飲食店における新卒スタッフの育成方法・教育のポイント