飲食店の約6割が経験あり。飲食店の「カスハラ」対応を調査
2020年3月5日
 画像素材:PIXTA
画像素材:PIXTA
■調査概要
調査対象:飲食店.COM会員(飲食店経営者・運営者)
回答数:491名
調査期間:2020年2月3日~2020年2月7日
調査方法:インターネット調査
アンケート結果:カスタマーハラスメントに関するアンケート調査
■回答者について
回答者のうち67.8%が1店舗のみを運営しています。また、東京にある飲食店の割合は56.6%(首都圏の飲食店の割合は74.4%)となっており、こうした背景が結果に影響していると推測されます。
約6割の飲食店がカスハラを経験。説教や居座りなど

まず、各飲食店のカスタマーハラスメント経験の有無を尋ねたところ、「はい」と回答した飲食店は64%。約6割の飲食店がカスハラの被害を受けていることからも、決して他人事ではない問題と言えるだろう。

では飲食店は、具体的にどのようなカスハラ被害にあっているのだろうか。最も多かったのが「必要以上に説教をされた」(56.4%)という回答。なかには運営に役立つ貴重な意見もあるかもしれないが、執拗に謝罪を迫るなど過度な要求が続く場合は、カスハラを疑って間違いないだろう。
次いで「備品を持ち帰られた」(31.2%)、「長時間、居座り続けられた」(30.9%)といった回答が続く。トイレットペーパーなど、備品の窃盗が悪質なのは言うまでもないが、閉店後に退店を促してもなかなか帰ってくれないなど、長時間にわたり店に居続ける行為も店の運営に関わる問題だ。
また、「料理を作り直しさせられた」(19.4%)や「故意にドタキャンをされた」(19.1%)という回答のほか、少数ではあるが「看板で怪我をしたといわれた」(3.5%)という回答もみられた。
カスハラに対する飲食店の様々な対応
アンケートでは、こうしたカスハラの被害を受けた際に、どのような対応を行ったかについても尋ねた。すると、各店で様々な対応をしていることがわかった。
■客が納得するまで謝罪をする
・丁寧に謝罪して納得してもらった。 (愛知県/焼肉/2店舗)
・お客様の言い分を最後までキチンと聞きました。その後は納得されて帰られました。 (秋田県/居酒屋・ダイニングバー/3~5店舗)
目立っていたのが、客が納得するまでひたすら謝罪をし続けるという回答だ。理不尽な言いがかりとはいえ、下手に意見を否定すればさらに相手の怒りを大きくさせることもある。まずは謝罪をし、相手の意見を受け止めることに徹して怒りを鎮めてもらい、ご納得いただこうと考える飲食店が多いようだ。
■退店を促したり、出入り禁止の措置を取る
・こちらに不備のない理不尽なクレームで、他のお客様の迷惑になっていたので、丁重にお断りをして帰ってもらった (鳥取県/居酒屋・ダイニングバー/6~10店舗)
・ある程度までは一旦クレームを受け止めるが、過大な要求や店内雰囲気を壊したり他のお客様のご迷惑になるような場合は退店していただき、出入り禁止にする (大阪府/その他/2店舗)
・あまりに暴言が酷かったので諸々確認、報告の上出禁。 (東京都/その他/101店舗以上)
大声での説教や暴言といったカスハラは、対応したスタッフのモチベーションを下げるだけでなく、純粋に料理を楽しんでいる他の客の迷惑にもなる。店の雰囲気を悪くしないためにも、場合によっては退店を促すほか、その後の出入りを禁止するという声も聞かれた。
■警察に通報をする
・ちょっとした問題をしつこく言ってくるので警察を呼んだ (東京都/ラーメン/3~5店舗)
・あまりに理不尽なお客様の時は、警察に通報しました。近隣の店舗でも同じトラブルを起こしている方でしたので、それからは来店してません。 (愛知県/居酒屋・ダイニングバー/2店舗)
今回のアンケートでは、警察に通報・相談した経験を持つ飲食店もみられた。カスハラは、恐喝や暴行などに発展するケースもあるため、悪質な客に対しては毅然とした対応も時に必要だ。
飲食店の約4割が店内ルールの共有を行い、カスハラを予防

続いて、それぞれの飲食店がカスハラに対しどのような予防策を講じているのか尋ねた。約4割の飲食店が実施していたのが、「店内ルールの共有」(40.1%)。店でのルール(最低限の決まりごと)を客が見える場所に提示したり、口頭で伝えたりすることで、カスハラに発展しそうな問題をあらかじめ潰しておこうと考えている飲食店が多いようだ。
次いで、多かったのが「クレーム対応の従業員への共有」(35.6%)だ。カスハラを行っている客についての情報や、カスハラへの対応経験を従業員同士で共有することで、次に同様のカスハラが起こった際に対応しやすくなる。
また、「防犯カメラ」(23%)や「研修」(9%)、「電話録音」(8.4%)で対策をとるという飲食店もいた。とくに防犯カメラや電話録音は、どちらも記録として残せるため、やった・やっていない、言った・言ってないといった客との不毛な論争も回避できそうだ。
カスハラ予防のために利用したいサービスは?
最後に、今後カスハラ予防としてどのようなサービスを利用したいか伺った。いくつかピックアップしてご紹介する。
・カスハラ予防研修とかマニュアルとかあれば参加したい (東京都/洋食/3~5店舗)
・カスハラに関する事例、対処法を法的な見解を含めたサイト。必要であれば関係機関に協力を仰げるとなお良いかと思います。 (神奈川県/その他/6~10店舗)
・弁護士による法的サービス (東京都/フランス料理/1店舗)
・お客様クレーム対応の代行 (京都府/ラーメン/1店舗)
・ブラックリスト情報の共有サービス (東京都/カフェ/6~10店舗)
・録音、録画に関わるサービス。 (大阪府/居酒屋・ダイニングバー/1店舗)
カスハラに対し、どのような対応をすればいいのか悩んでいる経営者は多いようで、研修や弁護士に相談できるようなサービスを求める回答が多くみられた。なかには、クレームに対応してくれる代行業を求める声も。
また、カスハラ客に関する情報共有サービスが欲しいという声も印象的だった。個人情報などの観点から簡単にとはいかないだろうが、スタッフ間やグループ店間で共有するような体制は整えておきたいところだろう。
客の満足度が売上に直結する飲食店。立場上、どうしても弱くなりやすいが、カスハラはスタッフのメンタルに大きく影響を及ぼす問題でもある。スタッフを守るためにも、クレームに繋がりそうな問題についてはあらかじめ対応策をとり、悪質なカスハラに対しては毅然とした態度で臨みたいものだ。
飲食店経営者が集う「飲食店リサーチ」
アンケート調査結果が見れる!店舗経営に役立つ!

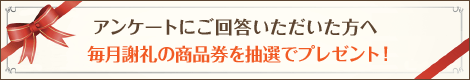
最近のアンケート調査結果
- 月例アンケート:2025年12月の経営状況は? (2026/01/15)
- 飲食店の「労働時間」に関するアンケートのお願い (2026/01/05)
- カテゴリ
- 飲食店経営に関する調査レポート
- その他
- 新着記事
新着記事一覧へ
飲食店リサーチマガジンについて
『飲食店リサーチ』で実施した調査によって得られたデータなど、『飲食店ドットコム』が保有するデータに対し様々な考察を加えて記事を作成。飲食店の経営に役立つ情報を毎月定期配信しています。


