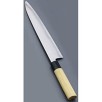Photo by iStock.com/ronstik
仕入れコストを軽減する方法の1つに「魚をまるごと仕入れ、自分の店でさばく」ことが挙げられます。そこで今回は、魚をさばくために必要な調理器具と選ぶポイントをまとめてご紹介します。
まず必要なのは、魚専用のまな板。まな板の素材はさまざまですが、鍛造製の和包丁を使う場合、木材がベストです。その理由はずばり、刃こぼれがしにくいため。木製のまな板には、適度な弾力があるので繊細な刃が傷つきにくいのです。また木材には抗菌作用もあります。
プロの料理人がよく使う木の材質は「イチョウ」です。木の香りがほとんどなく、匂い移りせず素材の風味をよく保ちます。「朴(ほお)の木」や高級な「ヤナギの木」も人気です。また刃当たり良く加工された、ポリエチレン製などのまな板も使われています。
■包丁
魚をさばくのに重要なポイントは「切れ味」です。和包丁の材質は「鋼」タイプと「ステンレス」タイプがありますが、「鋼」タイプの方が切れ味、切れ味の持続性などに優れています。中でも硬度や使い勝手の点から「青鋼」、コスパの点からは「白鋼」がオススメです。また、製造方法については、最良のものが鋼のみで鍛造した「本焼」です。ただし、使いこなすには十分な経験、高度な技術が必要。いわば料理人の憧れの包丁です。
そしてほとんどの料理人が使っているのが「合わせ包丁」。これは、鋼と軟鉄を鍛接・鍛造したもので、切れ味よく研ぎやすい仕上がりになっています。ステンレスタイプでは、安来鋼「銀三」がオススメ。硬度が鋼タイプと同程度にあり、切れ味がよく、研ぎやすくメンテナンスしやすいという特徴があります。
さらに魚をさばくためには、それぞれ形がことなる下記の3本を用意しておくとよいでしょう。
・出刃
骨を切る、身を卸す、頭を割るなど魚をさばくのに必須の出刃包丁。ほかの包丁に比べ、刃には厚みと重みがあります。サイズは魚の大きさや厨房の広さにもよりますが、70cm以上の魚をさばくには、刃渡り180mmのものが目安となります。アジなど小さな魚をさばくには、105~120mmのものが適しています。また、刃の厚みが出刃よりも薄く細身の「相出刃」は、魚を2枚3枚におろしたり、皮引き・きざみ切り出しなどにも向いています。
・柳刃包丁
刃が薄く切れ味がするどい刺身包丁です。刺身を造るには、一度に引き切りをした方が身をつぶさず、角が立ち美味しくなるので刃渡りは270mm、300mmなど長めの方がベターです。厨房の広さによっては、240mmの方が使いやすい場合もあります。
・砥石
「鋼」タイプのものは「ステンレス」タイプよりも錆びやすいので、日常的にメンテナンスが必要です。そこで必須となるのが砥石。砥石の荒さは粒度という数字で表し、小さいほど荒く、大きいほど細かくなります。日々のメンテナンスには、#400〜1500程度、さらに切れ味よく使うには仕上げ用の#3000以上が適しています。

■うろこ取り
アジなどは出刃包丁でうろこを取ることが多いですが、タイなど「うろこ」がしっかりしたものや、大量に魚をさばく際には「うろこ取り」を使うと良いでしょう。飛び散らない、衛生的なもの、耐久性があるものを選びましょう。
■骨抜き
小骨を抜くには「毛抜き」のタイプがよく使われます。身の緩いイワシやサンマ、身割れの恐れがあるサバの小骨を丁寧に取るのにピッタリです。中骨、腰骨抜きや、サケなどのピンボーン抜きには、「ペンチ」タイプが向いています。
いかがでしたか?魚を丸ごとさばくと仕入れのコストカットだけでなく、アラなども使うことが出来るため、メニューの幅が広がります。ぜひ道具選びの参考にしてください。
魚をさばくのに必要な調理器具がこちら!
■まな板まず必要なのは、魚専用のまな板。まな板の素材はさまざまですが、鍛造製の和包丁を使う場合、木材がベストです。その理由はずばり、刃こぼれがしにくいため。木製のまな板には、適度な弾力があるので繊細な刃が傷つきにくいのです。また木材には抗菌作用もあります。
プロの料理人がよく使う木の材質は「イチョウ」です。木の香りがほとんどなく、匂い移りせず素材の風味をよく保ちます。「朴(ほお)の木」や高級な「ヤナギの木」も人気です。また刃当たり良く加工された、ポリエチレン製などのまな板も使われています。
■包丁
魚をさばくのに重要なポイントは「切れ味」です。和包丁の材質は「鋼」タイプと「ステンレス」タイプがありますが、「鋼」タイプの方が切れ味、切れ味の持続性などに優れています。中でも硬度や使い勝手の点から「青鋼」、コスパの点からは「白鋼」がオススメです。また、製造方法については、最良のものが鋼のみで鍛造した「本焼」です。ただし、使いこなすには十分な経験、高度な技術が必要。いわば料理人の憧れの包丁です。
そしてほとんどの料理人が使っているのが「合わせ包丁」。これは、鋼と軟鉄を鍛接・鍛造したもので、切れ味よく研ぎやすい仕上がりになっています。ステンレスタイプでは、安来鋼「銀三」がオススメ。硬度が鋼タイプと同程度にあり、切れ味がよく、研ぎやすくメンテナンスしやすいという特徴があります。
さらに魚をさばくためには、それぞれ形がことなる下記の3本を用意しておくとよいでしょう。
・出刃
骨を切る、身を卸す、頭を割るなど魚をさばくのに必須の出刃包丁。ほかの包丁に比べ、刃には厚みと重みがあります。サイズは魚の大きさや厨房の広さにもよりますが、70cm以上の魚をさばくには、刃渡り180mmのものが目安となります。アジなど小さな魚をさばくには、105~120mmのものが適しています。また、刃の厚みが出刃よりも薄く細身の「相出刃」は、魚を2枚3枚におろしたり、皮引き・きざみ切り出しなどにも向いています。
・柳刃包丁
刃が薄く切れ味がするどい刺身包丁です。刺身を造るには、一度に引き切りをした方が身をつぶさず、角が立ち美味しくなるので刃渡りは270mm、300mmなど長めの方がベターです。厨房の広さによっては、240mmの方が使いやすい場合もあります。
・砥石
「鋼」タイプのものは「ステンレス」タイプよりも錆びやすいので、日常的にメンテナンスが必要です。そこで必須となるのが砥石。砥石の荒さは粒度という数字で表し、小さいほど荒く、大きいほど細かくなります。日々のメンテナンスには、#400〜1500程度、さらに切れ味よく使うには仕上げ用の#3000以上が適しています。

Photo by iStock.com/FotoCuisinette
■うろこ取り
アジなどは出刃包丁でうろこを取ることが多いですが、タイなど「うろこ」がしっかりしたものや、大量に魚をさばく際には「うろこ取り」を使うと良いでしょう。飛び散らない、衛生的なもの、耐久性があるものを選びましょう。
■骨抜き
小骨を抜くには「毛抜き」のタイプがよく使われます。身の緩いイワシやサンマ、身割れの恐れがあるサバの小骨を丁寧に取るのにピッタリです。中骨、腰骨抜きや、サケなどのピンボーン抜きには、「ペンチ」タイプが向いています。
いかがでしたか?魚を丸ごとさばくと仕入れのコストカットだけでなく、アラなども使うことが出来るため、メニューの幅が広がります。ぜひ道具選びの参考にしてください。
包丁・まな板の商品一覧はこちら
殻むき機・骨抜き・ウロコ取りの商品一覧はこちら
<関連記事>まな板はここまで進化した! 今、選ぶべき「おすすめ20選」
<関連記事>日本製の包丁に世界が熱い注目! するどい切れ味に豊富な種類が魅力